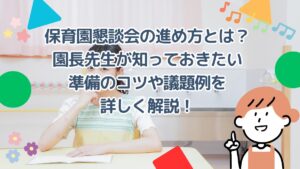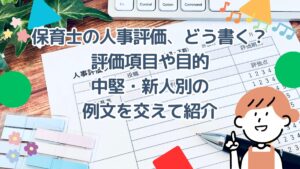保育士採用が難しい理由と解決策を徹底解説!選ばれる園になるためのポイント
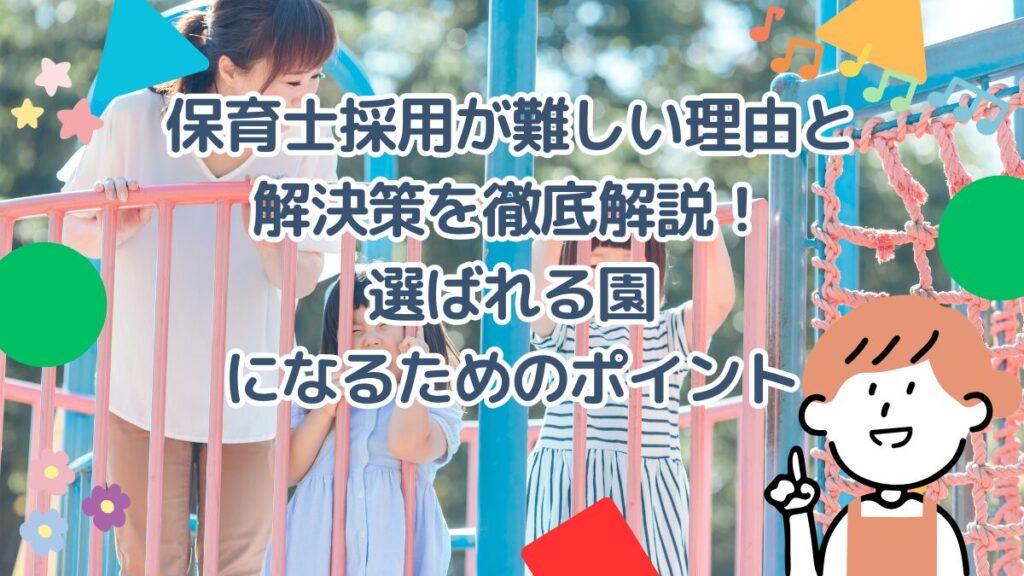
「求人を出しても応募が来ない…」「どうすれば、うちの園を選んでもらえるのだろうか?」
保育士の採用活動において、このような悩みを抱えている園長先生や採用担当者の方は多いのではないでしょうか。
少子化が叫ばれる一方で、保育士の有効求人倍率は依然として高く、保育業界全体で人材獲得競争は激化の一途をたどっています。ただ待っているだけでは、必要な人材を確保することは困難な時代です。
本記事では、なぜ保育士の採用がこれほどまでに難しいのか、その背景にある根本的な理由を深掘りします。さらに、給与や待遇の見直し、働きやすい環境づくりといった具体的な解決策から、明日からでも始められる求人活動の工夫まで、貴園が「保育士に選ばれる園」になるためのヒントを詳しく解説します。
保育士採用の現状|有効求人倍率は依然として高い水準

保育士不足は、今や保育業界全体が直面する深刻な課題です。多くの保育園で人材確保に苦戦しており、その厳しさは年々増しています。まずは、客観的なデータから保育士採用の現状を把握しましょう。
全国の有効求人倍率の推移
厚生労働省の発表によると、保育士の有効求人倍率は高い水準で推移しています。例えば、令和7年1月時点での全国平均は3.78倍となっており、これは求職者1人に対して3件以上の求人があることを示しています。 全職種の平均有効求人倍率と比較しても非常に高く、保育士がいかに「売り手市場」であるかが分かります。特に都市部ではこの傾向が強く、保育園同士での人材獲得競争が激化しているのが実情です。
| 年度(1月時点) | 保育士の有効求人倍率(全国平均) |
| 令和6年 | 3.54倍 |
| 令和7年 | 3.78倍 |
待機児童問題と保育の受け皿整備の状況
待機児童問題の解消に向けて、国や自治体は保育の受け皿となる施設の増設を進めてきました。その結果、待機児童数は減少傾向にありますが、一方で新たな課題が浮き彫りになっています。それは、施設の増加に保育士の供給が追いついていないという問題です。
新しい保育園が増えれば増えるほど、必要な保育士の数も増加します。結果として、保育士の需要は高まり続け、採用の難しさに拍車をかけているのです。
保育士の採用が難しいと言われる5つの理由
なぜ、これほどまでに保育士の採用は難しいのでしょうか。その背景には、保育士という仕事を取り巻く複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、主な5つの理由を掘り下げて解説します。
他業種と比較して賃金が低い
採用が難しい最も大きな理由の一つが、賃金の問題です。保育士の仕事は、子どもの命を預かるという大きな責任が伴う専門職であるにもかかわらず、その給与水準は全産業の平均と比較して低い傾向にあります。責任の重さや業務量に見合った対価が得られていないと感じる人が多く、これが保育士を目指す人が増えない、あるいは離職してしまう大きな原因となっています。
責任の重さと業務負担の大きさ
保育士の仕事は、子どもの保育だけにとどまりません。保護者への対応、指導計画や保育日誌の作成といった事務作業、季節ごとの行事の企画・準備など、その業務は多岐にわたります。
近年、保育のデジタル化も進んではいますが、まだまだ手作業が多く残る園も少なくありません。限られた人員の中でこれらの業務をこなさなければならず、結果として持ち帰り仕事やサービス残業が常態化し、心身ともに大きな負担となっています。
休みが取りづらく、ワークライフバランスが保ちにくい
共働き家庭の増加に伴い、保育園には早朝や延長、休日保育など、多様なニーズへの対応が求められています。しかし、慢性的な人手不足からシフト制の維持が難しく、希望通りに休暇を取得したり、連休を取ったりすることが困難な職場も少なくありません。プライベートとの両立が難しく、特に結婚や出産といったライフステージの変化を機に離職を選択する保育士が多いのが現状です。
職場の人間関係に対する不安
保育園は、職員同士はもちろん、子どもや保護者といった多くの人と密接に関わる職場です。職員間のチームワークが不可欠ですが、保育観の違いから対立が生まれたり、閉鎖的な環境で人間関係がこじれたりすることも少なくありません。
また、一部の保護者からの過度な要求やクレーム対応に一人で悩んでしまうケースもあります。こうした人間関係のストレスが、離職の引き金になることも多いのです。
資格を保有していても保育士として働かない「潜在保育士」の存在
保育士資格を持ちながらも、保育現場で働いていない「潜在保育士」が多数存在することも、採用を難しくしている一因です。厚生労働省の調査では、保育士資格を持つ人のうち、半数近くが保育士として就職していないというデータもあります。 これまで挙げたような労働条件や環境の問題から、資格は取得したものの、保育の仕事を選ぶことをためらったり、一度離職した後に復職をためらったりする人が多いのです。
難しい保育士採用を成功させるための具体的な対策

採用難の時代だからこそ、ただ待つだけでなく、保育園側から積極的に働きかけていく姿勢が重要です。ここでは、保育士から「選ばれる園」になるための具体的な対策を5つご紹介します。
給与・福利厚生などの待遇を改善する
採用の決め手として、給与や賞与といった待遇面は非常に重要です。国の処遇改善加算などを活用し、基本給のアップや手当の充実を図ることが、最も直接的で効果的な対策と言えるでしょう。また、住宅手当や借り上げ社宅制度など、職員の生活をサポートする福利厚生を充実させることも、他園との差別化につながり、大きなアピールポイントとなります。
ICTシステム導入で業務負担を軽減する
保育士の大きな負担となっている事務作業や書類作成は、ICTシステムの導入によって大幅に効率化できます。例えば、登降園管理や保護者への連絡、指導計画の作成などをデジタル化することで、保育士は事務作業に費やしていた時間を、子どもと向き合う時間や研修の時間に充てることができます。業務負担の軽減は、離職率の低下と定着率の向上に直結します。
多様な働き方を認め、休暇を取得しやすくする
全ての職員がフルタイムで働くことを前提とするのではなく、パートタイムや時短勤務など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を認めることも有効です。多様な働き方を導入することで、子育て中の保育士や復職を希望する潜在保育士など、これまで採用が難しかった層にもアプローチできます。また、職員を増やすことで一人当たりの業務負担が減り、有給休暇を取得しやすい環境も整います。
風通しの良い職場環境を構築する
職員が安心して長く働ける職場であるためには、良好な人間関係が欠かせません。定期的な面談を実施して職員の悩みや不満を早期に把握したり、職員同士の交流を深めるためのイベントを企画したりするなど、コミュニケーションを活性化させる取り組みが大切です。園長や主任が率先して、何でも相談しやすい雰囲気を作ることを心がけましょう。
人事評価制度を見直し、キャリアパスを明確にする
自分の頑張りが正当に評価され、給与や処遇に反映される仕組みは、仕事へのモチベーションを大きく左右します。客観的で透明性の高い人事評価制度を導入し、評価基準を明確にしましょう。また、研修制度を充実させ、主任やリーダーといった役職へのキャリアパスを示すことで、保育士が将来の目標を持って意欲的に働き続けられるようになります。
応募者を増やすために明日からできる採用活動の工夫
魅力的な職場環境を整えることと並行して、その魅力を求職者に効果的に伝える工夫も必要です。ここでは、採用活動においてすぐに実践できる3つのポイントをご紹介します。
園の魅力を伝えるキャッチコピーを考える
数多くの求人情報の中から自園を選んでもらうためには、求職者の心に響くキャッチコピーが効果的です。「残業月平均5時間以内!プライベートも充実」「産休・育休復帰率100%!ママさん保育士が活躍中」のように、具体的な数字や事実を盛り込むことで、求職者は働くイメージを具体的に持つことができます。園の最もアピールしたいポイントを、簡潔で魅力的な言葉で表現してみましょう。
求める人物像を明確にし、求人票に具体的に記載する
「保育士募集」といった漠然とした内容ではなく、「0歳児クラスの増員に伴う募集です。乳児保育の経験がある方、歓迎します」のように、求める人物像や仕事内容を具体的に記載することが大切です。これにより、園が求めている人材と、求職者の希望とのミスマッチを防ぐことができます。また、応募する側も自分のスキルや経験が活かせるかどうかを判断しやすくなります。
園の雰囲気が伝わる写真や動画を積極的に活用する
求人票の文章だけでは伝えきれない園の温かい雰囲気や、生き生きと働く職員の姿、子どもたちの笑顔は、写真や動画を使うことでよりリアルに伝えることができます。園のホームページやSNSで日常の様子を発信したり、ウェブ説明会で園内を案内したりするのも良いでしょう。求職者が「この園で働いてみたい」と感じられるような、視覚的な情報発信を心がけましょう。
まとめ

保育士の採用が難しい現状は、今後も続くと考えられます。
この厳しい状況を乗り越えるためには、採用難の理由を正しく理解し、職員から「選ばれる園」になるための地道な努力が不可欠です。待遇改善や業務負担の軽減、働きやすい環境づくりに取り組み、その魅力を効果的に発信することで、採用成功への道は開けます。本記事で紹介した内容を参考に、ぜひ貴園の採用活動を見直してみてください。
併せて、採用業務の効率化を図りたい方は、LINEを活用した採用支援ツール「採用担当らいん君」の導入もご検討ください。応募者とのスムーズなやり取りや選考フローの自動化により、採用業務の手間を大幅に軽減できます。詳しくはこちらをご覧ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。