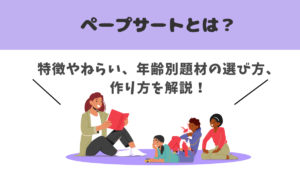【保育士必見!】保育園の避難訓練のポイントとは?災害別の実施内容も解説!
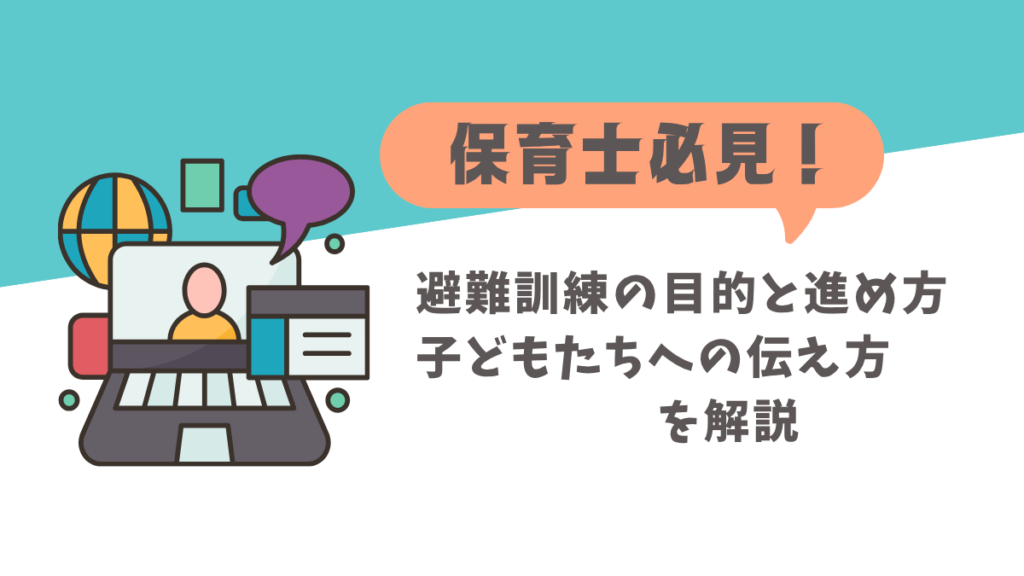
保育園や幼稚園では、子どもたちの命を守るために日常的な備えが欠かせません。その中でも「避難訓練」は、万が一の災害や事故に備える最も重要な取り組みのひとつです。
しかし現場では「形だけになってしまっているのでは?」と不安を抱く保育士や、「子どもたちにどう伝えればよいかわからない」と悩む声も少なくありません。
本記事では、避難訓練の目的や立場別の必要性、災害ごとの具体的な実施内容、子どもへの伝え方の工夫までを体系的に解説します。厚生労働省や消防庁のガイドラインなど公的資料も引用し、実務にすぐ活かせるポイントを紹介しているので、是非参考にしてください。
目次
保育園/幼稚園における避難訓練の目的

避難訓練の目的は、関わる立場によって少しずつ異なります。それぞれの視点を理解することで、より多角的に訓練の意義を捉えられます。
保育士視点での目的
保育士にとって避難訓練は「危機対応スキル」を養う場です。例えば、消防庁の「自主防災組織の手引」でも「避難経路を熟知しているか」「非常時に子どもを安全に誘導できるか」が強調されています。
また、心理学的に「緊急時に人は普段の行動習慣に従いやすい」という研究結果があります。繰り返しの訓練が実際の行動を左右するのです。
参考:消防庁「自主防災組織の手引」
子ども視点での目的
子どもにとって避難訓練は「生きるための学び」です。大きな音や突然の揺れにパニックになりやすいため、事前に「避難の流れ」を経験しておくことが安心感につながります。
特に未就学児は抽象的な説明だけでは理解が難しいため、絵本や遊びを通じた体験的な学びが有効です。教育心理学では「安心できる繰り返し経験」が恐怖を和らげる効果を持つとされています。
保護者視点での目的
保護者にとっては「園が安全対策をきちんと行っているか」が信頼につながります。避難訓練の様子をニュースレターや写真で共有すると、園への安心感が高まります。
内閣府「防災基本計画」にも「住民への周知・広報の重要性」が記されており、保護者との情報共有は園運営に欠かせない要素です。
参考:内閣府「防災基本計画」
避難訓練を行う際の事前準備
実効性のある避難訓練を行うためには、事前準備が欠かせません。計画性と準備がしっかりしていることで、当日の訓練がスムーズに進み、子どもや職員にとって安心感を持てる学びの場となります。
年間計画表の作成
内閣府や自治体の防災指針では、保育施設における避難訓練は「年複数回」の実施が推奨されています。年間計画を立てて、地震・火災・水害・不審者侵入など複数のケースを網羅することが重要です。事例として、ある自治体のモデル園では、毎月異なる想定で小規模な訓練を繰り返すことで、子どもたちが自然と避難行動を覚えたという報告があります。
マニュアルの作成
避難訓練は職員全員が同じ手順を理解していることが前提です。そのためには「避難経路」「集合場所」「役割分担」を明記したマニュアルが不可欠です。消防庁の『自主防災組織の手引』でも、明文化されたマニュアルの有無が緊急時対応の成否を左右すると示されています。心理学的にも「不安が強い状況では明確な行動指針があると安心感が高まる」ことが知られています。
防災グッズを揃える
避難訓練を現実的に行うためには、防災グッズの準備も欠かせません。非常食・飲料水・救急用品・懐中電灯・ホイッスルなど、基本的な備蓄を整えておく必要があります。文部科学省の『学校防災マニュアル作成の手引き』でも、備蓄品は「人数×3日分」が推奨されています。また、実際の園では「非常用リュックを子どもの年齢に合わせて軽量化する」などの工夫も効果的です。
参考:文部科学省『学校防災マニュアル作成の手引き』
【災害別】避難訓練の実施内容

災害の種類によって避難の手順や注意点は異なります。ここでは、代表的な災害ごとの避難訓練の進め方を整理します。
地震の場合…
地震発生時はまず「身の安全の確保」が最優先です。消防庁の防災マニュアルでは、強い揺れを感じたらすぐに「頭を守り机の下へ隠れる」行動を促すよう指導されています。実際の保育園でも「ダンゴムシのポーズ(体を小さく丸める)」を合言葉に、子どもたちが素早く動けるように工夫している事例があります。
参考:消防庁「防災マニュアル」
火災の場合…
火災時には「煙を吸わないように低い姿勢で避難する」ことが重要です。内閣府の資料では、火災の被害は煙による窒息が大半を占めるとされ、避難時の姿勢指導が欠かせません。実際の園では「濡れたタオルで口を覆う」練習を取り入れることで、子どもが楽しみながら理解できたという例もあります。
参考:総務省消防庁「火災からの避難」
水害の場合…
水害時には「園内に留まるか避難するか」の判断が極めて重要です。国土交通省のガイドラインでは、洪水が迫る際には原則として高い場所への移動が推奨されています。ある園では実際に地域のハザードマップを使って避難先を確認する訓練を行い、保護者からも高評価を得ました。
参考:国土交通省「地域の水害危険性の周知 に関するガイドライン」
不審者が侵入した場合…
不審者対応は災害とは異なり、心理的な恐怖心を伴うため特に難しい訓練です。文部科学省の『学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル』では「子どもを安全な部屋へ誘導」「110番通報の徹底」「複数職員で対応」が推奨されています。事例として、ある園では「鍵をかけて隠れる訓練」を繰り返し行うことで、子どもたちが遊び感覚で学べたという成果がありました。
参考:文部科学省の『学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル』
子どもたちに避難訓練を伝えるポイント
避難訓練は「子どもたち自身が安全に動けるようになること」が最終目的です。幼児期は抽象的な説明では理解しにくいため、わかりやすい言葉や遊びを通じて伝える工夫が求められます。心理学でも「子どもは繰り返し体験することで不安を減らし、安心感を得る」とされています。ここでは代表的な方法を紹介します。
合言葉
災害時に子どもがとっさに行動できるように、短い言葉でルールを覚えてもらう方法です。
「お・か・し・も・ち」
・お:押さない
・か:駆けない
・し:しゃべらない
・も:戻らない
・ち:近づかない(火や危険に近寄らない)
消防庁でも広く推奨されており、火災避難時に有効とされています。実際の園では壁にポスターを貼り、歌にして覚える工夫をしている事例もあります。
「い・か・の・お・す・し」
・い:行かない(知らない人について行かない)
・か:帰る(危険を感じたらすぐ帰る)
・の:乗らない(知らない人の車に乗らない)
・お:大声を出す
・す:すぐ逃げる
・し:知らせる
これは不審者対策の標語で、警察庁も子ども向けに広く活用しています。園内での安全教育にも応用できる言葉です。
絵本や紙芝居
子どもたちはストーリーを通じて学ぶ力が高いため、防災をテーマにした絵本や紙芝居が効果的です。例えば、地震時の身の守り方を描いた絵本を繰り返し読み聞かせることで、自然に行動が定着します。心理学でも「安心できる物語の繰り返し」は恐怖心の低減につながるとされています。
クイズ
「地震が来たらどうする?」などクイズ形式で問いかけると、子どもたちが楽しみながら答え、行動を確認できます。実際の園では「正解したらシールをもらえる」といった仕組みを導入し、意欲的に参加する姿が見られます。
まとめ
避難訓練は「命を守るための教育」であり、園の信頼を高める大切な取り組みです。保育士・子ども・保護者それぞれの視点を踏まえ、事前準備から災害別の対応、子どもへのわかりやすい伝え方までを整えることで、安心できる園づくりが実現します。
また、職員不足や情報共有不足があると訓練の質は低下してしまいます。そのため、園全体での体制づくりや情報発信が欠かせません。
株式会社チポーレの提供する「採用担当らいん君」は、保育士採用を効率化し、職員体制を安定させる支援ツールです。避難訓練を含む園の安全体制を強化するためには、人材確保と定着が大前提となります。日常の安全確保と人材基盤の両立を目指し、ぜひ参考にしてみてください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。