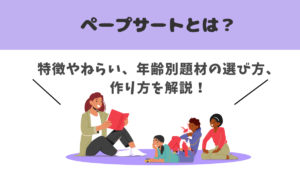不適切保育の具体例とは?保育現場で起こりやすい原因や防止策を解説!
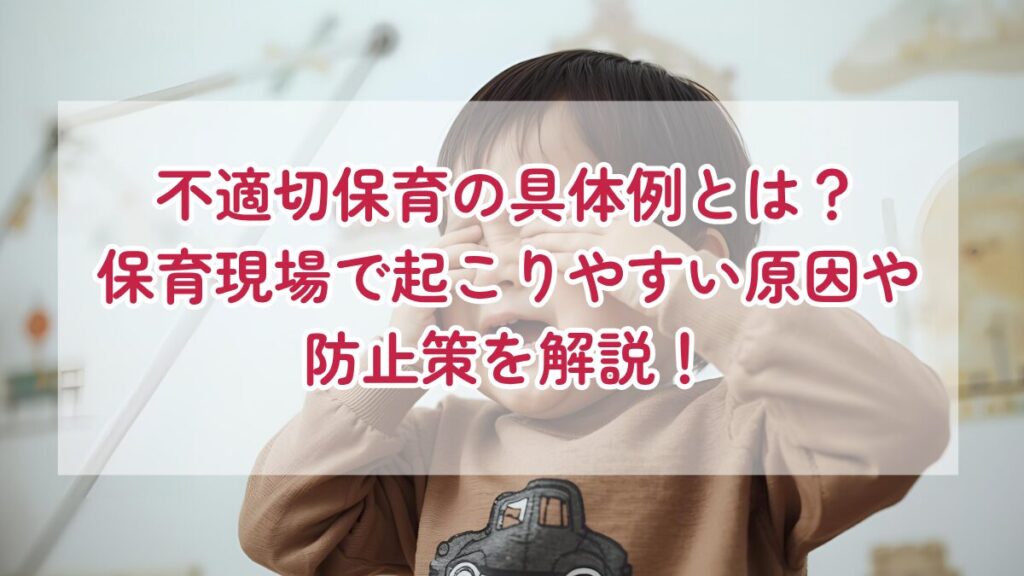
「不適切保育」という言葉は近年、ニュースや行政の報告で頻繁に取り上げられています。しかし、現場で子どもと向き合う保育士や園を運営する園長にとっては、「どこからが不適切なのか」「どうすれば未然に防げるのか」が分かりづらい部分も少なくありません。
しかしながら不適切保育がひとたび報道されれば、在園児や保護者との信頼関係にひびが入るだけでなく、園内外への対応に追われることになります。さらに長期的には、保育士採用や園児募集にも大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
そこで本記事では、国が示す定義や実際の事例を取り上げながら、不適切保育が起こる原因と防止策を整理しました。より健全な保育園運営のために、園長・保育士が押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。
目次
不適切保育とは何か

まずは不適切保育とは何か、その基本を整理しておきましょう。こども家庭庁や厚生労働省はガイドラインや指針の中で、不適切保育の考え方や具体的な例を示しています。明確に法律で決まっていないからこそ、こうした公的な基準を理解しておくことで、園内で共通の認識を持ちやすくなります。
不適切保育の定義
こども家庭庁が2023年に策定した「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」では、不適切保育を「保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為」と定義しています。
これは法律上(法第三十三条の十各号)の「児童虐待」とは異なり、直接的に違法行為に該当していない場合でも、間接的に子どもの成長を妨げる関わりがあれば不適切保育と定義しています。つまり「犯罪ではないから大丈夫」ではなく、日常の小さな行動でも子どもに悪影響を与える場合は不適切保育に当たる可能性があるのです。
引用:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
こども家庭庁による不適切保育の位置付け
「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」では、不適切保育に該当する行為の例として以下が挙げられています。
―「早く食べないとお外で遊べないよ」と脅すように促す
―「どうしてこんなこともできないの」と人格を否定するような言葉を繰り返す
―感情的に大声で叱責し、子どもを萎縮させる
・子どもを長時間にわたり叱責や隔離をする
―泣き止むまで一人きりで別室に閉じ込める
―クラス全員の前で繰り返し叱り続ける
―教室の隅に立たせたまま、長時間レクリエーションに参加させない
・援助を必要としているのに意図的に無視する
―体調が悪そうにしている子を放置し、必要な看護をしない
―泣き続けている子どもに声をかけず、抱き上げずに無関心を装う
―着替えや排泄の援助を求めても、あえて手を貸さない
・差別的な言動や扱いをする
―「あの子はできるのに、あなたはできない」と他児と比較して貶める
―特定の子だけおもちゃや活動に参加させず、仲間外れにする
―国籍や障害の有無などを理由に、違う扱いをする
これらは一度の行いでも問題となる場合がありますが、特に繰り返されると深刻な被害や園全体の保育の質悪化につながります。そのため園は「どんな行為が不適切保育にあたるのか」を明文化し、職員全員で確認と振り返りができる仕組みをつくることが重要です。
不適切保育が与える子どもへの影響
不適切保育が繰り返されると、子どもには以下のような深刻な影響が現れる可能性があります。
- 自己肯定感の著しい低下
- 集団生活や人間関係に対する強い不安感
- 学びや遊びに対する意欲の喪失
これらは一時的な心の揺らぎではなく、長期的に人格形成や社会性の発達に重大な障害を残すことがあります。心理学的にも、幼少期に不適切な対応をされた子どもは、「愛着の不安定化」や「学習性無力感」を引き起こし、心身に深い傷を残すことが立証されています。
例えば、幼少期に継続的に威圧的な言葉や無視を受け続けた子どもは、大人になってからも「自分は価値がない」という感覚を抱きやすく、人間関係の構築に大きな困難を抱えることが分かっています。さらに、海外の研究では、虐待や不適切な養育を経験した子どもが成長後に反社会的行動(暴力・犯罪など)に巻き込まれるリスクが高まることも指摘されています。
つまり不適切保育は、その場の「しつけ」や「指導」の問題にとどまらず、子どもの一生に関わる深刻な影響をもたらし得るということを、保育者一人ひとり、そして園全体で充分に理解しておきましょう。
過去の不適切保育事例を紹介

実際に起きた不適切保育の事例を知ることは、園での再発防止に欠かせません。報道や自治体が公表したケースには、多くの教訓があります。ここでは、近年の代表的な事例と訴訟に発展したケースを紹介します。
報道で取り上げられた不適切保育の具体例
中野区立保育園のケース
東京都中野区の公立保育園で、保育士が園児をうつ伏せにし、自身の両足を園児の足の上に乗せて動けない状態にする行為がありました。この対応は園児の身体的自由を奪う不適切保育とされ、区の調査を受けて発覚しました。行政は再発防止に向けた研修や体制の見直しを指導しています。
秦野市認定こども園のケース
神奈川県秦野市の認定こども園では、給食中に園児を叩いたり、落ち着かせる目的で園児を両足で持ち逆さづりにする行為が報告されました。第三者委員会の調査により、これらが身体的・心理的虐待と認定され、園には改善指導が入りました。
大和市の保育園長によるケース
神奈川県大和市の保育園では、園長が園児を逆さづりにしたり、給食を無理やり食べさせたりする行為が繰り返されていました。また、「うるせぇよ」「ぶっ飛ばす」といった暴言も確認されています。市の調査で事実が判明し、園長の行為は不適切保育として厳しく問題視されました。
訴訟や逮捕にまで発展したケースとその結果
不適切保育は、園や法人の監督責任が問われ、損害賠償を命じられた例もあれば、現場での不適切な行為が刑事事件に発展した例もあります。ここでは代表的な3つのケースを紹介します。
姫路市の認定こども園のケース
給食の量がスプーン一杯だけといった極端に少ない提供や、規定を下回る保育士配置になど、保育環境の実態が劣悪であることが報じられました。これを受けて利用者らが園長を相手取り、慰謝料や保育料の返還を求めて提訴。神戸地方裁判所姫路支部は、園に対し約103万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。(同年にこども園は廃園)
墨田区私立保育園のケース
保育園に勤務していた元保育士が、複数の女子園児に対して性的行為を繰り返していたとして逮捕・起訴されました。裁判では園児7人への不同意性交等の罪が認定され、東京地裁は被告に懲役14年の実刑判決を言い渡しました。
裾野市の私立保育園のケース
1歳児を担当していた保育士3人が、園児の足をつかんで宙づりにする、頭をバインダーでたたくなど、複数の不適切行為を行っていたことが発覚しました。さらに、倉庫に閉じ込める、ズボンを無理に下ろす、容姿を馬鹿にするなど、最大15項目に及ぶ不適切な対応が確認され、3人の保育士は暴行容疑で逮捕されました。
不適切保育が「虐待」と判断される4つのケース

不適切保育の中には、明確に児童虐待防止法で定められた「虐待」に該当する場合があります。こども家庭庁や厚生労働省は、虐待を4つの類型に分けており、園が注意すべき重大な行為を明確にしています。ここではその4つのケースを解説します。
身体的虐待
こどもの身体に外傷を与える、または外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。
例)殴る、蹴る、叩く、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団で覆って動けなくする(布団蒸し)、逆さづりにする、異物を飲ませる、ご飯を無理やり押し込む、食事を与えない、外に閉め出す、縄や紐で身体を縛るなど。
ネグレクト(育児放棄)
こどもの心や体の健やかな成長を妨げるような行為。たとえば、ごはんを極端に少なく与える、長い時間ひとりで放っておくなど。さらに、ほかの子どもからのいじめや暴力を見過ごしたり、本来しなければならない保育士としての役割をおろそかにすることも含まれます。
例)体調不良やケガをしている子を放置する、長時間車内に放置する、泣き続ける子を無視し続ける、汚れた衣服のまま長時間過ごさせる、適切な食事を与えない、視線を合わせたり抱き上げたりするなどの情緒的な関わりを全く持たない、別室に閉じ込める、他の職員や子どもによる虐待を見て見ぬふりをするなど。
心理的虐待
こどもに対する暴言や、拒絶的な対応を行うこと。またこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例)日常的に「バカ」「あほ」などの侮辱的な言葉を投げかける、失敗を執拗に責め立てる、からかいを繰り返す、差別的な扱いをする、無視する、拒絶的な態度をとる、大切にしている物を壊す・捨てる、他の子どもと意図的に隔離する、感情にまかせて怒鳴り続けるなど。
性的虐待
こどもに対してわいせつな行為をする、あるいはわいせつな行為をさせること。
例)必要のない場面で裸や下着のままにする、子どもの性器を触る・触らせる、性的な言葉を無理やり聞かせる・言わせる、わいせつな映像や画像を見せる、性交や性的行為を強要する、ポルノの被写体にさせるなど。
不適切保育が起こる要因とは?

不適切保育は、保育士一人の性格や態度だけでなく、職場環境や人員体制といった背景が影響して起こります。例えば十分な研修が受けられない、人手が足りない、職員同士の連携が不足しているなど、現場の環境が重なることでもリスクが高まります。ここでは、その主な要因を整理します。
保育士個人の知識不足やストレス
保育士の経験が浅かったり、十分な研修を受けていなかったりすると、子どもへの接し方を間違えてしまうことがあります。たとえば「子どもを落ち着かせたい」と思って大声で叱ったり、乱暴な口調になってしまうったりすることは、本人にそのつもりがなくても不適切保育にあたる可能性があります。
また、強いストレスが続くと気持ちに余裕がなくなり、冷静に対応することが難しくなることもあります。心理学の研究でも、ストレスが高い状態では人は感情をコントロールしづらくなり、不適切な言動につながりやすいとされています。
慢性的な人手不足による過重労働
保育士採用の難易度が上がり、多くの園が人手不足に直面しています。人員配置が最低基準ぎりぎりだと、休憩が取れず、子どもの行動に落ち着いて対応する余裕を失いがちです。
こうした状況は、保育の質の低下だけでなく、不適切な言動を引き起こすリスクを高めます。保育士を安定的に確保することは、不適切保育防止の土台です。
職員間の連携不足と閉鎖的な職場環境
園内での情報共有が不十分だったり、職員が自由に意見を言えない雰囲気があると、不適切行為が発生しても見逃されたり、是正が遅れる危険があります。こども家庭庁のガイドラインでは「相談や報告がしやすい職場風土づくり」が明記されており、園全体で取り組むべき課題とされています。
心理学的には、周囲が見ていても誰も止められない「傍観者効果」が働きやすくなることが指摘されており、風通しの良い職場づくりが予防策となります。
保育園全体で取り組むべき不適切保育の防止策
不適切保育を防ぐには、一人ひとりの意識に任せるだけでは限界があります。国のガイドラインでも示されているように、園全体で「未然に防ぐ仕組み」を整え、システム化することが重要です。ここでは、組織的に取り組める主な防止策を紹介します。
定期的な研修で知識と意識をアップデートする
例えば横浜市では「よこはま☆保育・教育宣言~乳幼児の心もちを大切に~」を策定し、基本的な保育に対する考え方を園に向けて共有しています。その一環として、定期的な研修や事例検討を通じて、不適切保育の未然防止を図っています。他の自治体でも定期的な「不適切保育防止研修」を開催していたり、チェックリストを作成するしたりするなどの意識のアップデートに努めています。
全国保育士会 保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト
https://www.z-hoikushikai.com/about/siryobox/book/checklist.pdf
横浜市 よりよい保育のためのチェックリスト~人権擁護のために~
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/jikotaio/hoiku.files/0119_20211213.pdf
職員が意見を言える風通しの良い環境を作る
不適切保育が発生しても「言いにくい雰囲気」があると、問題は放置されがちです。こども家庭庁のガイドラインでは「相談・通報しやすい仕組みづくり」を推奨しており、1on1ミーティングの定期的な設定といった園長や主任が意識的にオープンな場を設けることが重要です。
労働環境を見直し心身の負担を軽減する
慢性的な長時間労働や持ち帰り業務は、職員のストレスを高め、不適切保育のリスク要因となります。園としては、ICTを導入して事務作業を削減する、休憩を確実に取れるようシフトを工夫するなど、労働環境の改善が不適切保育の防止策に直結します。
保育士一人ひとりが今日からできること

園全体の体制整備とあわせて、現場で子どもと接する保育士一人ひとりの意識と行動も重要です。日々の小さな実践が積み重なって、不適切保育を防ぐ大きな力になります。ここでは、今日から取り組める実践例を紹介します。
自身の保育を客観的に振り返る習慣をつける
全国保育士会が公開している「人権擁護のためのセルフチェックリスト」を活用し、自分の言動を振り返る時間を設けましょう。例えば「子どもに威圧的な言葉を使っていないか」「一人ひとりの気持ちに寄り添えているか」を定期的に確認することで、無意識のうちに不適切な対応をしていないかを自分自身で早めに気づけます。
疑問や不安を一人で抱え込まずに相談する
こども家庭庁のガイドラインでは、疑問や不安を感じた際に相談できる環境を整えることが強調されています。個人の判断で「これくらいなら大丈夫」と思い込まず、主任や園長、同僚に気軽に相談することが大切です。
また、園内で解決できない場合は、自治体の相談窓口を利用することも推奨されています。声を上げることで、自分自身を守るだけでなく、園全体の健全な運営にもつながります。
もし不適切保育を見聞きしたらどうする?

不適切保育を目にしたとき、「自分が注意していいのか」「どこに報告すべきか」と迷う職員も少なくありません。しかし放置をしてしまうことは自分自身がネグレクトに加担することになってしまいます。ここでは不適切保育を認知してしまった場合の対応方法を紹介します。
まずは主任や園長に報告・相談する
こども家庭庁のガイドラインでは、不適切保育を見聞きした場合、まず園内の上司に速やかに報告することが求められています。園長や主任に共有することで、事実確認や再発防止策を講じる第一歩となります。
また、報告は口頭だけでなく、日時・状況を簡潔に記録して報告することが推奨されています。後に保護者や自治体への説明が必要になった場合、記録をしておけばスムーズな対応が可能です。
解決が難しい場合は自治体の窓口へ通報する
園内で対応が進まない、または園自体に問題がある場合は、自治体の担当課(保育指導課・子育て支援課など)へ通報しましょう。匿名での相談が可能なケースも多く、職員が不利益を受けないよう制度も整えられています。通報は「園を守るため」ではなく「子どもの権利を守るため」であることを意識することが大切です。
人員配置を手厚くすることが不適切保育を防ぐカギ

不適切保育が起きてしまう背景には「現場に余裕がない」ことが大きく関わっています。国の調査でも、職員不足や過重労働が保育の質を低下させる要因となることが繰り返し指摘されています。ここでは人員配置と不適切保育の関係について整理します。
配置基準と不適切保育の関係
児童福祉法施行規則により、子どもの年齢ごとに必要な保育士数が定められています。たとえば3歳児は「子ども20人に対して保育士1人」が最低基準です。
しかし、この基準はあくまで“最低ライン”であり、実際の保育内容や園児数によっては、より手厚い配置が必要です。基準ぎりぎりでは余裕がなく、職員一人の負担が増え、結果細かいところに気を配ることができず、不適切な対応が起きやすくなります。
余裕ある人員配置がもたらす安心と信頼
人員に余裕があると、保育士は一人ひとりの子どもに丁寧に関われます。例えば「食事に時間がかかる子へゆっくり付き添う」「気持ちが不安定な子に寄り添う」といった余裕が生まれます。逆に人手が不足していると「他のこどもと活動をそろえるために強い語気で促す」「こどもの気持ちや状況に十分に耳を傾けられない」といった場面が増え、不適切保育につながりかねません。
また、保護者にとっても「先生が慌ただしくない」「相談をじっくり聞いてくれる」という安心感は園への信頼度を大きく高めます。こうした信頼は園児募集や職員採用にも影響していきます。
採用担当らいん君を活用した保育士採用の効率化
しかし、現実には十分な人員を確保することに苦労している園が少なくありません。そこで役立つのが、LINEを活用した採用支援ツール「採用担当らいん君」です。「採用担当らいん君」では、園オリジナルのLINE公式アカウントを作成することにより、LINE上で求職者と直接つながり、求人情報の発信、応募から面接調整までをチャットでスムーズに行うことができます。
また従来の求人媒体に比べて掲載できる情報量が多く、園の雰囲気や強みをアピールしやすいのも大きな特長です。採用活動と同時にブランディングも強化できるため、求職者から「この園で働きたい」と選ばれる可能性が大きく高まります。 人材不足は不適切保育を生む大きな要因のひとつです。だからこそ、費用対効果の良い採用戦略は、重要な投資と言えます。今すぐ「採用担当らいん君」を導入し、安定した人員体制と子どもたちに安心を届けられる環境づくりを始めましょう

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。