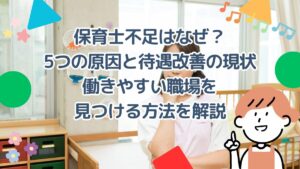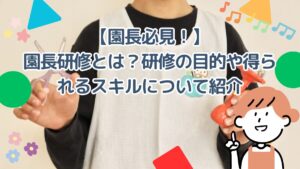ノンコンタクトタイムとは?導入メリットや利用可能な補助金について解説!
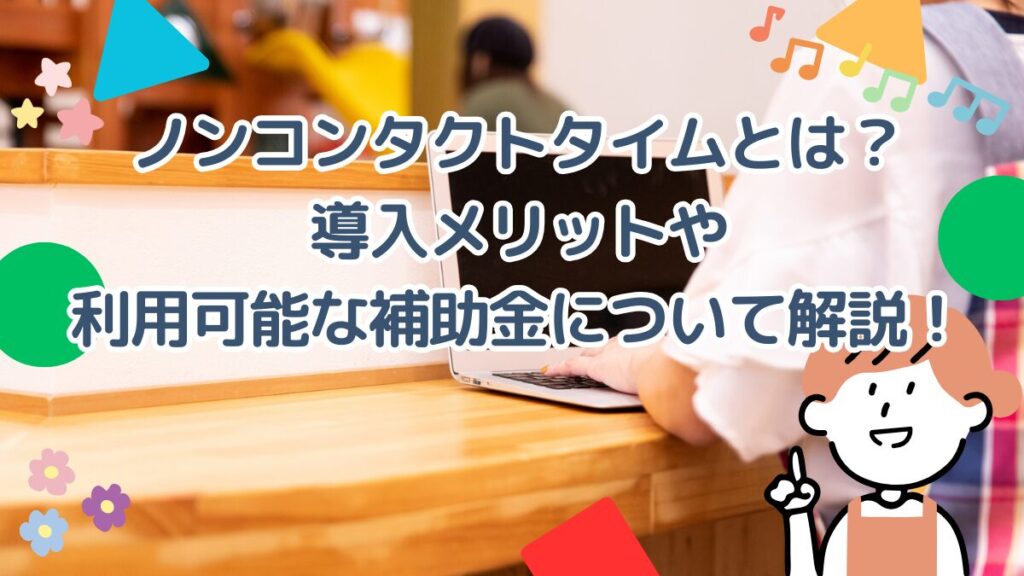
近年、保育業界では「保育の質」をどう高めるかが大きな課題となっています。
人材不足や業務過多に悩む保育現場では、働きやすい環境づくりが急務です。その中で注目されているのが「ノンコンタクトタイム」です。
本記事では、ノンコンタクトタイムを確保することで、業務効率化や保育の質向上にどのような効果があるのかを解説します。
目次
ノンコンタクトタイムとは?

ノンコンタクトタイムとは、保育士が子どもと直接かかわる保育業務(コンタクトタイム)以外の時間を、あえて確保する取り組みです。この時間を使い、計画や記録、職員同士の打ち合わせ、保護者対応、研修などを行います。
厚生労働省は令和元年度より「保育士等の業務負担軽減・処遇改善推進事業」を通じて、ノンコンタクトタイムの確保を後押ししています。
【参考:厚労省 保育士等キャリアアップ研修の手引き】
これまでの保育現場では、保育士が子どもを見ながら記録を書いたり、退勤後に計画を作成したりと、いわゆる「ながら業務」や「持ち帰り仕事」が常態化していました。その結果、長時間労働や精神的疲労の要因となり、離職につながるケースも少なくありません。
ノンコンタクトタイムは、こうした問題を改善する一つの手段として注目されています。
具体的には、以下のような時間にあてられます。
– 週案や月案などの指導計画作成
– 保育日誌や個別記録の作成
– 保護者への連絡準備や対応
– 職員間の情報共有や会議
– 外部研修や職員研修の参加
ノンコンタクトタイムの導入は、保育士の働き方を見直し、業務の質を高める大きなきっかけとなります。また、補助金や加算制度も活用できるため、制度を上手に取り入れることで無理なく導入が可能です。
次の章では、実際にノンコンタクトタイムを導入することで得られる具体的なメリットを見ていきましょう。
ノンコンタクトタイム導入のメリット
ノンコンタクトタイムの導入は、単なる「保育士の休憩時間」ではありません。保育の質や職員の働き方に直結する、重要な取り組みです。ここでは、導入によって得られる主なメリットを4つの観点から解説します。
保育士・職員同士で連携が取りやすい
ノンコンタクトタイムを設けることで、保育士同士が落ち着いて話し合う時間が生まれます。これにより、引き継ぎミスや情報伝達のズレを防ぎ、チーム全体の連携がスムーズになります。
たとえば、保育日誌をもとに1日の保育を振り返り、改善点を共有するだけでも、子どもへの対応力が格段に向上します。これは「職場の一体感」を高める心理学的効果(社会的証明)とも関連します。人は仲間が取り組んでいることを自分も行おうとする傾向があるため、定期的な連携機会があることで、園内に前向きな保育文化が根づきやすくなります。
保育環境の改善に取り組みやすい
ノンコンタクトタイムでは、保育室の環境を見直す時間も確保できます。たとえば、年齢別の玩具の入れ替えや安全対策の点検など、日々の業務では後回しになりがちな項目も丁寧に見直せます。
実際、東京都の保育所等におけるモデル実施報告(令和3年度)でも、ノンコンタクトタイムを設けた施設では「職員からの改善提案が増えた」という結果が報告されています【出典:東京都福祉保健局】。
このように、物的環境と人的環境の両面から、よりよい保育の実現につながるのがノンコンタクトタイムの利点です。
残業時間が減りやすい
業務時間内に記録や計画作成が完了すれば、持ち帰り業務やサービス残業の削減が期待できます。これは職員の働きやすさに直結する改善です。
心理学の「損失回避バイアス」によると、人は「得をする」より「損をしない」行動を重視する傾向があります。つまり、「ノンコンタクトタイムがないと残業が増える」という状況は、多くの職員にとって強いストレスです。
この負担を減らすことで、保育士の定着率向上にもつながります。現に、ICT導入とノンコンタクトタイムの併用により、年間の残業時間を半減できた園の事例も報告されています。
保護者への信頼向上
ノンコンタクトタイムで保育内容の振り返りや連絡帳の質が向上すれば、保護者とのコミュニケーションも丁寧になります。言葉の選び方や伝え方に時間をかけられることで、「信頼できる園」という印象が強まります。
これは「第一印象効果(初頭効果)」や「丁寧な説明が信頼を高める」という心理法則に基づくものです。たとえば、ある園では、連絡帳をアプリ化して、ノンコンタクトタイム中に内容を深めた結果、保護者からの感謝の声が増えたという報告もあります。
園と家庭がより良いパートナー関係を築くためには、保育士の“準備の時間”が欠かせません。
ノンコンタクトタイムの課題

ノンコンタクトタイムは、保育士の業務改善や働き方改革に有効な手段ですが、導入にはいくつかの課題があります。特に小規模施設や人員に余裕のない保育園では、制度として定着させるには工夫が必要です。ここでは、現場が直面しやすい代表的な課題を整理します。
1. 人員不足の中で時間確保が難しい
最も大きな課題は「時間をどうやって捻出するか」です。園児に対して必要な人数の保育士を配置した上で、誰かをノンコンタクトに回すには、シフト調整や補助職員の活用が不可欠です。
特に1〜2歳児を多く抱える園では、配置基準を満たすだけでもギリギリという状況が多く、ノンコンタクトタイムを確保するには新たな人材確保が求められます。結果的に「わかってはいるけど無理」という声が多く聞かれます。
このような状況では、まずは「短時間・少人数から試す」ことや、ICTを活用して効率化した分をノンコンタクトに回す方法が現実的です。
2. 職員間での不公平感が生じやすい
ノンコンタクトタイムを誰に割り当てるかによって、「あの人だけ楽をしている」「私はいつも現場にいる」という不満が出やすくなります。制度の趣旨や目的が職員全体に正しく理解されていないと、チームワークの悪化を招きかねません。
対策としては、ノンコンタクトタイムを全職員に順番で回す、または担当業務ごとに必要な時間を設定するなど、「平等感」が感じられる運用ルールをあらかじめ整備しておくことが重要です。
また、ノンコンタクト中の業務内容を可視化し、記録に残して共有することも、不公平感を減らす効果があります。
3. 園長や主任の意識と運用負担
制度を導入しても、園長や管理職が現場の多忙さに押されて「結局、時間を削って保育に入ってしまう」という状況もあります。
ノンコンタクトタイムは、単なる休憩ではなく「保育の質を高める専門的業務の時間」として園全体で位置づけることが不可欠です。
心理的バリアを越えるには、「時間を取ること=職員や園児の未来を守ること」という視点に立ち返る必要があります。
4. 補助金制度の複雑さ・申請の手間
ノンコンタクトタイムを制度的に導入するには、国や自治体の補助金制度の活用が重要ですが、内容が複雑で、情報収集や申請業務に時間を取られることも課題です。
特にICT関連や人材加配に関する補助は、年度ごとに内容が変わることも多く、最新情報を常に確認しなければなりません。
このような行政手続きの煩雑さが、現場のハードルを上げている現実も見逃せません。
ノンコンタクトタイムを導入するためのポイント
ノンコンタクトタイムの重要性は理解していても、実際に現場に落とし込むとなると「人も時間も足りない」と感じる園が多いのではないでしょうか。ここでは、限られたリソースの中でも導入・定着を進めるために意識すべき3つのポイントを紹介します。
人員配置を調整する
まず考えるべきは、「いつ、誰に、どれくらいの時間を確保するか」です。すべての職員に一律の時間を設けるのは難しくても、短時間・ローテーションでの運用なら現実的です。
たとえば、午前の短時間保育の間に1人を抜いて事務作業にあてる、早番・遅番を調整して日中のノンコンタクトタイムを確保するなど、柔軟なシフト設計が有効です。
また「一時的な補助人材の加配」や「フリーの保育士配置」も導入の鍵になります。2025年度の加算制度でも、保育士確保や配置改善のための支援が強化されており、それを活用することで無理のない体制づくりが可能です。
業務内容の見直し
ノンコンタクトタイムを確保するには、日々の業務そのものを効率化する視点も必要です。不要な会議、重複する記録、非効率な書類作業など、時間を奪っている原因を洗い出しましょう。
実際に、全国的に行われている「業務改善プロジェクト」の中でも、「記録の簡素化」「行事の見直し」などが導入にあたって有効であったという報告があります。
心理学でいう「スモールステップ法(行動変容を細かく分解)」にならい、小さな見直しの積み重ねから始めることが、定着の近道になります。
ICTシステムを活用する
ノンコンタクトタイムの確保とICTの導入は、切っても切れない関係にあります。記録作業や連絡業務をICTで効率化できれば、その分だけ「保育士の手を空ける」ことが可能になるからです。
たとえば、登降園管理や保護者連絡、日誌作成などをアプリやクラウドで一括管理することで、1日あたり15〜30分の時短につながったという施設もあります。
導入時は補助金制度(次章で詳述)も活用できますし、ツール選びで迷ったら「保育所等におけるICT化推進等事業」の活用要件に合致したツールを選ぶのがおすすめです。
導入後は、ICTの利用ルールや職員間の研修などを通じて、定着させていく仕組みづくりも忘れてはいけません。
ノンコンタクトタイムの補助金について
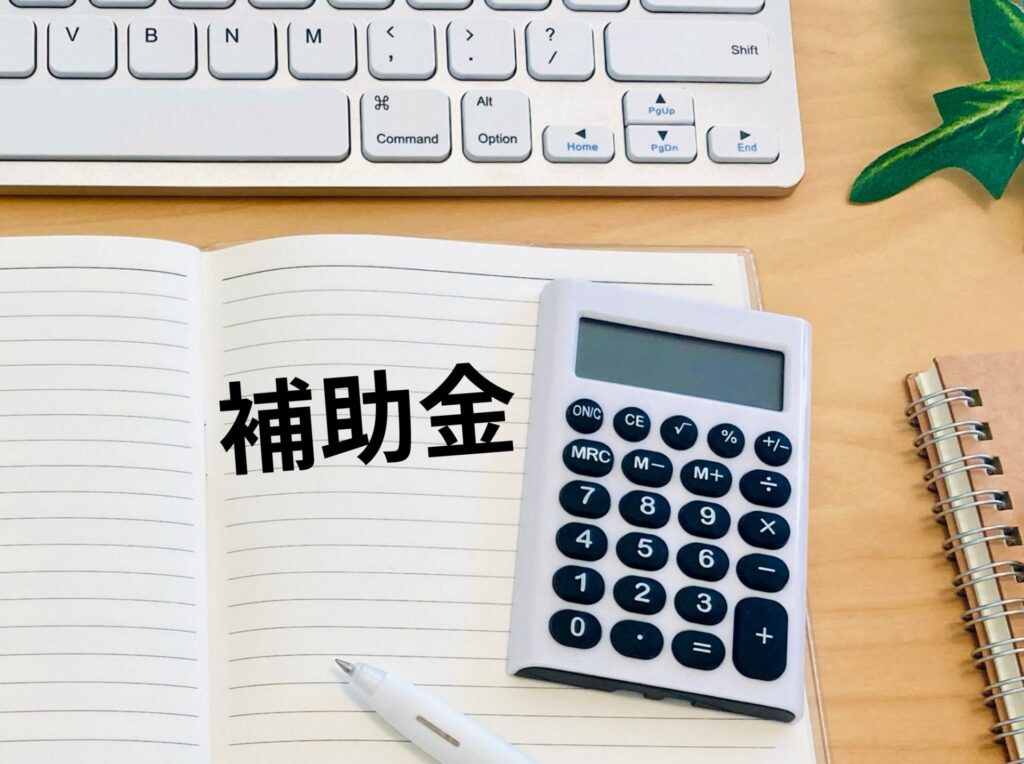
ノンコンタクトタイムの導入は、制度の活用次第でより現実的になります。特に、厚生労働省や自治体が実施している補助制度を活用することで、ICT導入や人員加配にかかる費用負担を軽減できます。
ここでは、代表的な補助金や事業を4つ紹介し、それぞれの概要と活用方法を解説します。
保育所等整備交付金
「保育所等整備交付金」は、保育施設の環境改善を支援する国の代表的な補助金制度です。この交付金は、施設の新設・改修のほか、ICT機器の導入にも活用できます。
たとえば、登降園管理システムや業務用タブレットの導入費用を、この交付金で一部または全額まかなった事例もあります。
自治体により対象設備や補助率が異なるため、事前に市区町村の担当窓口で確認することが重要です。
保育体制強化事業
この事業は、保育士の負担軽減や保育の質向上を目的として、非常勤職員の配置や支援スタッフの導入を支援する制度です。
ノンコンタクトタイムを確保するために、補助職員を一時的に配置する場合などに活用できます。特に小規模園では、常勤職員の代替が難しいため、非常勤加配による支援が有効です。
この事業を活用することで、ノンコンタクト時間を作りやすい運営体制が整います。
【参考:子ども家庭庁 令和7年度 保育関係予算概算要求の概要】
保育所等におけるICT化推進等事業
ICT活用を進める園に対して、機器購入費や導入支援費を補助する制度です。対象となる機器には、以下のようなものが含まれます。
– 登降園管理システム
– 保育記録アプリ
– 保護者連絡システム
– タブレット端末、Wi-Fi整備など
この事業の特徴は、導入支援事業者との連携が必須である点です。認定業者との契約・報告を通じて、計画的かつ効率的にICT化を進めることが求められます。
ICT導入によって記録作業の短縮が実現すれば、ノンコンタクトタイムの確保にも直結します。
成功事例の共有と活用
国や自治体の補助金は、「成果報告」として公開されることがあります。こうした成功事例を参考にすることで、導入のイメージが湧きやすくなります。
たとえば、横浜市の保育ICT導入モデル園の報告書では、業務時間の短縮や記録精度の向上が明記されており、「どの機器を使い、どう活用したか」が具体的に書かれています。
また、導入園同士での横のつながりを持ち、情報交換を行うことで、地域全体でノンコンタクトタイムの活用が広がる好循環を生むこともできます。
まとめ
ノンコンタクトタイムは、保育士の業務負担を軽減し、保育の質を高めるための有効な手段です。
しかし、実際の現場では「時間がない」「人が足りない」「制度がわからない」といった悩みが多く、導入に踏み出せない施設も少なくありません。
ここでは、導入にあたって押さえるべき2つの重要な観点をお伝えします。
ノンコンタクトタイムの導入には「人材確保」が必要
ノンコンタクトタイムを継続的に運用するためには、保育士の人数確保が前提です。
2025年度からは、国による保育士配置改善加算制度が拡充されており、人員加配を行う園に対して補助が出る仕組みも整ってきました。
しかしながら、現場では「求人を出しても応募がない」「若手が定着しない」といった採用難が続いています。人材不足の状態では、いくら制度が整っていてもノンコンタクトタイムの確保は難しいのが現実です。
だからこそ、採用戦略を見直し、長く働き続けられる環境づくりと職員の安定的確保が、今後ますます重要になります。
保育園の人材確保するなら「採用担当らいん君」
「ノンコンタクトタイムを取りたいが、人がいない」
この課題を解決する手段として、多くの保育園で導入されているのが、採用支援ツール「採用担当らいん君」です。
このツールは、LINEを活用して求職者とスムーズにやり取りができる採用チャットシステムで、応募対応や面接調整などを24時間自動化できます。若手求職者が慣れ親しんだLINEを使うことで、応募率が向上し、ミスマッチの防止にもつながります。
また、既存の採用フローを大きく変えずに導入できるため、園長や事務担当者の負担も最小限に抑えられます。
ノンコンタクトタイムを「制度」で終わらせず、「日常」に根づかせるには、人材確保の仕組みもセットで考える必要があります。採用から職場定着までを見据えた体制づくりが、保育の未来を支える第一歩です。
これまでの働き方を見直し、「保育の質」と「働きやすさ」を両立する第一歩として、ノンコンタクトタイムの導入を検討してみませんか?

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。