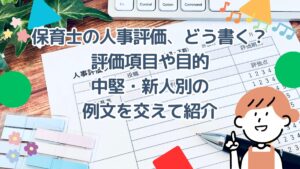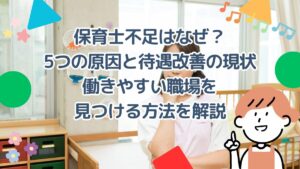保育士の働き方改革はどこから始める?課題解決のポイントと明日からできる取り組みを解説
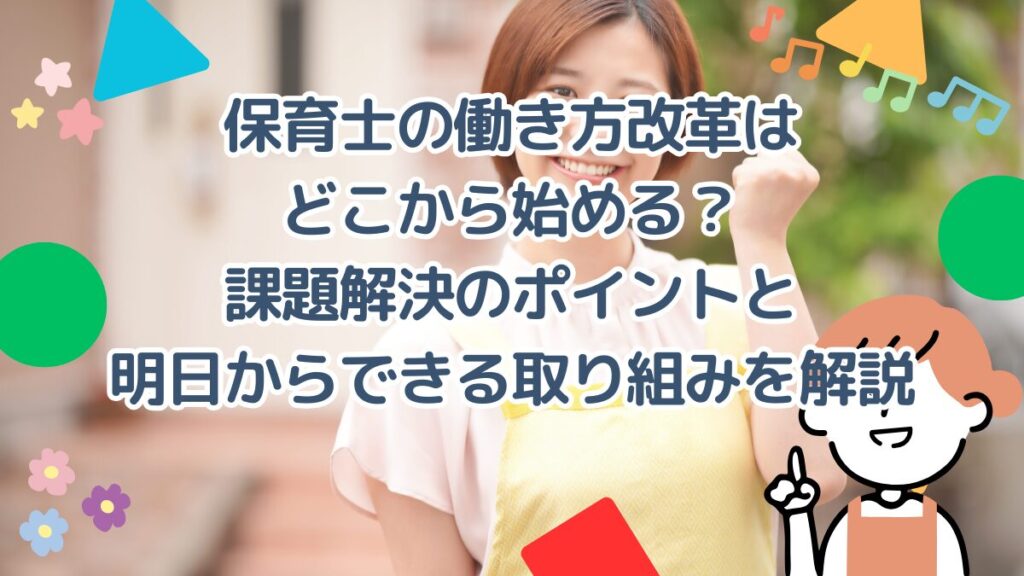
「残業や持ち帰り仕事が当たり前…」「人手不足で、心にも時間にも余裕がない」
多くの保育士さんが、このような厳しい状況で日々奮闘されているのではないでしょうか。国が「働き方改革」を推進する一方で、保育の現場では「何から手をつければ良いのか分からない」「うちの園では無理だ」といった声が聞こえてくるのも事実です。
しかし、諦める必要はありません。保育士一人ひとりがやりがいを持って働き続けられる環境は、必ず作れます。
この記事では、保育士の働き方改革が進まない根本的な理由を解き明かし、ICTの活用や業務の見直しといった明日からでも実践できる具体的な取り組みを、成功事例や活用できる補助金とあわせて網羅的に解説します。子どもたちと心から向き合える、より良い保育の未来のために。この記事が、あなたの園の働き方を変えるための、確かな一歩となれば幸いです。
目次
保育士の働き方改革とは?法律のポイントと必要性を解説

「残業続きでヘトヘト」「休みの日も仕事のことを考えてしまう」多くの保育士さんが、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。保育業界の労働環境を改善し、誰もがやりがいを持って働き続けられるようにするために「働き方改革」が不可欠です。働き方改革は、単に残業を減らすだけでなく、保育の質そのものを向上させるための重要な取り組みです。まずは、法律で定められたポイントと、なぜ保育現場で特に改革が求められているのかを理解することから始めましょう。
働き方改革関連法の3つの重要ポイント
2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」では、主に3つの大きな変更点があります。これらは保育園を運営する上で必ず守らなければならないルールです。
| ポイント | 内容 | 保育園での影響 |
| 時間外労働の上限規制 | 残業時間の上限が原則として月45時間・年360時間と法律で定められました。臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできません。 | 行事の準備などで常態化していた長時間の残業が見直され、業務時間内に仕事を終える工夫が求められます。 |
| 年次有給休暇の取得義務化 | 年10日以上の有給休暇が付与される職員に対し、年間5日は園側が時季を指定してでも取得させることが義務付けられました。 | 「周りに迷惑がかかるから」と休みを取りづらかった状況が改善され、計画的な休暇取得が促進されます。 |
| 同一労働同一賃金 | 同じ業務内容であれば、正規雇用の職員と非正規雇用の職員(パート、契約職員など)との間で、給与や福利厚生などの不合理な待遇差を設けることが禁止されました。 | パート保育士の役割や貢献に見合った待遇が必要となり、組織全体の公平性が高まります。 |
なぜ今、保育現場に働き方改革が必要なのか
保育の現場は、社会にとって不可欠な役割を担う一方で、長年厳しい労働環境が課題とされてきました。共働き世帯の増加により保育ニーズは高まり続けており、保育士の有効求人倍率は常に高い水準で推移しています。これは、保育士を求める保育園の数に対して、働きたいと考える保育士の数が追いついていない「人手不足」が深刻であることを示しています。
この人手不足の背景には、責任の重さに対して給与水準が低いことや、日々の保育に加え、指導案や日誌、保護者対応、行事準備といった多岐にわたる業務による負担の大きさがあります。結果として、心身の不調や将来への不安から離職を選ぶ保育士が後を絶ちません。
子どもたちの健やかな育ちを支える保育士が、安心して長く働き続けられる環境を整えること。それが、待機児童問題の解消や保育の質の向上につながるため、保育現場における働き方改革は急務とされているのです。
保育園の働き方改革が進まない3つの理由

国が働き方改革を推進しているにもかかわらず、「自分の園では何も変わらない」と感じている方は少なくないでしょう。保育園の働き方改革がなかなか進まないのには、業界特有の根深い理由が存在します。
子どもの安全を預かる責任と終わらない業務
保育士の仕事は、子どもたちの命と安全を預かるという非常に大きな責任を伴います。そのため、少しの気の緩みも許されず、常に緊張感を持って業務にあたる必要があります。日々の保育はもちろんのこと、指導計画の作成、保育日誌や連絡帳の記入、行事の企画・準備、壁面装飾の作成、研修への参加など、その業務は多岐にわたります。これらの業務は子どもたちが降園した後に行われることが多く、結果として長時間労働や持ち帰り仕事が常態化しやすくなっているのです。
深刻な人手不足と採用の難しさ
前述の通り、保育業界は慢性的な人手不足に悩まされています。職員一人ひとりの業務負担が大きいことに加え、離職率も低くありません。一人が退職すると、その穴を埋めるために残された職員の負担がさらに増え、新たな離職を招くという悪循環に陥りがちです。
また、新たな人材を採用しようにも、厳しい労働環境のイメージから応募者が集まりにくいという現実もあります。「人が足りないから休めない」「新しい取り組みを始める余裕がない」といった状況が、改革の足かせとなっています。
根強く残る旧来の価値観とアナログな業務体制
保育現場によっては、「子どもたちのために、保育士が自己犠牲を払うのは当たり前」「手書きの書類こそ心がこもっている」といった旧来の価値観が根強く残っている場合があります。このような環境では、業務効率化の提案が「手抜き」や「愛情が足りない」と捉えられかねず、新しい取り組みへの心理的な抵抗が大きくなります。また、連絡帳や指導案、職員間の情報共有など、多くの業務がいまだに手書きや口頭で行われている園も多く、アナログな業務体制が非効率を生み出す大きな原因となっています。
明日からできる!保育士の働き方改革 具体的な取り組み

「うちの園では改革なんて無理…」と諦める必要はありません。大規模な設備投資や人員増強がすぐにできなくても、工夫次第で始められることはたくさんあります。ここでは、働きやすい職場づくりのための具体的な取り組みを紹介します。
ICTシステムで事務作業を徹底的に効率化する
働き方改革を進める上で最も効果的な手段の一つが、ICT(情報通信技術)システムの導入です。パソコンやタブレットを活用することで、これまで手作業で行っていた多くの事務作業を自動化・効率化できます。
| ICTで効率化できる業務の例 | 具体的なメリット |
| 登降園管理 | ICカードやタブレットで打刻するだけで、登降園時間を自動で記録。延長保育料の計算も自動化できます。 |
| 保護者連絡 | 専用アプリを通じて、欠席連絡や園からのお知らせを一斉配信。連絡帳も電子化すれば、すきま時間に記入・確認ができます。 |
| 指導案・日誌作成 | 過去のデータを参考にしたり、テンプレートを活用したりすることで、書類作成の時間を大幅に短縮できます。 |
| 職員のシフト・勤怠管理 | 職員の希望や配置基準を考慮したシフトを自動で作成。出退勤記録もデータで管理し、労働時間を正確に把握できます。 |
ICTシステムの導入には初期費用がかかりますが、国や自治体の補助金を活用できる場合も多くあります。 長い目で見れば、保育士の業務負担軽減、ひいては保育の質の向上に大きく貢献する投資と言えるでしょう。
業務の棚卸しで「やらなくていい仕事」を見つける
新しいシステムを導入する前に、まずは現在の業務内容を全て洗い出し、「本当に必要な仕事か」を見直すことが重要です。長年の慣習で続けているだけで、実はやめても支障がない業務が見つかるかもしれません。
例えば、「毎日手書きで作成している報告書は、週次報告にできないか」「定例会議の時間を短縮し、情報共有はチャットツールで済ませられないか」など、職員全員で業務の棚卸しを行うことで、無駄をなくし、効率化の意識を高めることができます。
保育補助者や外部サービスを積極的に活用する
保育士が本来の専門業務である「子どもの保育」に集中できる環境を作ることも大切です。清掃、洗濯、給食の準備、園庭の管理といった保育周辺業務は、専門の外部サービスに委託したり、保育士資格を必要としない「保育補助者」を配置したりすることで、保育士の負担を大きく軽減できます。これにより、保育士は子どもと向き合う時間をより多く確保できるようになり、保育の質の向上につながります。
多様な働き方を認める職場風土を醸成する
職員一人ひとりのライフステージに合わせた、多様で柔軟な働き方を認めることも、人材の定着には不可欠です。例えば、子育て中の職員のための短時間勤務制度や、週休3日制の導入、個人の希望に応じた固定シフトなど、様々な選択肢が考えられます。
大切なのは、どのような雇用形態や働き方であっても、全ての職員が尊重され、チームの一員として力を発揮できる職場風土を作ることです。多様な人材が活躍できる職場は、組織全体の活性化にもつながります。
働き方改革で活用できる補助金・支援制度

働き方改革を進めるにあたり、資金面での課題を感じる園も多いでしょう。国や自治体は、保育現場の環境改善を後押しするために、様々な補助金や支援制度を用意しています。これらを活用しない手はありません。
ICT化の導入を支援する補助金
保育園のICT化を支援する補助金制度があります。これは、保育士の業務負担を軽減し、事務作業を効率化するためのパソコンやソフトウェア、タブレット端末などの導入費用の一部を補助するものです。補助額や対象となる経費は自治体によって異なりますが、導入時の大きな助けとなります。まずは、ご自身の園が所在する自治体の情報を確認してみましょう。
引用文献:処遇改善等加算IIの仕組み
職員の待遇改善やキャリアアップを支える制度
保育士の給与アップやキャリアアップを目的とした「処遇改善等加算」という制度があります。 これは、園が職員のキャリアアップのための研修制度を整えたり、役職を設けたりすることで、国から給付金が支給され、職員の給与に上乗せされる仕組みです。
処遇改善等加算IIでは、経験年数に応じて「職務分野別リーダー」「専門リーダー」「副主任保育士」といった新たな役職が設けられました。これにより、若手や中堅の保育士も具体的なキャリアプランを描きやすくなり、仕事へのモチベーション向上や離職防止につながることが期待されています。
引用文献:令和6年度保育関係予算概算要求の概要
まとめ:働き方改革は保育の未来をつくる第一歩

保育士の働き方改革は、単に労働時間を短縮するための取り組みではありません。それは、保育士一人ひとりが心身ともに健康で、専門職としての誇りを持ち、やりがいを感じながら働き続けられる環境を整えることです。
保育士が笑顔で働ける職場は、子どもたちの笑顔と健やかな成長に直結します。ICTの導入、業務の見直し、多様な働き方の推進など、できることは数多くあります。
また、採用活動や職員管理の効率化も働きやすい環境づくりには欠かせません。LINEを活用した保育業界向け採用管理ツール「採用担当らいん君」では、採用・連絡・管理を一元化し、現場の負担を大きく軽減できます。
この記事で紹介した取り組みや事例を参考に、ぜひ自園に合った方法で、働き方改革の第一歩を踏み出してください。その一歩が、保育の明るい未来へとつながっていくはずです。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。