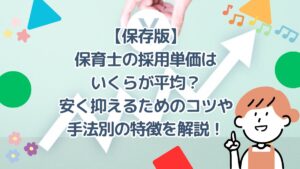保育園の経営が難しい時の改善策は?閉園を回避するための秘訣

保育園の経営は年々難しくなっていますが、適切な改善策を講じることで閉園のリスクを減らすことが可能です。
本記事では、経営が厳しいときに取るべき具体的な対策をわかりやすく解説します。
目次
保育施設経営者が抱える課題とその原因
近年、保育園の経営が厳しさを増しています。その背景には少子化の進行や労働環境の変化、保護者ニーズの多様化など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
この記事では、保育施設が直面している主な課題とその原因について解説します。
少子化で園児確保が困難に|地方保育園が直面する厳しい現実
地域の人口減少や少子化による出生数の減少を背景に、地方を中心に定員割れの園が増加し、園児の確保が難しくなるとともに、収入の減少にもつながっています。
厚生労働省によると全国的な出生数は2000年代以降減少の一途をたどっており、特に中山間地域では保育需要自体が縮小しています。
深刻な保育士不足と労働環境の見直しの必要性
慢性的な保育士不足は、多くの園にとって深刻な問題です。厚生労働省によると、私立保育園の離職率は10.7%と高水準で、採用コストや業務の引き継ぎによる負担が経営を圧迫しています。
また、ICT導入や業務分担の見直しが進まない園では、現場の疲弊が続き、さらなる離職を招く悪循環に陥るリスクもあります。
行政とのやり取りや規制の変化への対応における負担増
制度改正や監査対応など、行政とのやり取りも保育園経営の大きな負担です。
例えば2025年度から導入される1歳児配置改善加算では、ICT活用や職員の平均経験年数要件などの条件を満たす必要があり、準備や申請業務に手間がかかっています。都度変化する制度変更に柔軟に対応する力が、今後の経営継続には不可欠です。
成功している保育園の経営戦略
経営が厳しい中でも安定運営を実現している保育園には、共通する戦略があります。
この章では、実際に成果を上げている園が取り入れている経営戦略を紹介します。費用管理やサービス設計、人材育成など、多方面にわたる工夫が見られます。
安定運営の鍵は、支出構造の“見える化”
保育園の主な支出は人件費・給食費・施設維持費が中心です。特に人件費は全体の60〜70%を占め、園の運営バランスに直結します。
収入源としては、自治体からの運営費交付金が中心ですが、加算措置や独自収入(延長保育・アルバム・園グッズ販売など)の有無で差が生まれます。経営が安定している園ほど、費用構造を可視化し、無駄のない支出管理がされています。
地域に根ざした特色ある保育内容でブランド力UP
経営が安定している園の多くは、地域の子育て世帯に響く独自の保育方針を打ち出しています。
例えば「自然体験保育」「異年齢交流」「地域食材を使った食育」など、保護者に選ばれる魅力を高めています。保育の質はもちろん、共感を得られる理念を外部に発信する姿勢が、安定した定員確保につながっています。
SNSやホームページを活用したコミュニティ形成
園のSNS活用やホームページによる情報発信も経営戦略の一部となっています。園
の雰囲気や保育理念を伝えることで、認知度向上や信頼獲得につながります。また、地域イベントへの参加や子育て支援講座の開催など、コミュニティとつながる活動も、園児募集に効果を発揮しています。地域とのつながりを強めることで、園の存在価値が高まります。具体的には、地域イベントへの参加、保育体験の提供、高齢者施設との交流などが挙げられます。地域との交流を持つことで、口コミでの評価が広がり、入園希望者の増加にもつながります。
弊社の園児募集らいん君では、LINEから子育て支援イベントのお申込みを受け付けることができます。誰もが使っているLINEを活用することでお申込み率が上がったというお声もいただいています。
効率的な経営管理とICT導入で保育士の負担を軽減
ICT(情報通信技術)を導入し、業務効率を上げる園が増えています。
登降園管理、日誌や連絡帳の電子化によって職員の負担を軽減し、その分保育の質を高めることができます。特に「1歳児配置改善加算」を受けるためにはICT活用が条件となるため、制度活用の面でもメリットがあります。
職員の研修と働きやすい環境づくり
人材の定着は経営の安定に直結します。
成功している園では、段階的な研修やメンター制度を取り入れ、保育士の成長と定着を促しています。また、有休取得率の向上や時短勤務の推進など、柔軟な働き方の整備にも取り組んでいます。労働環境の改善が、職員のモチベーション向上と離職防止につながっています。
柔軟な料金体系と助成金支援の活用
保護者の経済状況に合わせた料金設計や、助成制度の活用支援も差別化の一つです。
認可外施設であっても、自治体の助成制度を案内することで、保護者の負担軽減と満足度向上が図れます。経営視点からも、収入を安定させる工夫として重要な要素です。
保育士の定着と育成戦略
安定した保育園運営のためには、職員の定着が不可欠です。
職員が定着している園では、面談やメンター制度を取り入れ、早期離職の防止に取り組んでいます。また、「研修制度」や「キャリアパスの明示」も保育士のモチベーション維持に有効です。給与面だけでなく、働きがいのある環境づくりが重要です。
保育施設の環境改善と設備投資
施設の老朽化や安全対策の不備は、経営リスクにも直結します。
近年では「遊具の安全基準」「換気設備」「ICT設備」などの改善が求められています。自治体の補助金や助成制度を活用しながら、段階的な改修や投資を計画的に行うことがポイントです。
保育園の経営計画と長期ビジョンの立て方
経営の安定化を図るには、短期的な対策だけでなく、中長期的な視点も大切です。
ここでは、保育園が描くべき事業計画や成長ビジョンについて解説します。
事業計画作成のステップとポイント
まずは「現状分析」「課題抽出」「目標設定」「アクションプランの策定」の流れで計画を立てます。
具体的には、園児数や人員配置、財務状況を数値で把握し、将来像とその達成手段を明文化することが重要です。自治体への報告や補助金申請にも使えるため、計画書の整備は欠かせません。
STEP:1「現状分析」マーケット調査と顧客分析
地域の人口動態や競合園の状況を把握することで、より精度の高い戦略立案が可能になります。
特に、新築住宅の開発状況、転入世帯の増減、保護者ニーズの変化などは重要な指標です。アンケート調査や地域の子育て支援課との連携も、有益な情報源となります。
STEP:2「課題抽出」データと現場の声から経営の“核心”を見極める
現状分析で得たデータや地域情報をもとに、保育園の運営における課題を多面的に掘り下げます。
単なる数値の把握にとどまらず、「なぜ定員が埋まらないのか」「なぜ職員の定着率が低いのか」といった“背景にある要因”を現場の声やヒアリングから読み取ることが大切です。
また、財務・人材・保育の質といった複数の視点から課題を分類・整理することで、取り組むべき優先順位や、短期・中長期で解決すべき課題が明確になります。ここでの洞察が、次のアクションプラン策定の精度を大きく左右します。
STEP:3「アクションプランの策定」保育園の成長ビジョンと投資計画
将来的な拡張や新規事業の構想を持つことは、職員や保護者の期待にもつながります。
例えば、分園の開設、障害児保育の強化、企業主導型施設との連携などが挙げられます。こうしたビジョンに基づき、設備投資や人材育成に計画的に資源を配分することが、持続可能な経営の鍵となります。
経営改善に向けた行動計画の進め方
いくら長期ビジョンを描いても、実行に移すための手順が曖昧では計画倒れに終わってしまいます。
ここでは、経営者が経営計画を具体的な行動に落とし込むためのステップをご紹介します。
現状把握と課題整理の手法
まずは、園の経営状態を正しく把握することが出発点です。
職員の協力を仰ぐ際にも、目に見える数字で説得することが大事になります。財務諸表や園児数推移、職員の勤務状況、保護者満足度など、あらゆる指標を”見える化”をしましょう。SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)を使って整理すると、課題の優先順位が明確になり、行動に起こしやすくなります。
職員の意識改革とチームビルディング
職員全員が経営改善に当事者意識を持つことが重要です。
理念の共有やミーティングでの発言機会を増やすなど、現場の声を尊重したチーム運営を心がけましょう。また、保育以外の業務にも関心を持てるよう研修の機会をつくることが、経営意識の形成につながります。
外部コンサルタント活用のメリット
第三者の視点を取り入れることで、園内では見えづらい課題が明らかになります。
たとえば、経営診断や人材マネジメントの専門家によるアドバイスは、計画策定の大きな助けになります。特に財務面やICT導入、助成金申請など専門知識が必要な分野では、外部支援を活用するのが効果的です。
まとめ|保育園経営に悩んだら、専門家のサポートで再出発を
少子化や保育士不足、制度変更による業務負担など、保育園の経営は年々難しさを増しています。
しかし、経営課題を“見える化”し、地域に合った園の魅力づくりとICTによる効率化、そして人材の育成や定着を意識的に進めていくことで、閉園のリスクを回避することは十分に可能です。
「どこから手をつければいいかわからない」「人手も時間も足りない」とお悩みの園長先生には、弊社の採用・園児集客支援サービスがおすすめです。
例えば…
- 「園児募集らいん君」なら、LINEで地域イベントの申し込み受付や情報発信ができ、認知度と信頼を高めながら効率的な園児募集が可能になります。
- 「採用担当らいん君」を使えば、保育士採用をLINE経由で自動化・省力化し、採用難の悩みを軽減できます。
経営の行き詰まりを感じたそのときこそが、園の成長を加速させるチャンスです。保育業界に特化した採用のプロである私たちチポーレが、園の未来づくりを全力で支援します。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。
参考サイト:厚生労働省「保育士の現状と主な取組」
参考サイト:宮崎県公式サイト「第2章中山間地域の現状と課題等」
参考サイト:厚生労働省「令和2年版厚生労働白書」
参考サイト:こども家庭庁「令和7年度保育関係予算案関連資料」