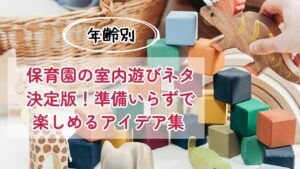保育園のヒヤリハット事例集|報告書の書き方と事故防止策を解説

保育園では、子どもたちの笑顔を守るために、日々の安全管理が最も重要です。しかし、どれだけ注意していても「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりする瞬間は訪れるものです。これらのヒヤリハットは、重大な事故を防ぐための貴重なサインです。この記事では、保育現場で実際に起こりがちなヒヤリハットの具体例から、分かりやすい報告書の書き方、そして未来の事故を防ぐための対策までを詳しく解説します。
目次
保育園におけるヒヤリハットとは?重大な事故を防ぐ第一歩

保育現場で使われる「ヒヤリハット」という言葉は、単なる危なかった出来事以上の重要な意味を持っています。子どもたちの安全を守る上で、この概念を正しく理解し、活用することが不可欠です。
「ヒヤリ」「ハッ」とした経験が事故を防ぐ
ヒヤリハットとは、結果的に事故には至らなかったものの、一歩間違えれば重大な事故や怪我につながる可能性があった出来事を指します。 例えば、「子どもが遊具から落ちそうになったが、寸前で体勢を立て直した」「床に落ちていた小さなブロックを口に入れかけたが、保育士が気づいて取り上げた」といったケースがこれにあたります。
これらの出来事は、幸いにも怪我などがなかったため、つい見過ごしてしまいがちです。しかし、それは「運が良かっただけ」であり、背景には事故につながる危険性が潜んでいます。この「ヒヤリ」「ハッ」とした経験を放置せず、なぜそれが起きたのかを考え、対策を講じることが、事故を未然に防ぐための最も効果的な手段となります。
1件の重大事故の裏に潜むハインリッヒの法則
ヒヤリハットの重要性を説明する際によく用いられるのが、「ハインリッヒの法則」です。これは、1件の重大な労働災害の背後には、29件の軽微な災害と、300件の傷害に至らない災害(ヒヤリハット)が存在するという統計的な法則です。
これを保育園の現場に置き換えると、1件の大きな怪我や事故の裏には、29件の軽い擦り傷や打撲などの事故があり、さらにその背景には300件のヒヤリハットが隠れていると考えられます。つまり、日常に潜む数多くのヒヤリハットの芽を一つひとつ摘み取っていくことが、結果として重大な事故を防ぐことに直結するのです。日々の小さな気づきを決して軽視せず、記録し、共有することが、園全体の安全性を高めるための鍵となります。
【内部リンク】【保存版】園児が怪我をした際の保育園の対応方法を解説!保護者説明の実践ガイド – 株式会社チポーレ – お役立ち情報
【場面別】保育園で起こりやすいヒヤリハットの具体例
保育園の活動は多岐にわたるため、危険が潜む場面も様々です。ここでは、具体的な場面ごとに起こりやすいヒヤリハットの事例を紹介します。自園の環境と照らし合わせながら、潜んでいるリスクを再確認してみましょう。
| 場面 | ヒヤリハット事例 | 考えられる対策 |
| 室内活動 | 走っていて友達と衝突しそうになる。棚の角に頭をぶつけそうになる。 | 室内でのルールを子どもたちと確認する。家具の角にクッション材を設置する。 |
| 園庭 | 遊具(ブランコ、滑り台)から転落しそうになる。 | 遊具の正しい使い方を指導し、定期的な安全点検を行う。保育士の監視体制を明確にする。 |
| 食事・おやつ | アレルギーのある子に誤って提供しそうになる。ミニトマトを丸ごと口に入れ喉に詰まらせそうになる。 | アレルギー情報は職員全員で共有し、配膳時はダブルチェックを徹底する。食材は年齢に応じて適切な大きさにカットする。 |
| 午睡 | うつぶせ寝になってしまい、窒息の危険があった。 | 定期的な午睡チェック(ブレスチェック)を実施し、記録する。安全な睡眠環境を整える。 |
| 園外活動 | 散歩中に子どもが列から離れ、道路に飛び出しそうになる。 | 出発前に人数確認を徹底し、散歩中のルールを再確認する。保育士の役割分担と配置を工夫する。 |
室内活動でのヒヤリハット(転倒・衝突・誤飲)
室内は安全と思われがちですが、多くのヒヤリハットが潜んでいます。子どもたちが走って友達や棚にぶつかりそうになる「衝突」、床のおもちゃにつまずく「転倒」は日常的に見られます。 また、特に低年齢児のクラスでは、床に落ちていた小さなものを口に入れてしまう「誤飲」の危険性が常に伴います。 これらの対策として、活動前に室内の環境整備(整理整頓、危険物の確認)を徹底することが重要です。
園庭でのヒヤリハット(遊具からの落下・飛び出し)
園庭では、活動がダイナミックになる分、危険性も増します。滑り台の上でふざけて転落しそうになる、ブランコの近くを横切ってぶつかりそうになるなど、遊具に関するヒヤリハットは後を絶ちません。 また、園庭の門扉の管理が不十分な場合、子どもが興味本位で外に出てしまうケースも報告されています。 遊具の安全点検を定期的に行い、子どもたちと繰り返し使い方を確認し合うと共に、門扉の施錠管理を徹底する必要があります。
食事・おやつの時間でのヒヤリハット(アレルギー・喉詰め)
食事の時間は、子どもの命に直結するヒヤリハットが起こりやすい場面です。アレルギーを持つ子どもの給食を取り違えそうになる、除去食の情報を職員間で共有できていなかった、といった事例は絶対に防がなければなりません。 また、ミニトマトやブドウ、パンなどによる窒息のリスクも常に意識する必要があります。アレルギー情報は複数の職員で確認し、食材は子どもの発達に合わせて適切な大きさや硬さに調理することが求められます。
午睡(お昼寝)中のヒヤリハット(うつぶせ寝・体調不良)
午睡中は、SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクもあり、特に注意が必要な時間帯です。 保育士が少し目を離した隙に子どもがうつぶせ寝になっていたり、寝具が顔にかかって呼吸を妨げそうになったりする事例が報告されています。 定期的な午睡チェックを確実に実施し、一人ひとりの子どもの顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察することが不可欠です。
園外活動(散歩)でのヒヤリハット(交通、迷子)
園外での活動は、予期せぬ出来事が起こりやすい環境です。散歩中に子どもが急に道路に飛び出しそうになる、公園で他の園の集団に紛れ込んでしまい見失いそうになる、といったヒヤリハットが考えられます。 園外活動の前には、ルートの安全確認、当日の参加人数の確認、職員の役割分担などを綿密に行い、子どもたちにも交通ルールや約束事を分かりやすく伝えることが重要です。
水遊び・プール活動でのヒヤリハット
夏場の水遊びやプールは、子どもたちが大好きな活動ですが、重大な事故につながる危険性も高い活動です。プールサイドで走って転倒する、友達とふざけて水を大量に飲んでしまう、少し目を離した隙に溺れそうになるなど、一瞬の油断が命に関わります。 監視体制を通常時よりも強化し、子どもの体調管理を徹底するとともに、水深や活動時間にも配慮することが求められます。
誰でも書ける!ヒヤリハット報告書の書き方と例文

ヒヤリハットを経験した際に重要なのが、その内容を記録し、共有することです。そのためのツールが「ヒヤリハット報告書」です。ここでは、報告書の目的から具体的な書き方、例文までを解説します。
なぜ報告書を書く必要があるのか?その目的を再確認
ヒヤリハット報告書は、単に「危なかった出来事を記録する」だけのものではありません。その最大の目的は、「事故の再発防止」です。報告書によってヒヤリハットの事例を園全体で共有し、原因を分析することで、具体的な対策を立てることができます。 また、記録として残すことで、どのような危険が園内に潜んでいるのかを客観的に把握し、保育環境の改善や職員の安全意識の向上につなげることができます。報告書は、誰かを責めるためのものではなく、未来の子どもたちを守るための大切な資産なのです。
報告書に必ず含めるべき5W1Hの項目
分かりやすく、事実が正確に伝わる報告書を作成するためには、「5W1H」のフレームワークを使うのが効果的です。誰が読んでも状況を客観的に理解できるよう、以下の項目を盛り込みましょう。
- When(いつ): 発生した日時(例: 〇月〇日 午前10時15分頃)
- Where(どこで): 発生した場所(例: 〇〇組保育室 ブロックコーナー)
- Who(誰が): 関係した子どもや職員(例: A子ちゃん 3歳児)
- What(何を): 何をしていたか(例: ブロックで遊んでいた)
- Why(なぜ): なぜヒヤリハットが起きたか(原因の推測)
- How(どうした): どのようにヒヤリハットが発生し、どう対応したか
これらの項目に沿って記述することで、個人の主観や感情を排し、事実に基づいた客観的な記録を残すことができます。
【そのまま使える】状況が伝わるヒヤリハット報告書の例文
ここでは、具体的な事例に基づいたヒヤリハット報告書の例文を紹介します。
ヒヤリハット報告書 記入例
| 項目 | 記入内容 |
| 報告日 | 2025年 7月 23日 |
| 報告者 | 保育 太郎 |
| 発生日時 | 2025年 7月 22日(火) 14時30分頃 |
| 発生場所 | 園庭 滑り台付近 |
| 対象児 | B雄くん(4歳児) |
| 発生状況(5W1H) | 園庭での自由遊び中、B雄くんが滑り台の頂上からジャンプしようとした。近くにいた保育士がすぐに声をかけ、ジャンプする前に制止したため、怪我はなかった。 |
| 原因の分析 | ・前日のテレビ番組でヒーローがジャンプするシーンを見ており、その真似をしようとした可能性がある。 ・他の子どもたちも興奮状態で、周囲の雰囲気に影響されたことも考えられる。 |
| 対応 | ・B雄くんに駆け寄り、ジャンプは危険であることを伝えた。 ・他の子どもたちも集め、改めて遊具の安全な使い方について説明した。 |
| 改善策・今後の対策 | ・遊具で遊ぶ前には、毎回安全な使い方について子どもたちと確認する時間を設ける。 ・職員会議で本件を共有し、園庭での監視体制について見直しを行う。 |
なぜヒヤリハットは起こるのか?主な原因を分析する

ヒヤリハットの再発を防ぐためには、その背景にある原因を理解することが重要です。ヒヤリハットは様々な要因が複雑に絡み合って発生しますが、主な原因として以下の3つが挙げられます。
慣れや思い込みによる確認不足
「いつもこうだから大丈夫」「この子はもう大きいから分かっているはず」といった、日々の業務の中での慣れや思い込みは、ヒヤリハットの大きな原因となります。 例えば、毎日通る散歩道だからと油断して安全確認を怠る、ベテラン保育士が自分の経験を過信してマニュアル通りの手順を省略してしまう、といったケースです。常に初心を忘れず、一つひとつの業務を確実に確認する姿勢が求められます。
職員間のコミュニケーション不足
保育はチームプレーです。職員間の情報共有が不足していると、危険な状況を見逃す原因となります。「Aちゃんが今日は少し体調が悪そうだ」という情報が共有されていなければ、午睡中の細やかな観察がおろそかになるかもしれません。「門の鍵が少し壊れている」という報告がなされていなければ、修理が遅れ、子どもの園外への飛び出しにつながる危険性があります。 職員会議や日々のミーティング、連絡ノートなどを活用し、些細なことでも報告・連絡・相談(ほうれんそう)を徹底する職場環境が不可欠です。
危険を予測する力の欠如
子どもの行動は、大人の予測を超えることが多々あります。「まさかこんなことはしないだろう」という大人の想定を、子どもは簡単に乗り越えていきます。例えば、部屋の隅にある小さな棚に登ろうとする、ブラインドの紐で遊んで首に巻きつけてしまうなど、予期せぬ行動からヒヤリハットは発生します。 様々なヒヤリハット事例を学ぶことで、「この環境では、子どもはこう動くかもしれない」と危険を予測する能力(危険予知能力)を高め、先回りして対策を講じることが重要です。
ヒヤリハットを未来の安全につなげるための対策

ヒヤリハットは、報告して終わりではありません。その情報をいかにして未来の安全につなげるかが最も重要です。個人レベルでの対策と、園全体での対策の両方からアプローチすることで、より安全な保育環境を構築できます。
保育士一人ひとりが実践できる事故防止策
まず、保育士一人ひとりが自身の行動を振り返り、安全意識を高めることが基本です。具体的には、子どもの目線に合わせて保育環境を見直し、「ここに危険はないか?」と常に自問自答する習慣をつけることが大切です。また、活動の節目節目で子どもの人数を声に出して確認する、少しでも不安に思ったら他の職員に相談するなど、基本的な行動を徹底することが事故防止の第一歩となります。
園全体で取り組むべき情報共有と再発防止の仕組み
個人の努力だけでは限界があります。ヒヤリハット報告書を基に、園全体で対策に取り組む仕組みを作ることが不可欠です。こども家庭庁の資料でも、ヒヤリハット事例の収集と共有の重要性が示されています。 定期的に職員会議で報告書を議題にあげ、特定の場面や時期にどのようなヒヤリハットが多いのか傾向を分析します。そして、その原因を探り、具体的な再発防止策を園の共通ルールとしてマニュアル化していくことが有効です。
| 対策のレベル | 具体的な取り組み内容 |
| 個人レベル | ・子どもの目線で危険箇所をチェックする ・活動の節目で人数確認を徹底する ・不安な点はすぐに同僚や上司に相談する |
| 園全体レベル | ・ヒヤリハット報告書を職員会議で定期的に共有する・事例を分析し、園の安全マニュアルを更新する ・危険箇所マップを作成し、職員全員で共有する |
報告書を活用して保育の質を高める方法
蓄積されたヒヤリハット報告書は、園の安全性を高めるだけでなく、保育の質そのものを向上させるための貴重なデータとなります。例えば、「〇〇の場所で転倒が多い」というデータがあれば、その場所の環境設定を見直すきっかけになります。「〇歳のクラスで誤飲のヒヤリハットが多い」のであれば、その年齢の発達段階に合ったおもちゃ選びや指導方法を再検討することにつながります。このように、ヒヤリハット報告書を分析・活用することは、より安全で、子どもたちの発達に適した保育環境を創造することに直結するのです。
まとめ
保育園におけるヒヤリハットは、決して軽視してはならない重大な事故への警告です。この記事で紹介した事例や報告書の書き方を参考に、日々の保育に潜む危険の芽を見つけ出し、一つひとつ丁寧に取り除いていくことが重要です。ヒヤリハットを職員全員で共有し、園全体の課題として捉えることで、子どもたちが毎日を笑顔で、そして安全に過ごせる保育環境を実現しましょう。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。