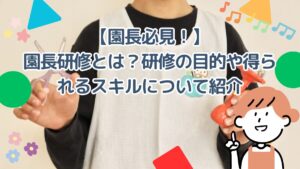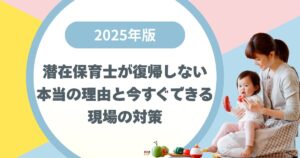【保存版】園児が怪我をした際の保育園の対応方法を解説!保護者説明の実践ガイド
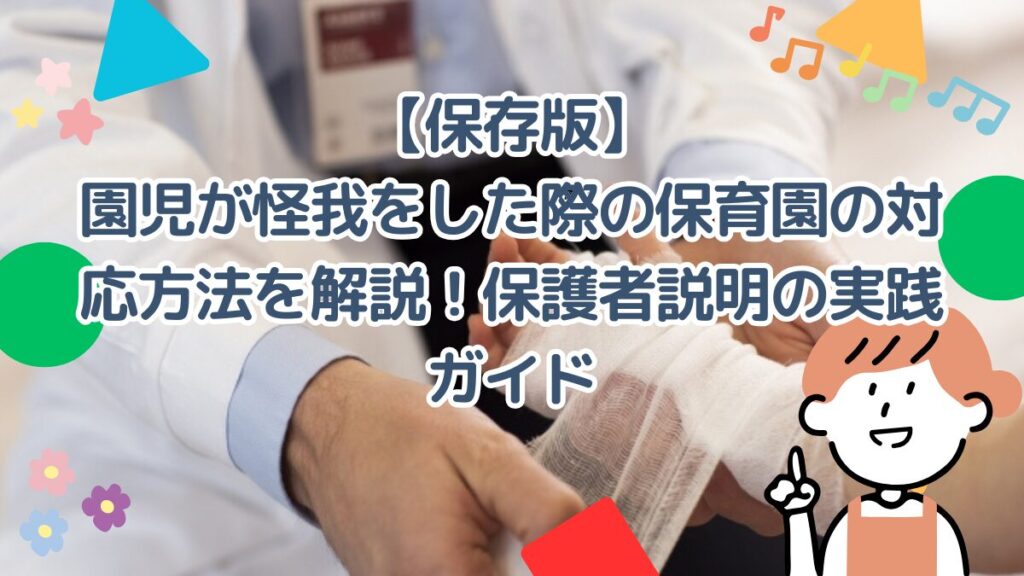
保育園では、どんなに安全に配慮していても、子ども同士の接触や遊具での転倒などによる怪我(けが)は避けられません。
大切なのは、怪我が起きた後にどう対応するかです。
園児のケアだけでなく、保護者への説明までが一つの「対応フロー」です。
本記事では、保育園で実際に怪我が発生した際の対応手順や、保護者対応のコツ、さらには
未然に防ぐための工夫までを詳しく紹介します。信頼される園づくりのために、ぜひ参考にしてください。
目次
園児が怪我をしたときの保育園の対応フロー《実践編》
園児が怪我をした際には、初動対応の速さと正確さが信頼につながります。
ここでは、現場での動きから保護者への説明まで、保育園が取るべき実践的な対応フローを
解説します。
現場での初期対応(安全確保・応急処置)
まず最優先すべきは、園児の安全確保です。
怪我の程度にかかわらず、速やかに現場から離し、落ち着ける場所に誘導します。
出血や腫れがある場合は、すぐに応急処置を行いましょう。
清潔なガーゼで止血し、冷やす処置などが基本です。
このとき、子どもが不安にならないよう、優しい声掛けも忘れずに行います。
応急処置が済んだら、怪我の程度や経過を観察し、必要に応じて医療機関の受診を判断しま
す。
園内での情報共有・報告ルールの徹底
初期対応と並行して、園内での情報共有をすばやく行います。
担任だけで判断せず、主任や園長など管理職にも必ず報告しましょう。
また、保育日誌やヒヤリハット記録などへの記録も重要です。
「いつ・どこで・なぜ・どうなったか」を時系列で残しておくことで、今後の対応や改善に
も活かせます。
必要ならば病院へ連れて行く
出血が止まらない、腫れが引かない、転倒時に頭を打ったなどの場合には、迷わず病院に連
れて行く判断が求められます。
このときは保護者に電話で連絡を取り、了承を得たうえで対応します。
救急車を呼ぶか職員が付き添うかは、園のルールと保護者の希望をもとに判断しましょう。
近隣の小児科・外科の受診先リストは、あらかじめ準備しておくとスムーズです。
保護者への説明とお詫びの言葉

保護者への対応は、園に対する信頼を左右する大きなポイントです。
電話連絡またはお迎え時に、誠意を持って丁寧に説明します。
事実関係の正確な説明(何が起きたのか、どのように対応したのか)
園児の様子(泣いていたか、会話ができるか、元気か)
応急処置や受診の内容
今後の再発防止策
以上を簡潔に、かつ冷静に伝えることが大切です。
園児が軽傷だった場合(例:すり傷・小さな打撲)
「○○ちゃんが園庭で遊んでいる最中に転んでしまい、ひざをすりむいてしまいました。す
ぐに流水で洗って消毒し、冷やして様子を見ました。元気はあり、泣いた後はすぐに落ち着
いて遊びに戻れています。」
このように、状況と対応を伝えたうえで、「ご心配をおかけして申し訳ございません」と誠
意を伝えましょう。
保護者が神経質な場合や不安が強そうなとき
感情的になってしまう保護者には、まず共感を示すことが大切です。
「ご心配なお気持ち、お察しします」「お子さまの安全を第一に、今後も気をつけてまいり
ます」といった声かけを先に行うことで、相手の不安は和らぎます。
また、説明は感情的ではなく客観的に行うようにします。
園児同士の喧嘩による怪我の場合(例:噛みつき・衝突)
噛みつきなどのトラブルでは、「加害・被害」という言葉は避け、状況説明に徹することが
肝心です。
「遊びの中で○○くんと接触があり、その際に噛んでしまったようです」と伝え、双方の保
護者に丁寧な説明を行いましょう。
加害側の保護者への伝え方も配慮が必要です。「あくまで成長過程の中での出来事」である
ことを理解してもらえるよう言葉を選びましょう。
病院受診が必要な怪我の場合
医師の診断内容を共有し、今後の経過観察や通院の必要性も伝えます。
また、園としての再発防止策を示すことで、保護者の安心感につながります。
対応記録と保管のポイント
すべての対応内容は、記録として残しておくことが重要です。
後からトラブルになった際の証拠として活用できるほか、園全体での改善材料にもなります。
日時・場所・怪我の状況
初期対応と処置の内容
保護者への連絡内容
医療機関の診断内容(必要に応じて)
職員間の共有状況
記録はデジタルと紙媒体の両方で残し、一定期間保管しておくことをおすすめします。
保護者への報告タイミングについて

園児が怪我をした際、保護者への報告は「初期対応が落ち着いたあと、速やかに行う」のが基本です。
出血や腫れなどがある場合は、応急処置をしたうえで、できるだけ早く電話連絡をします。
軽微な怪我(すり傷・小さな打撲など)の場合は、お迎え時に対面で報告することが一般的です。
ただし、顔など目立つ部位の怪我は、事前に電話連絡を入れると安心感につながります。
保護者が不在時は、連絡先を順にあたり、できる限り当日中に伝えるようにしましょう。
報告の遅れは不信感につながるため、園内で対応ルールを統一しておくことが大切です。
保護者対応における NG 例と信頼を守る伝え方のコツ
園児が怪我をした際、保護者とのやり取りは園の信頼性を大きく左右します。
同じ出来事でも、伝え方ひとつで信頼が深まることもあれば、不信感を生むこともあります。
ここでは、よくある NG 対応と、それを避けるための具体的な伝え方の工夫を紹介します。
平謝りをしない。まずは共感と安心感の提供を意識する
園児が怪我をしたとき、「申し訳ありません」を繰り返すだけでは、かえって保護者の不安
や不満を強めてしまうことがあります。
まずは、「お子さまのご様子はいかがでしょうか」「驚かれたことと思います」といった共感
の言葉を最初に伝えることが大切です。
保護者は、「この園は子どもを大切に考えてくれている」と感じることで、感情を落ち着け
やすくなります。
そのうえで、「怪我の状況」「園での対応」「再発防止策」を順に伝えると、冷静に受け止め
てもらいやすくなります。
「どこで・なにが・どうなったか」を明確にする
あいまいな説明は、保護者の不信感につながります。
説明の際には、以下の 3 点をはっきり伝えましょう。
どこで(園庭・室内・遊具の近くなど)
なにが(走っていて転倒、ぶつかってしまった等)
どうなったか(すり傷・たんこぶ・腫れなどの様子)
たとえば、「園庭で走っていた際に、ほかのお子さまとぶつかり、ひざをすりむいてしまい
ました」と具体的に伝えると、保護者も状況をイメージしやすくなります。
不必要に細かく説明する必要はありませんが、「なにが起きたのか、わかる」ことが信頼に
つながります。
誰かのせいにしない
「職員の目が届いていなかった」「お友だちが悪かった」など、特定の誰かを責めるような
発言は避けましょう。
責任の所在よりも、「園全体での対応」を伝えることが大切です。
たとえば、「見守っていた職員がすぐに対応し、状況を共有しました」と伝えることで、園
全体で子どもを大切にしている姿勢が伝わります。
また、保護者が職員や他の園児に対して強く怒りを示した場合も、感情をあおるような言葉
は控えましょう。
保護者のタイプに合わせて対応を変える
保護者には、冷静に受け止める方もいれば、些細なことでも不安や不満を強く感じる方もい
ます。
そのため、以下のようなタイプ別対応を意識すると良い結果につながりやすくなります。
保護者のタイプ 対応のポイント
心配性で感情的になりやすい 共感の言葉を先に伝え、安心できる言葉を繰り返す
冷静に事実を知りたいタイプ 時系列で客観的に説明し、資料があれば提示する
他の保護者に影響しやすいタイプ 園の方針を丁寧に伝え、不安が広がらないように配慮
する
誰にでも同じように対応するのではなく、「この方にはどう伝えると安心してもらえるか」
を意識すると、信頼関係が築きやすくなります。
保育園で園児の怪我を未然に防ぐ方法
保育園での怪我はゼロにはできなくても、限りなく防ぐことは可能です。
そのためには、日常的な環境整備や職員の意識改革が不可欠です。
ここでは、保育園で怪我のリスクを下げるための具体的な対策を 4 つの観点から紹介しま
す。
園内環境の見直しと安全対策

まずは物理的な「園の環境」から見直しましょう。
段差・すべりやすい床・尖った角など、日常の中に潜む危険を定期的にチェックします。
対策としては、
クッションマットやコーナーガードの設置
遊具や家具の固定と点検
照明や床材の見直し(滑りにくさや視認性の向上)
入口・階段付近の安全柵やゲート設置
また、毎月一回の安全点検をルール化することで、事故の芽を早期に発見できます。
職員の連携とヒヤリハットの共有
子どもの動きは予測できないことも多いため、ひとりの職員だけで防ぐのは難しいもので
す。
だからこそ、職員同士の連携が怪我防止の鍵となります。
具体的には、次のような取り組みが効果的です。
ヒヤリハット事例を毎週共有する
担任以外の職員も全園児の特徴を把握する
忙しい時間帯(登園時・昼食時・外遊び前後)にフォロー体制を強化する
事故が起きたあとではなく、「起きるかもしれない」という視点で情報を共有することで、
園全体の安全意識が高まります。
保育士の観察力と声掛けの質を高める
怪我を未然に防ぐうえで、保育士の「気づき力」は重要な要素です。
子どもの顔色・動き・表情の変化に早く気づけるよう、観察の精度を高めていきましょう。
また、声掛けひとつでも怪我の予防につながります。
たとえば、走り出しそうな園児には「ゆっくり歩こうね」「段差に気をつけてね」といった
一言をかけるだけで、転倒リスクが下がります。
観察力と声掛けは経験と意識で育まれるものです。
職員研修などを通じて、継続的にスキルアップを図ることが大切です。
園児、保育士ともに危険回避力を育てる
子ども自身にも「気をつける力」を育てていくことが、長期的な安全対策になります。
年齢に応じて「なぜ危ないのか」「どうすれば避けられるのか」を少しずつ伝えていきましょう。
また、保育士にも「常に危険を想定する習慣」を身につけてもらう必要があります。
たとえば、
運動遊びの前に危険個所を確認する
雨上がりの園庭では滑りやすい場所を事前にチェックする
こうした積み重ねが、事故を未然に防ぐ力につながります。
まとめ:日常の積み重ねが信頼される園づくりにつながる
園児が怪我をしたとき、保育園がどのように対応するかは、保護者からの信頼に直結します。
丁寧な初動対応、冷静で誠実な説明、正確な記録管理──そのすべてが信頼構築の土台です。
さらに、園全体で安全への意識を高め、子ども・保育士ともに危険回避力を育てていくことが、
トラブルを未然に防ぎ、安心して預けられる保育環境を築く鍵となります。
日々の小さな気づきと行動が、園全体の安心と信頼につながっていくのです。
採用活動の質も園の安心安全を左右します
「採用担当らいん君」で信頼できる保育士の確保を
怪我やトラブルを防ぐうえで欠かせないのが、経験豊富で信頼できる保育士の存在です。
しかし、近年は保育士不足が深刻化し、「良い人材がなかなか採用できない」と悩む園も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、LINE を活用した保育士採用支援ツール「採用担当らいん君」です。
・応募者とのやり取りを LINE でスムーズに管理
・時間帯を問わず連絡が取りやすくなる
・園の魅力を動画やメッセージで丁寧に伝えられる
「採用担当らいん君」を活用することで、採用業務の負担を軽減しつつ、保育の質を支える“信頼できる仲間”との出会いがスムーズになります。
保育園の安全・安心を守るためにも、「人材確保」の質を見直してみませんか?
詳しくは、採用担当らいん君|公式サイトをご覧ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。