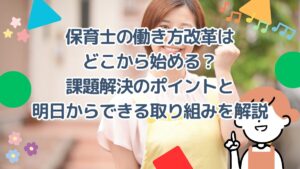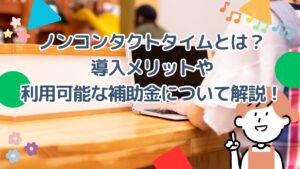保育士不足はなぜ?5つの原因と待遇改善の現状、働きやすい職場を見つける方法を解説
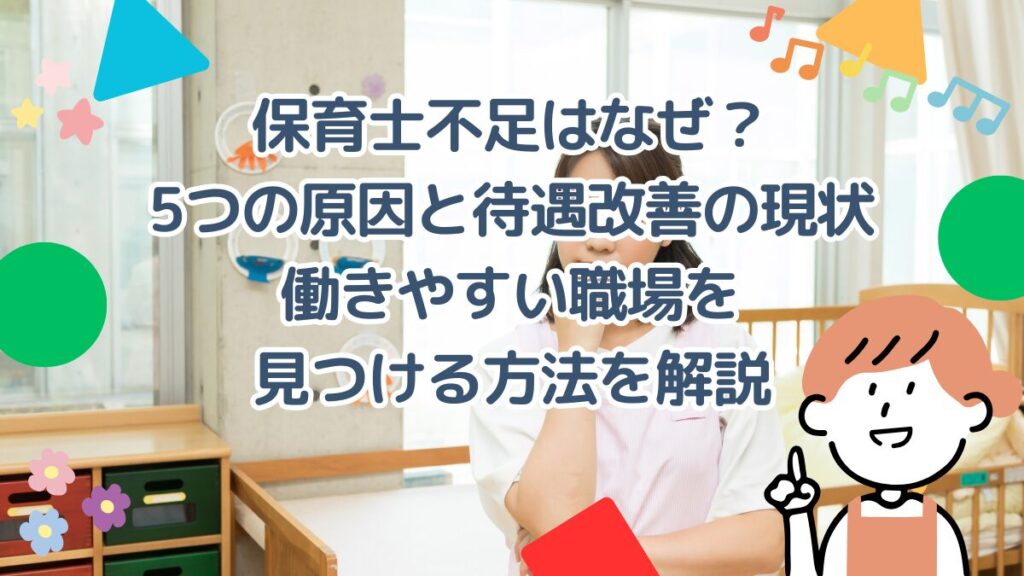
子どもの成長を間近で支える、やりがいのある仕事、保育士。しかしその一方で、責任の重さに見合わない給与や、終わりの見えない事務作業、多忙さからくる心身の疲れに、「このままでいいのだろうか」と、ふと不安を感じることはありませんか。
「保育士不足」という言葉をニュースで耳にするたびに、ご自身の職場の状況と重ね合わせ、将来に対して漠然とした不安を抱えている方も少なくないはずです。
この記事では、なぜ保育士不足がこれほどまでに深刻化しているのか、その根本的な原因を客観的なデータに基づいて紐解いていきます。さらに、国や保育園が進めている具体的な待遇改善策や、私たち保育士が今後、より良い環境で自分らしく働き続けるためのキャリアの選択肢について、詳しく解説します。ご自身の現状を見つめ直し、未来への一歩を踏み出すためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
目次
保育士不足の現状は?有効求人倍率と待機児童問題

保育士不足は、日本の社会が抱える深刻な問題の一つです。ニュースなどで耳にする機会は多いものの、その実態を正確に把握している方は少ないかもしれません。ここでは、客観的なデータを用いて、保育士不足の現状を解説します。
有効求人倍率は依然として高い水準
保育士の不足状況を示す指標の一つに「有効求人倍率」があります。これは、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す数値で、1倍を超えると人手が不足している状態を意味します。
厚生労働省のデータによると、2024年1月時点での保育士の有効求人倍率は3.54倍でした。全職種の平均が1.35倍であることと比較すると、保育士の不足がいかに深刻であるかが分かります。これは、保育士を探している1人の求職者に対して、3件以上の求人があるという状況を示しており、全国的に保育士の確保が緊急の課題となっています。
| 職種 | 有効求人倍率(2024年1月) |
| 保育士 | 3.54倍 |
| 全職種平均 | 1.35倍 |
待機児童問題は保育の受け皿確保が課題
保育士不足が直接的に影響するのが「待機児童問題」です。保育施設への入所を希望しているにもかかわらず、定員オーバーなどで入所できない子どもたちの問題は、長年社会問題として議論されてきました。
近年、国や自治体の取り組みにより保育施設の数は増加し、待機児童数は減少傾向にあります。例えば、2017年4月に約2.6万人いた待機児童は、2022年4月には約3千人まで減少しました。しかし、これは問題の完全な解決を意味するわけではありません。
共働き世帯の増加に伴い、保育の需要は依然として高く、国は2024年度末までに約14万人分の保育の受け皿を新たに確保する必要があるとしています。保育施設という「ハコ」はあっても、そこで働く「ヒト」、つまり保育士が不足している限り、待機児童問題の根本的な解決には至らないのです。
保育士不足が起こる5つの主な原因

なぜ、これほどまでに保育士は不足しているのでしょうか。その背景には、保育士という仕事を取り巻く複合的な要因が存在します。ここでは、主な5つの原因について、具体的なデータと共に掘り下げていきます。
責任の重さに対して給与が低い
保育士不足の最大の原因として挙げられるのが、賃金の低さです。厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」を見ると、全産業の平均月収が約31.2万円であるのに対し、保育士の平均月収は約26.7万円に留まっています。子どもの命を預かるという大きな責任を伴う仕事でありながら、その対価が他の職種と比較して低いことが、保育士のなり手を減らし、離職を招く大きな要因となっています。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/dl/01.pdf
膨大な業務量とサービス残業の常態化
保育士の仕事は、子どものお世話をするだけではありません。日々の保育計画の作成、連絡帳の記入、保護者へのお便り作成、行事の準備など、その業務は多岐にわたります。多くの園では、これらの事務作業を保育時間外に行うことが常態化しており、結果として長時間労働や持ち帰り残業につながっています。人員が不足している園では、こうした負担がさらに重くのしかかり、心身の疲弊から離職を選ぶ保育士が後を絶ちません。
不規則な勤務時間と休暇の取りにくさ
保育園は、保護者の就労形態に合わせて早朝から夜間まで開園しており、保育士はシフト制で勤務するのが一般的です。しかし、慢性的な人手不足から、シフトが過密になったり、希望通りの休暇が取得できなかったりするケースが少なくありません。
特に、運動会や発表会などの行事前には準備で多忙を極め、休日出勤を余儀なくされることもあります。このようなワークライフバランスの取りにくさが、特に結婚や出産などのライフイベントを迎えた女性保育士の離職につながっています。
保護者対応や職員間の人間関係の難しさ
保育士は、子どもだけでなく保護者との良好な関係構築も求められます。しかし、中には過度な要求をする保護者も存在し、その対応に精神的なストレスを抱える保育士は少なくありません。また、保育園は女性が多い職場であるため、職員間の人間関係に悩むケースもあります。保育観の違いや、先輩・後輩とのコミュニケーションの難しさが、職場への不満となり、退職の引き金となることもあります。
潜在保育士の存在と復職への壁
「潜在保育士」とは、保育士の資格を持ちながらも、保育の現場で働いていない人々のことを指します。厚生労働省の調査によると、保育士資格の登録者約167万人のうち、約102万人が潜在保育士であると推計されています。
これは、資格保有者の実に6割以上が、何らかの理由で保育の仕事から離れていることを示しています。一度離職すると、最新の保育知識やスキルの習得、子育てとの両立などに不安を感じ、復職へのハードルが高くなってしまうのです。この膨大な数の潜在保育士を、いかにして現場に呼び戻すかが、保育士不足解消の大きな鍵となります。
保育士不足を解消するための国の対策

深刻な保育士不足に対し、国も手をこまねいているわけではありません。保育士の確保と定着を目指し、待遇改善や働きやすい環境整備に向けた様々な施策を打ち出しています。ここでは、代表的な国の対策について解説します。
処遇改善等加算による給与アップの取り組み
保育士の給与水準の低さを改善するため、国は「処遇改善等加算」という制度を設けています。これは、職員のキャリアアップの仕組みを整えたり、賃金改善に取り組んだりする保育園に対して、国が補助金を支給する制度です。この制度により、保育士の給与は年々改善傾向にあります。例えば、技能・経験を積んだ職員には月額最大4万円が加算される仕組みなどがあり、保育士がキャリアに応じて着実に昇給できる環境の整備が進められています。
保育士宿舎借り上げ支援事業による住居サポート
特に都市部では、家賃の高さが若手保育士の生活を圧迫する一因となっています。そこで国は、保育園が職員のために借り上げたアパートなどの家賃の一部を補助する「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。
この制度により、保育士は月額最大82,000円の家賃補助を受けることができ、経済的な負担を大幅に軽減することが可能になります。これにより、地方出身者や一人暮らしの保育士が安心して働き続けられるよう支援しています。
保育士・保育所支援センターによる再就職支援
全国の都道府県には「保育士・保育所支援センター」が設置されており、保育の仕事から離れている潜在保育士の再就職をサポートしています。センターでは、最新の求人情報の提供や就職相談、復職に向けた研修などを実施しています。ブランクがあることへの不安を解消し、スムーズに現場復帰できるよう、きめ細やかな支援を行っています。
ICT化推進による業務負担の軽減
保育士の大きな負担となっている書類作成などの事務作業を軽減するため、国はICT(情報通信技術)システムの導入を支援しています。登降園管理システムや、保護者との連絡帳アプリ、指導計画作成支援ソフトなどを導入することで、業務の効率化を図ります。ICT化によって生まれた時間を、子どもと向き合う時間や研修に充てることで、保育の質向上と保育士の負担軽減の両立を目指しています。
保育園側で進む労働環境の改善策

国の施策と並行して、各保育園でも保育士が働きやすい環境を作るための様々な取り組みが進められています。人材の確保と定着は、保育園の安定した運営に不可欠であり、魅力的な職場づくりが急務となっているためです。
基本給や手当の見直しによる賃金アップ
国の処遇改善加算を確実に職員に還元することはもちろん、園独自の取り組みとして基本給のベースアップや手当の新設・拡充を行う保育園が増えています。職員の頑張りを正当に評価し、給与という目に見える形で応えることで、仕事へのモチベーションを高め、離職率の低下につなげています。
| 改善の取り組み | 具体例 |
| 基本給の改善 | 全職員の基本給を一律で引き上げる。 |
| 手当の拡充 | 資格手当、役職手当、住宅手当などを充実させる。 |
| 賞与の増額 | 業績に応じて賞与(ボーナス)の支給額を増やす。 |
業務の効率化と残業時間の削減
保育士の負担を減らし、プライベートな時間を確保するために、業務の見直しは不可欠です。ICTシステムの導入による事務作業の効率化はもちろん、行事内容の簡素化や、壁面装飾の削減、書類フォーマットの統一など、様々な工夫が行われています。また、保育補助者を積極的に採用し、保育士が保育に専念できる体制を整える園もあります。
働きやすい職場環境と人間関係の構築
職員が安心して長く働けるためには、風通しの良い職場環境が何よりも重要です。定期的な面談を実施して職員の悩みや意見を吸い上げたり、ハラスメント対策の窓口を設置したりするなど、コミュニケーションの活性化とトラブルの未然防止に努めています。職員同士が互いを尊重し、チームとして協力し合える文化を育むことが、人材定着の鍵となります。
多様な働き方を認める制度の導入
結婚や出産、介護など、ライフステージの変化に合わせて働き続けられるよう、多様な勤務形態を導入する園も増えています。短時間勤務制度や、週3日勤務、固定時間勤務など、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を認めることで、優秀な人材の離職を防ぎ、潜在保育士の復職を促しています。
保育士として今後どうキャリアを築くべきか

国や保育園による労働環境の改善が進む中、私たち保育士自身も、今後のキャリアについて主体的に考えていく必要があります。ここでは、自身の価値を高め、より良い環境で働き続けるための3つの視点を紹介します。
現職場で活用できる制度を確認する
まずは、現在お勤めの職場で利用できる制度がないか、改めて確認してみましょう。国の処遇改善加算が自身の給与にどのように反映されているか、自治体独自の家賃補助や手当の対象になっていないかなど、就業規則や給与明細をチェックしたり、園長や事務担当者に質問したりするのも良いでしょう。意外と知られていない制度を活用することで、現在の待遇が改善される可能性があります。
待遇や環境の良い園へ転職を検討する
もし現在の職場環境に大きな不満があり、改善が見込めない場合は、転職も有効な選択肢の一つです。保育士不足の今、保育士は「選ばれる」立場から「選ぶ」立場にあります。給与や休日数、残業時間、福利厚生などを比較し、自身の希望に合った、より働きやすい環境を提供してくれる保育園を探してみましょう。保育士専門の転職エージェントなどを活用すれば、非公開求人を含め、多くの情報を効率的に収集できます。
キャリアアップ研修で専門性を高める
国が推進する「保育士キャリアアップ研修」を受講することも、自身の市場価値を高める上で非常に有効です。この研修は、「乳児保育」や「障がい児保育」、「保護者支援」など8つの専門分野に分かれており、研修を修了することで専門リーダーや副主任保育士といった新たな役職に就くことができます。役職に就けば月額最大4万円の手当が支給されるだけでなく、自身の専門性を高め、保育士としてのキャリアに深みを持たせることができます。
まとめ

保育士不足は、低賃金や長時間労働、人間関係のストレスなど、様々な要因が絡み合った根深い問題です。しかし、国や保育園による処遇改善や労働環境の整備は着実に進んでおり、保育士がより働きやすい環境が整いつつあります。
このような状況の中、私たち保育士一人ひとりが、利用できる制度を正しく理解し、時には転職という選択肢も視野に入れながら、主体的にキャリアを形成していくことが重要です。この記事が、あなたが保育士として、今後も安心してやりがいを持って働き続けるための一助となれば幸いです。
また、採用難に直面している園にとっては、優秀な人材との出会いの機会を増やすことも重要です。
採用活動の効率化とマッチング精度の向上を実現するLINE型の採用支援サービス「採用担当らいん君」も、ぜひご活用ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。