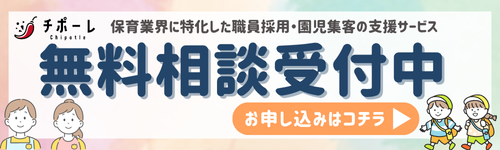【2025年版】保育士の離職率や離職理由について分かりやすく解説!

保育士は「離職率が高い職業」と言われることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。
厚生労働省の調査によれば、保育士全体の離職率は9.3%で、約10人に1人が毎年職場を去っていることになり、保育現場では人材確保が大きな課題となっています。
この記事では、保育士の離職率の実態や離職理由、また保育士が長く働ける職場環境づくりのポイントなどを詳しく解説します。
目次
保育士の離職率の現状
保育士の離職率について、具体的な数値から見ていきましょう。
厚生労働省の「保育士の現状と主な取組」によると、保育士全体の離職率は9.3%となっており、公立保育園の離職率が5.9%であるのに対し、私立保育園では10.7%と高くなっています。
|
区分 |
勤務者 |
採用者数 |
採用率 |
退職者数 |
離職率 |
|
全体 |
407,287人 |
60,830人 |
14.9% |
37,716人 |
9.3% |
|
うち公営 |
118,481人 |
10,087人 |
8.5% |
6,941人 |
5.9% |
|
うち私営 |
288,806人 |
50,743人 |
17.6% |
30,775人 |
10.7% |
また、経験年数別に見ると、若手保育士の割合が多いことも特徴的です。
保育士全体の中で、経験年数6年未満の保育士が全体の約5割を占めており、経験を重ねる前に離職してしまう保育士が多いことがわかります。
|
区分 |
2年未満 |
2~4年未満 |
4~6年未満 |
6~8年未満 |
8~10年未満 |
10~12年未満 |
12~14年未満 |
14年以上 |
総数 |
|
全体 |
15.5% |
13.3% |
11.1% |
9.5% |
7.9% |
6.7% |
5.8% |
30.1% |
100% |
|
うち公営 |
10.8% |
10.3% |
9.4% |
6.3% |
6.8% |
6.1% |
6.0% |
42.7% |
100% |
|
うち私営 |
17.9% |
14.9% |
12.0% |
10.2% |
8.5% |
7.1% |
5.8% |
23.6% |
100% |
保育士が離職する5つの主な理由
保育士がどのような理由で離職しているのかを知ることは、離職率改善の第一歩です。
厚生労働省の「保育士として就業した者が退職した理由 」の調査によると、主な離職理由は以下の5つに集約されます。
職場の人間関係
厚生労働省の調査では、保育士の離職理由のトップが「職場の人間関係」で33.5%となっています。
保育現場は女性が多い職場であり、少人数のチームで密に連携して働くことが多いため、人間関係の問題が発生しやすい環境と言えます。
具体的には園長や主任からの厳しい指導や管理スタイル、同僚との保育観の違いによる軋轢などがあります。
また、女性の多い職場特有の人間関係の難しさもあり、精神的な負担から離職を選ぶケースも少なくありません。
給料の低さ
「給料の安さ」は離職理由の上位に常にランクインしています。
特に私立保育園では、園によって給与体系や昇給制度に大きな差があり、長く働いても給与が大きく上がらないことへの不満が離職につながっているケースが多いようです。
国は保育士の処遇改善として2022年に月額平均9,000円(収入の3%程度)の引き上げを実施しましたが、すべての保育士に行き渡っているわけではありません。
仕事量の多さと労働時間の長さ
保育士の業務は子どもの保育だけではありません。連絡帳の記入、保育計画の作成、おたよりの制作、環境整備、保護者対応など、多岐にわたる業務を担っています。
特に行事前の準備や書類作成などで残業が増え、持ち帰り仕事が常態化している園も少なくありません。また、担任や主任など役職が上がるほど責任や業務量が増加しますが、それに見合った給与体系になっていない場合も多く、モチベーション低下につながっています。
妊娠・出産を機とした退職
保育士自身が妊娠・出産を機に離職するケースも多く見られます。子どもの成長を見守る仕事であるにもかかわらず、自分の子育てと仕事の両立が難しいという皮肉な状況があります。
具体的には、体力的に保育業務と育児の両立が厳しい、産休・育休制度はあっても、復帰後の働き方に不安があるといった理由から、妊娠・出産を機に離職を選択する保育士が少なくありません。
特に小規模な私立保育園では、産休・育休取得者の代替職員確保が難しいなどの理由から、制度はあっても取得しづらい雰囲気がある場合もあります。
健康上の理由(体力的な問題含む)
保育士の仕事は想像以上に体力を使います。子どもを抱っこしたり、おんぶしたり、園庭で一緒に走り回ったりと、常に動き続ける必要があります。
そのため、腰痛や腱鞘炎などの身体的な不調を訴える保育士も少なくありません。また、常に気を張った状態で子どもたちを見守る精神的な負担も大きく、メンタルヘルスの問題も発生しています。
特に人手不足の園では一人あたりの負担が増え、身体的・精神的な健康問題から離職するケースも見られます。
若手保育士の離職率が高い理由
先の保育士の経験年数データを見ると、6年未満の保育士が全体の約5割を占めており、若手の離職率が高い傾向にあります。
では、なぜ若手保育士は早期に離職してしまうのでしょうか。主な理由を解説します。
平均給与が他の職種に比べて低い
若手保育士の大きな離職理由の一つが「給与の低さ」です。厚生労働省の調査によると、保育士の平均月収は他職種と比べて低い傾向があります。責任の重さに比して報酬が見合わないと感じると、より条件の良い職場や異業種への転職を考える傾向があります。
残業や持ち帰り仕事が多い
保育業務は子どもとの関わり以外にも、計画作成や記録など多岐にわたります。
子どもたちが降園した後も、書類作成、制作物の準備、行事の準備など、業務は多岐にわたります。サービス残業や自宅に仕事を持ち帰ることも常態化しており、心身ともに疲弊してしまうことがあります。若手保育士は業務効率化が未熟なため、より負担が大きく、心身の疲労から離職につながります。
職場や保護者などの人間関係に悩みを抱えやすい
厚生労働省の調査によると、保育士の離職理由トップは「職場の人間関係」(33.5%)です。若手保育士は先輩・同僚との関係構築や保護者対応に不安を抱えやすく、特に子育て経験のない若手は保護者からの質問や要望に適切に応えられないプレッシャーを感じることも少なくありません。
若手保育士の離職防止には、初期研修の充実、メンター制度の導入、給与改善、業務効率化など複合的な対策が必要です。
公立と私立で離職率に差がある理由
先のデータから保育士の離職率は公立保育園が5.9%、私立保育園が10.7%と、約2倍の差があります。
この差はなぜ生じるのでしょうか。公立と私立の保育園の違いから、離職率の差の要因を探ってみましょう。
給与体系と昇給制度の違い
公立保育園の保育士は地方公務員として雇用され、給与体系も公務員に準じています。
一方、私立保育園では園ごとに給与体系が異なり、園の経営状況や方針によって大きな差があります。
公立保育園のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 経験年数に応じた安定した昇給制度がある
- 賞与(ボーナス)が確実に支給される
- 地域手当や住居手当などの各種手当が充実している
私立保育園では園によって状況が大きく異なりますが、昇給額が少なかったり、賞与が安定して支給されなかったりするケースもあります。この給与面での安定感の違いが、離職率の差につながっていると考えられます。
雇用の安定性の差
公立保育園は公的な運営基盤を持つため、園の統廃合などの大きな変化がない限り、雇用の安定性は高いと言えます。一方、私立保育園では経営状況によって雇用環境が左右されることもあります。
具体的には以下のような違いが挙げられます。
|
比較項目 |
公立保育園 |
私立保育園 |
|
運営基盤 |
自治体の予算に基づく運営経営破綻のリスクが低い |
少子化や競合園の増加などの影響を受けやすい |
|
雇用の安定性 |
人事異動はあるものの基本的には解雇リスクが低い |
園の方針変更や経営者の交代によって職場環境が大きく変わることがある |
この表は、ご提供いただいた情報に基づいて、運営基盤と雇用の安定性という2つの主要な観点から公立と私立の保育園の違いをまとめたものです。こうした雇用の安定性の違いも、公立と私立の離職率の差に影響していると考えられます。
福利厚生の充実度
公立保育園と私立保育園では、福利厚生の内容や充実度にも違いがあります。特に重要なのは、以下のような制度の違いです。
- 産休・育休制度とその取得のしやすさ
- 時短勤務や休暇取得の柔軟性
- 健康診断や各種保険の充実度
- 研修制度や自己啓発支援
公立保育園では公務員としての福利厚生が整備されており、特に産休・育休制度は取得しやすい環境が整っていることが多いです。私立保育園でも充実した福利厚生を提供している園はありますが、園によって差が大きいのが現状です。
こうした働きやすさに関わる福利厚生の差も、離職率に影響を与える重要な要因と言えるでしょう。
離職率を下げるための5つの効果的対策
保育士の離職率を下げるためには、離職の原因となっている問題に対して具体的な対策を講じる必要があります。ここでは、保育園の運営者や管理者が取り組むべき効果的な対策を5つご紹介します。
コミュニケーション改善による良好な人間関係づくり
離職理由のトップである「人間関係」の問題に対応するためには、職場内のコミュニケーションを改善することが重要です。
以下のような取り組みを通じて、「相談できる」「理解し合える」職場環境を作ることが、人間関係に起因する離職を防ぐ鍵となります。
|
項目 |
内容 |
|
定期的な個人面談の実施 |
悩みや不安を早期に発見し、解決するために、園長や主任が定期的に個人面談を行います。特に若手保育士には頻度を高めることで、孤立感を防ぐことができます。 |
|
ミーティングの質の向上 |
単なる連絡事項の伝達だけでなく、保育の悩みや成功事例を共有する時間を設けることで、チームとしての一体感を育みます。 |
|
メンター制度の導入 |
新人保育士に対して、直属の上司とは別に相談役となるメンターを付けることで、気軽に相談できる環境を作ります。 |
|
チームビルディング活動の実施 |
保育業務以外での交流の機会を設けることで、職員間の理解を深め、協力関係を築きます。 |
給与体系の見直しと処遇改善
給与面の不満は離職の大きな原因の一つです。
保育士の処遇改善のために以下のような対策が考えられます。
|
対策 |
内容 |
|
明確な昇給制度の確立 |
経験年数や能力、役職に応じた明確な昇給基準を設け、将来の見通しを持てるようにします。 |
|
処遇改善加算の活用 |
国の処遇改善加算を活用し、キャリアアップに応じた手当を支給することで、モチベーションの向上につなげます。 |
|
各種手当の充実 |
住宅手当、通勤手当、資格手当など、様々な手当を整備することで、実質的な収入アップを図ります。特に若手保育士には家賃補助などの生活支援が効果的です。 |
|
賞与の安定支給 |
業績に応じて変動するのではなく、安定して一定額以上の賞与を支給することで、経済的な安心感を高めます。 |
|
職務に応じた適切な評価 |
役職や特別な職務(行事担当、研修担当など)に対して、適切に評価し手当を支給することで、やりがいと報酬のバランスを整えます。 |
業務効率化とICT活用
保育士の業務負担を軽減するためには、業務の効率化が不可欠です。特にICT(情報通信技術)の活用は、書類作成や情報共有の効率化に大きく貢献します。
以下のような取り組みにより、保育士が子どもと直接関わる時間を増やし、本来の専門性を発揮できる環境を整えることが、離職防止につながります。
|
取り組み |
内容 |
|
保育支援システムの導入 |
連絡帳や指導案、日誌などの書類作成をデジタル化することで、業務時間を短縮します。特に手書きからデジタル化することで、記録の再利用や情報の共有が容易になります。 |
|
タブレット端末の活用 |
子どもの活動の記録や写真撮影にタブレット端末を活用し、その場で記録できる環境を整えます。 |
|
業務分担の最適化 |
園内の業務を洗い出し、保育士の専門性を活かすべき業務とそうでない業務を区別して、適切に分担します。例えば、清掃や事務作業の一部は非常勤スタッフに任せるなどの工夫が有効です。 |
|
会議の効率化 |
会議の目的と時間を明確にし、必要な情報は事前に共有するなど、会議時間の短縮と質の向上を図ります。 |
産休・育休制度の充実と復帰支援
保育士自身のライフイベントに対応できる職場環境を整えることは、長く働き続けるために重要です。特に女性が多い職場では、妊娠・出産・育児と仕事の両立支援が不可欠です。
保育士として子どもの成長を支える仕事に就きながら、自分の子育てとの両立ができないというのは皮肉な状況です。保育のプロフェッショナルが自身の子育ても大切にできる環境づくりが、長く働き続けられる職場の条件と言えるでしょう。
具体的には以下のような施策が考えられます。
|
施策 |
内容 |
|
産休・育休制度の周知と取得促進 |
制度の内容を明確に伝え、取得しやすい雰囲気づくりを心がけます。特に「取得すると迷惑がかかる」という心理的障壁を取り除くことが重要です。 |
|
代替職員の確保体制の整備 |
産休・育休取得者の業務をカバーするための代替職員確保の仕組みを整え、他の職員の負担増を防ぎます。 |
|
復帰後の柔軟な勤務体制 |
時短勤務や固定シフトなど、子育て中の職員が働きやすい勤務形態を提供します。 |
|
職場復帰支援プログラム |
長期間現場を離れていた保育士が安心して復帰できるよう、研修の機会や段階的な業務復帰の仕組みを整えます。 |
研修制度とキャリアパスの構築
保育士としての専門性を高め、将来のキャリアビジョンを描けることは、モチベーション維持と離職防止に大きく影響します。
具体的には以下のような取り組みがあります。
特に若手保育士が「この仕事を続けていく意味」や「将来の姿」を具体的にイメージできることが、早期離職の防止につながります。
|
取り組み |
詳細 |
|
体系的な研修制度の整備 |
新人、中堅、ベテランなど、経験や役割に応じた研修体系を整え、段階的にスキルアップできる環境を提供します。 |
|
キャリアパスの明確化 |
「保育士→主任→園長」といった一般的なルートだけでなく、「専門分野のエキスパート」「研修担当」など、多様なキャリアの道筋を示します。 |
|
自己啓発の支援 |
園外の研修参加や資格取得を奨励し、時間的・金銭的な支援を行います。 |
|
研修成果の発表機会 |
学んだことを実践し、その成果を発表する機会を設けることで、学びがいと成長の実感を持てるようにします。 |
保育士が働きやすい職場の選び方
保育士として長く働き続けるためには、自分に合った職場を選ぶことが非常に重要です。
ここでは、保育士が転職を考える際や、新卒で就職先を探す際に参考になる、働きやすい職場の見極め方をご紹介します。
園見学でチェックすべきポイント
実際に園を訪問して雰囲気を確認することは、書類だけではわからない職場環境を知る重要な機会です。園見学では以下のポイントに注目しましょう。
園見学の際は、遠慮せずに疑問点を質問することが大切です。
園側の対応の仕方からも、その園の体質を知ることができます。
|
確認ポイント |
観察内容 |
注意点 |
|
保育者と子どもの関わり方 |
保育者の笑顔、子どものびのびとした様子 |
緊張感が強すぎる雰囲気や指導不足は問題の可能性あり |
|
職員同士のコミュニケーション |
会話の様子、職場の雰囲気 |
協力し合う様子や自然な笑顔での会話があるか確認 |
|
園内の環境整備 |
清掃状況、整理整頓、安全対策 |
極端に整理が行き届いていない場合や安全面に不安がある場合は注意 |
|
園長や主任の対応 |
質問への答え方、職員への接し方 |
管理者の姿勢が園全体の雰囲気に大きく影響する |
求人票から読み取る職場環境
求人票には、園の基本情報だけでなく、働く環境に関する重要な情報が含まれています。以下のポイントを特に注意深くチェックしましょう。
求人票に書かれていない情報は、面接時に積極的に質問することをお勧めします。特に気になる点について質問した際の回答の具体性や誠実さも、園の姿勢を判断する材料になります。
|
確認項目 |
確認ポイント |
|
給与体系と昇給制度 |
• 基本給と各種手当の有無 • 昇給の仕組み • 経験年数に応じた昇給制度の有無 • 将来的な給与アップの見通し |
|
勤務時間と残業の実態 |
• 固定残業代(みなし残業)の有無と時間数 • 実際の労働時間の目安 • シフト制の場合はローテーションの詳細 |
|
福利厚生の内容 |
• 社会保険の加入状況 •住宅手当の有無と金額(最大8万円近い補助がある園も) • 通勤手当の有無 • 退職金制度の有無 |
|
休暇制度の充実度 |
• 有給休暇の取得率 • 産休・育休の取得実績 • 具体的な数字(有給休暇取得率〇%など)の確認 |
|
離職率や平均勤続年数 |
• 直接的な記載の有無 •「勤続5年以上の職員が〇%」などの情報 • 職場の定着率の参考になる情報 |
経営方針や園長の考え方を知る方法
保育園の雰囲気は、経営方針や園長の考え方に大きく影響されます。以下の方法で、園の根本的な方針を把握することが重要です。
園の経営方針や園長の考え方と自分の保育観が合致することは、長く働き続けるための重要な条件です。表面的な条件だけでなく、根本的な価値観のマッチングを大切にしましょう。
|
調査方法 |
内容 |
|
園のホームページやSNSをチェック |
園の教育方針や日々の活動の様子、保護者向けの情報発信などから、園の価値観や雰囲気を知ることができます。更新頻度や内容の充実度も、園の運営姿勢を反映していることが多いです。 |
|
面接時の質問を工夫する |
「園として大切にしていることは何ですか?」「職員の成長をどのようにサポートしていますか?」など、園の方針に関する質問をすることで、経営者や園長の考え方を知ることができます。 |
|
第三者評価の結果を確認する |
福祉サービス第三者評価を受けている園であれば、その結果を確認することで、客観的な視点から園の運営状況を把握できます。 |
|
在職者や元職員の評判を調べる |
可能であれば、現在働いている職員や以前勤めていた方から、実際の職場環境について話を聞くことも有益です。ただし、個人的な意見である点は考慮する必要があります。 |
保育士の離職率を下げるためのツール「採用担当らいん君」
この記事では、保育士の離職率の実態と離職の原因、そして離職を防ぐための対策について詳しく解説してきました。
保育士の離職率を下げるためには、園の環境改善だけでなく、採用段階から適切な人材を見極めることも重要です。
保育園の人材確保・定着に役立つツールとして「採用担当らいん君」があります。
「採用担当らいん君」は、保育施設の採用担当者の業務負担を軽減しながら、応募者とのコミュニケーションを円滑にするLINE連携型の採用管理ツールです。
このツールを活用することで、以下のようなメリットが期待できます。
-
- 応募者との円滑なコミュニケーション:若手保育士が多く使うLINEを通じて連絡を取り合えるため、レスポンスが早く、採用プロセスがスムーズに進みます。
-
- ミスマッチの防止:事前に職場の雰囲気や保育方針を共有しやすくなり、入職後のギャップを減らせます。
-
- 応募者情報の一元管理:応募者の情報を一元管理できるため、採用業務の効率化が図れます。
保育士の離職理由の多くは「職場の人間関係」や「想像と違った職場環境」です。
採用段階から丁寧なコミュニケーションを取り、お互いの価値観や期待をすり合わせることで、入職後のミスマッチを防ぐことができるでしょう。
離職率を下げ、長く働ける職場づくりの第一歩は、適切な採用から始まります。詳しい情報は下記のリンクからご確認ください。