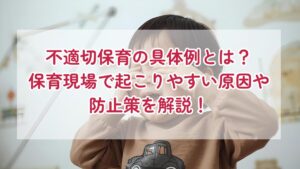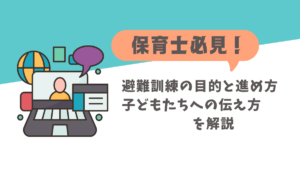【保存版】ペープサートとは?特徴やねらい、年齢別題材の選び方や作り方を解説!
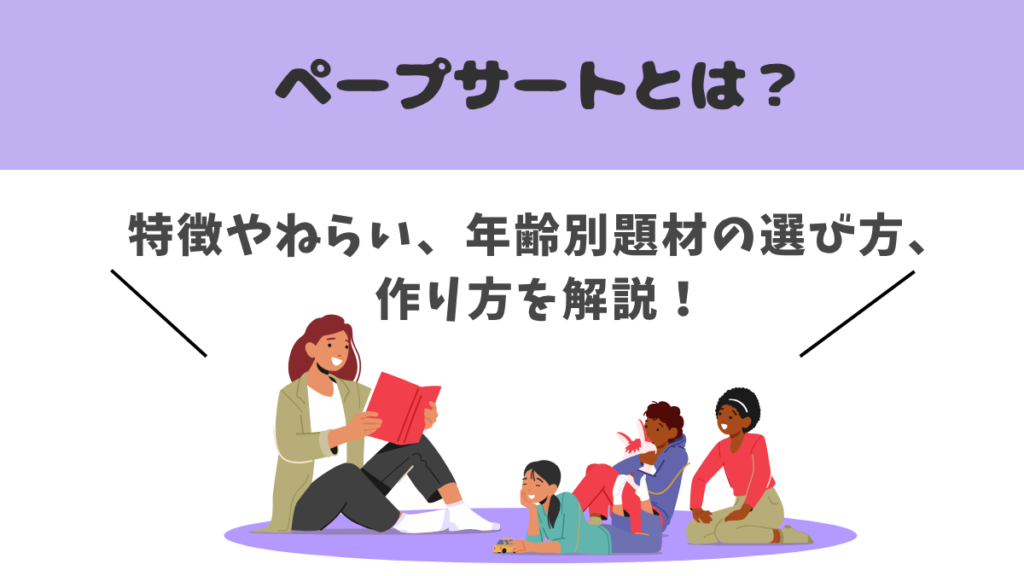
保育の現場で「子どもたちが夢中になれる活動を取り入れたい」と思ったことはありませんか。そんなときに役立つのが、紙と棒を使って演じる「ペープサート」です。
ペープサートは準備が比較的簡単でありながら、子どもの想像力や集中力を高める効果があるため、保育士にとって強い味方になります。
本記事では、ペープサートの基本的な特徴や現場でのメリット、年齢別題材の選び方、作り方の手順、そして子どもがより楽しめる工夫までを、心理学的な裏付けや実際の事例とともに解説します。保育の引き出しを増やしたい先生方はぜひ参考にしてください。

目次
ペープサートとは?
保育園や幼稚園で広く取り入れられている「ペープサート」。紙に描いたキャラクターを割りばしや厚紙に貼りつけて動かす紙人形劇の一種で、保育の現場では子どもの心を引きつける人気の活動です。
ペープサートは「紙(paper)」と「人形劇(puppet show)」を組み合わせた造語であり、誰でも手軽に作れる点が特徴です。
同じく保育現場で人気の教材に「パネルシアター」があります。ペープサートと混同されやすいですが、実は次のような違いがあります。
| 項目 | ペープサート | パネルシアター |
| 材料 | 紙と棒(割りばし・ストローなど) | 不織布パネルと人形(不織布を貼り付け) |
| 表現方法 | 人形を手で動かして演じる | パネルに貼り付けて登場・移動させる |
| 観客の見え方 | 立体的にキャラクターが動く | 大きな舞台のように場面転換がしやすい |
| 特徴 | 手軽に作れる・子どもと距離が近い | 視覚的に豪華・大人数に向けて展開しやすい |
ペープサートは「子どもと距離が近い、小規模な場面」で効果的に使えます。一方でパネルシアターは「行事や大人数の集会」などで物語をダイナミックに見せたいときに適しています。
参考:保育所保育指針解説
ペープサートを現場に取り入れるメリット

ペープサートは単なる遊びではなく、子どもの発達を支える教育的効果がある教材です。ここでは、保育現場で取り入れることで得られる主なメリットを整理します。
子どもの興味・関心を引きやすい
ペープサートは動く絵本のような感覚で、子どもが自然と集中しやすいのが特長です。心理学の「注意の選択理論」によれば、子どもは動きのある対象や音声に強く関心を示します。人形が左右に揺れたり表情を変えることで、絵本の読み聞かせ以上に視覚と聴覚を同時に刺激でき、興味を持続させやすいのです。
実際に園で行事前の導入としてペープサートを活用した例では、通常の読み聞かせよりも子どもの発言が増え、会話に参加する子の割合が高まったという報告もあります。
話を理解しやすくなる
ペープサートはキャラクターの動きとセリフが結びつくため、物語の流れや因果関係を理解しやすくなります。特に言葉がまだ発達段階にある子どもにとって、視覚情報が補助になることで理解が深まります。
『保育所保育指針解説』でも、子どもは具体的な事物や感覚的な体験を通して言葉の意味を理解しやすいと示されています。例えば、動物が食べ物を食べる様子など、身近な場面を動きで表現すると、抽象的な言葉だけよりも直感的に理解につながると考えられます。
想像力や表現力が育つ
ペープサートは受け身の鑑賞だけでなく、子どもが自ら演じる活動にも応用できます。自分でキャラクターを動かし、声をあてる体験は「役割取得」と呼ばれる心理的スキルを育み、他者の視点に立つ練習になります。これは社会性や共感力の発達に直結する重要な要素です。
また、保育士が演じた後に「次はみんなでやってみよう」と声をかけることで、子どもたちは自分の言葉や動きで表現する楽しさを味わえます。表現活動としての価値が高く、保育指針で求められる「創造的な活動」の実践にもつながります。
【年齢別】ねらいを活用した題材の選び方
ペープサートは年齢に応じて題材を工夫することで、子どもの発達段階に合った学びを引き出せます。ここでは1歳から5歳までの年齢別に、ねらいとおすすめ題材を紹介します。
【1~2歳】想像力を育てる
1~2歳の子どもは言葉の発達がまだ始まったばかりです。そのため、簡単な動きや身近な題材を取り入れることで、安心して楽しめるようになります。
おすすめ題材例:
◆いないいないばあ
◆バナナが一本ありました
◆ 動物の鳴き声を真似するストーリー
発達心理学によれば、1~2歳児は「感覚運動期」から「前操作期」への移行期であり、見たものと音のつながりに強い関心を持ちます。ペープサートのシンプルな動きは、この段階の「模倣」や「予測する力」を自然に刺激します。
【3~4歳】空想力を育てる
3~4歳になると語彙が増え、空想的な物語を理解する力がついてきます。キャラクター同士の会話やちょっとした物語性のある題材が効果的です。
おすすめ題材例:
◆おおきなかぶ
◆三匹のこぶた
◆ 季節の歌に合わせたストーリー(七夕、クリスマスなど)
この時期は「ごっこ遊び」が盛んになる年齢であり、役割を演じることを通じて社会性が育まれます。園で「三匹のこぶた」をペープサートにして演じた事例では、子ども同士で「こぶた役をやりたい」「オオカミになりたい」と自然に役を分け合い、協調性が育つ姿が見られました。
【5歳~】言語化能力を育てる
5歳以上になると、物語を理解するだけでなく、自分で言葉を使って説明したり感想を述べる力が高まります。長めのお話やストーリー展開のある題材を選ぶことで、言語化能力をさらに伸ばせます。
おすすめ題材例:
◆ももたろう
◆複雑な展開の童話
◆オリジナルストーリーを作る活動
教育心理学者ヴィゴツキーの「最近接発達領域(ZPD)」理論によると、子どもは大人の支援を受けながら一歩先の課題に挑戦することで能力を伸ばします。保育士が演じたあとに「次はみんなで続きを考えてみよう」と問いかけると、子どもたちは自分の言葉で物語を組み立てる経験を積むことができます。
ペープサートの作り方

ペープサートは特別な道具を必要とせず、身近な材料で作れるのが大きな魅力です。ここでは、必要な材料から具体的な作り方、サイズの工夫までを解説します。
必要な材料
◆キャラクターを描いた紙(画用紙や厚紙)
◆割りばしやストローなどの持ち手
◆はさみ、のり、テープ
園によってはラミネート加工を施し、繰り返し使えるよう工夫することもあります。子どもが触っても破れにくくなるため、安全面からもおすすめです。
作り方
1. 画用紙にキャラクターや背景を描く
2. はさみで丁寧に切り抜く
3. 割りばしやストローを裏側にテープで固定する
4. 必要に応じて裏面を補強する
このシンプルな工程で、すぐに舞台に立てるペープサートが完成します。心理学的にも「自分の手で作った教材を使う」ことは保育士自身の愛着やモチベーションを高める効果があるとされます。
ペープサートのサイズ
サイズは A4 程度の大きさが標準的です。子どもが集まる保育室で全員に見せるためには、ある程度大きめに作ると効果的です。
一方で、個別や少人数で楽しむ場合には A5 サイズ程度でも十分です。特に1〜2歳児は近距離でのやり取りが中心になるため、小さめサイズの方が安心感を与えやすいという実践例もあります。
子どもが夢中になる!ペープサートを楽しんでもらうコツ
同じペープサートでも、ちょっとした工夫で子どもの集中度や楽しさは大きく変わります。ここでは、現場ですぐに役立つ5つのポイントを紹介します。
入念に準備する
物語の流れやセリフを事前に練習しておくことで、子どもに安心感を与えられます。
子どもが見やすい高さ・角度にする
演じる位置は子どもの目線より少し高めが効果的です。
子どもに問いかける場面を入れる
「このあとどうなると思う?」など問いかけを入れることで、子どもは主体的に参加できます。
一人ひとりの様子を見ながら演じる
途中で飽きてしまう子がいればテンポを早めたり驚きの仕掛けを入れると効果的です。
人形は意味があるときだけ動かす
常に人形を動かしていると混乱を招きます。動きに緩急をつけることで感情移入を高められます。
まとめ
ペープサートは、子どもたちが物語に親しみ、想像力や表現力を育むことができる魅力的な教材です。特別な材料は不要で、年齢に応じて題材を工夫すれば、日々の保育をより楽しい時間に変えてくれます。
しかし、こうした取り組みを現場で継続するには、人材確保や保護者への情報発信も欠かせません。どれだけ工夫した保育を実践しても、その魅力が伝わらなければ「人材採用」や「園児募集」の面では十分に活かしきれないからです。
そこでおすすめなのが、LINEを活用した支援ツール「採用担当らいん君」や「園児募集らいん君」です。
– 採用担当らいん君:保育士採用における問い合わせ対応や応募管理を効率化できる
– 園児募集らいん君:保護者に園の魅力や活動を分かりやすく届けられる
ペープサートのような工夫ある取り組みを、採用や園児募集の場面でもしっかり伝えられるよう、こうしたツールを活用してみてはいかがでしょうか。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。