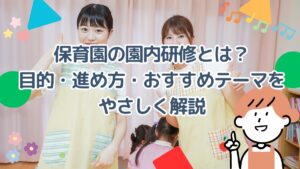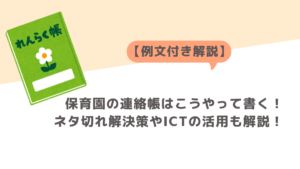【事例つき】保育ドキュメンテーションの始め方とは?導入メリットや書き方について徹底解説
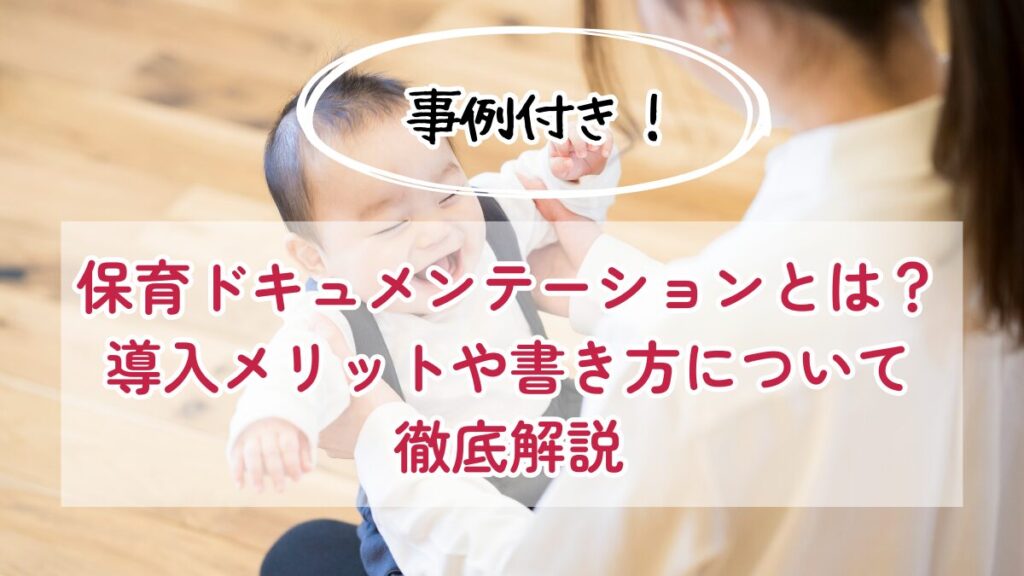
保育の専門性を「見える化」し、保護者や地域に伝える手段として注目されているのが保育ドキュメンテーションです。
単なる記録ではなく、子どもの行動の背景や保育者の意図を言語化し、成長の意味を共有する取り組みとして、多くの園で導入が進んでいます。一方で「時間が足りない」「どう書けばいいか分からない」といった課題も多く、ICTの活用や園全体での取り組み体制づくりが成功の鍵となります。
本記事では、ドキュメンテーションの基礎から書き方のステップ、導入事例、ICT活用までをわかりやすく解説します。
目次
保育ドキュメンテーションとは?
保育ドキュメンテーションとは、子どもの日常の姿を写真や言葉で記録し、その背景にある育ちや保育者の意図を「見える化」する取り組みです。単なる出来事の記録ではなく、保育の価値や意味を他者に伝えることを目的としており、近年、注目が高まっています。
この手法は、子ども一人ひとりの主体的な行動を読み取り、その成長や興味関心を具体的に示すことで、保育の専門性を社会と共有する手段として活用されています。また、記録する過程で保育者自身が保育の意図や子どもの育ちを再確認できるため、実践を内省し、学びに変えるツールとしての役割も担っています。
ドキュメンテーションは、保育の“見える化”と“伝える化”を同時に叶える、今後の園運営に欠かせない取り組みのひとつです。
保育日誌やポートフォリオとの違い
保育日誌、ポートフォリオ、保育ドキュメンテーションはすべて子どもの記録ですが、目的や内容、視点が異なります。下記はその違いを簡潔にまとめた比較表です。
| 項目 | 保育日誌 | ポートフォリオ | ドキュメンテーション |
| 主な目的 | 事実の記録、引き継ぎ | 子どもの発達の記録と保存 | 育ちの「意味」を可視化し共有 |
| 対象 | クラス全体 | 個々の子ども | 特定の出来事・育ち・保育者の気づき |
| 記述スタイル | 客観的・業務報告寄り | 子ども主体の記録 | 写真+言葉+解釈、保育者の視点を含む |
| 共有範囲 | 職員内 | 保護者と個別に共有 | 職員・保護者・地域(場合によってはWeb等)にも共有 |
| 活用場面 | 日々の保育管理 | 子どもの発達確認や連絡帳など | 保育の振り返り・園の広報・学びの深化 |
保育日誌は事実の記録、ポートフォリオは成長の記録。これに対し保育ドキュメンテーションは、子どもの行動の背景や意味を保育者が捉え、言語化して共有するものです。記録自体が内省や学びにつながるという点でも、他の記録とは大きく異なります。保護者にとっても、表面の行動ではなく“内面の育ち”を知る手がかりになるのが特徴です。
なお、保育日誌の書き方について知りたい方はこちらを参考にしてください。
注目が高まる背景と保育の現場課題
保育ドキュメンテーションが注目されるようになった背景には、保育の質を「見える形」で伝える必要性が高まっていることがあります。保育所保育指針でも「子どもの育ちを共有・振り返る記録の重要性」が明記されており、保育のプロセスや意図を外部に開かれた形で示すことが求められています。
少子化や保育の多様化が進む中で、園にとって「どんな保育をしているのか」「どんな子どもの姿があるのか」を保護者や地域に伝えることは、信頼の獲得や園選びの判断材料にも直結します。ドキュメンテーションは、こうした**“伝える力”を高めるツール**として非常に有効です。
また、ICTの発展により、以前に比べて写真や動画を使った記録が手軽になったことも追い風となっています。スマートフォンやタブレットを使えば、保育中の一瞬を逃さず記録し、それを文章とともに整理・共有することが可能です。こうした技術の進化が、現場での実践を後押ししています。
一方で、保育の現場では「時間が足りない」「どのように書けばいいか分からない」といった悩みも多く聞かれます。特に人手不足や業務量の多さから、記録が後回しになる、続かないといったケースも少なくありません。
さらに、保育者の間で記録の目的や観点が共有されていないと、「何をどう書くか」がバラバラになり、成果として実感しにくくなることもあります。こうした課題を乗り越えるには、記録の役割を園全体で理解し、チームとして分担・継続する体制づくりが重要です。
出典:厚生労働省「保育所保育指針について」
保育ドキュメンテーションを導入する4つのメリット

保育ドキュメンテーションは、ただの記録ではありません。導入することで保育現場にさまざまなプラスの変化をもたらします。
ここでは主な4つのメリットをご紹介します。
子どもの成長を具体的に実感できる
ドキュメンテーションでは、子どもが何に興味を持ち、どんなプロセスで成長しているかを具体的に記録します。写真や子どもの発言、行動を整理して記すことで、小さな「できた」が積み重なり、発達の過程が視覚化されるのが特徴です。保護者からも「我が子の成長が手に取るように分かる」と好評で、保育の信頼性を高める手段にもなっています。
保育者の専門性向上とやりがいにつながる
記録を通して日々の保育を振り返ることで、保育者自身の気づきや判断の理由を言語化しやすくなります。
これは保育の“暗黙知”を“共有知”に変えるプロセスともいえ、チーム全体の専門性向上につながります。また、自分の保育が可視化されることで、職員のやりがいや達成感も高まり、離職防止にも効果が期待できます。
保護者との信頼関係を深める
ドキュメンテーションを通じて日常の園での様子が伝わることで、保護者は「どのように過ごしているか」を具体的に理解できます。
「ちゃんと見てもらっている」「成長を見守ってくれている」と実感できることは、保護者の安心感と信頼感に直結します。特に育児不安を抱えやすい0~2歳児の家庭では、大きな心理的支えになります。
職員間の対話が増えチーム保育が活性化する
記録を共有することで、他クラスの職員とも子どもの成長や関わりについて話し合う機会が増えます。
これにより、「〇〇ちゃん、こんな一面もあるんだね」といった視点の広がりが生まれ、チーム保育が一層強化されます。職員同士の対話が増えることは、保育の一貫性や安心感にもつながります。
保育ドキュメンテーションの基本的な書き方5ステップ
「何から始めればいいか分からない」という声も多い保育ドキュメンテーション。ここでは、初めての園でも無理なく取り組めるよう、基本の5ステップに沿って書き方のコツを解説します。
ステップ1:記録するテーマや場面を決める
まずは「この瞬間を残したい」と思えるテーマや場面を選ぶことが大切です。たとえば、「友達と協力して遊ぶ」「初めての挑戦」「じっくり遊びに集中している」など、子どもの育ちが表れているシーンを見つけましょう。すべての出来事を記録する必要はありません。大事なのは「なぜこの瞬間を残すのか」という視点を持つことです。
ステップ2:心を動かされた瞬間を写真に撮る
子どもの表情、姿勢、道具の使い方など、言葉では伝えにくい情報を写真で残すことはドキュメンテーションの大きな特徴です。シャッターを切る際には、「この写真から何が伝わるか?」を意識すると記録の質が高まります。プライバシーや肖像権にも配慮しつつ、園内でルールを整えて運用しましょう。
ステップ3:具体的なエピソードと子どもの言葉を記述する
写真だけでなく、その時のエピソードや子どものつぶやき、行動を記述すると、読み手の理解がぐっと深まります。「〇〇くんが“できた!”と笑顔で叫んだ」など、感情の動きが伝わる描写を心がけると、子どもの育ちがよりリアルに伝わります。
ステップ4:保育者の気づきや育ちの視点を加える
「この子はどうしてこの行動をとったのか」「この遊びから何を学んでいるのか」など、保育者の解釈や視点を添えることで、記録が“単なる出来事”から“学びの記録”に変わります。発達心理や保育指針に照らして記述すると、より専門性の高い記録になります。
ステップ5:関係者と共有し次の保育へつなげる
完成した記録は、保護者や職員間で共有しましょう。印刷して掲示する、保護者アプリで配信するなど方法はさまざまです。**記録は伝えてこそ価値が生まれます。**その記録をもとに、次の保育をどう展開するかを考えることで、子どもの育ちを継続的に支えるサイクルが生まれます。
実践園から学ぶ!ドキュメンテーション導入事例集

ドキュメンテーションは、園の規模や職員体制に関係なく取り入れやすい一方、実際の導入方法や成果には個性があります。ここでは、導入事例から見える「成功の鍵」と「つまずきポイント」を紹介します。
成功園の取り組みから見る導入効果
ある私立保育園では、週に1回「育ちの瞬間」をテーマにクラスごとのドキュメンテーションを作成し、園内掲示や保護者連絡ツールで共有しています。写真・言葉・解釈の3点セットで伝えることで、保護者の信頼度が向上し、職員間の会話も活発になりました。
導入の決め手は「記録に正解はない」と共有したこと。職員が完璧を目指しすぎず、まずは“気づいたことをメモする”ところから始めることで、現場の負担感が軽減され、継続につながりました。
うまくいかなかった事例とその原因
一方、ICTを導入しながら定着しなかった園では、「写真を撮るだけ」「誰が記録するか決まっていない」「保護者に共有しない」などの問題が見られました。記録の目的や観点が園全体で共有されていないと、“ただの写真日記”になり、ドキュメンテーション本来の効果が得られません。
改善のためには、「目的の明確化」「業務分担の見直し」「成功体験の蓄積」など、園全体で取り組む仕組みが必要です。
地域・園の規模による導入パターンの違い
小規模園では、保育者一人ひとりの視点が反映されやすく、日々の振り返りが自然と記録につながる傾向があります。一方で、共有の場が限られるため、掲示やアプリを使った保護者への見せ方に工夫が必要です。
大規模園では、職員数が多い分「記録の基準」や「誰が担当するか」のルールを整備することが成功の鍵です。チームごとの分担や、ICTを使った効率的な管理が進んでいます。
現場職員の声に基づいたステップアップ
現場の職員からは「写真に気づきを書くことで、子どもの発達を立体的に見られるようになった」「他の先生と感覚を共有しやすくなった」という声が多く聞かれます。
また、「最初は苦手だったが、短いコメントでも良いと知って気が楽になった」という声もあり、心理的ハードルを下げる工夫も継続のポイントです。
保育ドキュメンテーションを実施する際のポイント

ドキュメンテーションは、ただ書けばいいというものではありません。現場で継続的に取り組むためには、業務として無理なく回せる工夫や、記録の質を高めるための視点が欠かせません。ここでは、実施時の3つのポイントをご紹介します。
ICTシステムを導入して効率化を図る
ドキュメンテーションの継続には、記録作業をいかに省力化できるかが鍵です。紙ベースの運用は手間がかかり、長続きしにくいため、スマホやタブレットを使ったICT化が有効です。
特に、写真撮影から記録共有までをアプリやLINEで完結できるシステムを使えば、業務負担を大幅に減らしつつ、保護者への発信もスムーズになります。
以下に、ICTツールの導入によって改善できるポイントをまとめます。
| 項目 | 紙ベースの場合 | ICT導入後の変化 |
| 写真の扱い | 現像やプリントが必要 | タブレットで即保存・加工 |
| 記録の作成 | 手書き、時間がかかる | 文章入力がスムーズ、テンプレあり |
| 保護者共有 | 掲示または紙で配布 | アプリやLINEで簡単共有 |
| 管理・保存 | 紛失リスクあり | クラウドで一元管理 |
たとえば「保護者連絡アプリ」「クラウド写真アルバム」「共有ドライブ」などを組み合わせることで、現場の負担を軽減しつつ、リアルタイムでの発信が可能になります。
テーマを決めておく
事前に「どんな育ちを記録したいか」「どんな視点で保育を見ているか」を職員間で共有しておくと、記録が偏らずに済みます。たとえば「探究心を育てる場面」「関わりの変化に注目」などのテーマを月ごとに設定しておくと、記録内容に統一感が出て、比較・振り返りもしやすくなります。
テーマは保育指針の5領域や年間保育計画と連動させることで、より実践的な活用が可能になります。
ポイントを絞って素材を集める
「何を残すか迷ってしまう」「たくさん写真を撮りすぎて整理できない」といった悩みを防ぐには、“この写真で何を伝えたいか”を明確にすることが大切です。たとえば、「遊びに集中する表情」や「友達と協力した瞬間」など、育ちが見える1~2枚に絞って記録することで、読む側にも伝わりやすくなります。
また、記録する際は「写真+ひとことコメント」だけでも構いません。まずは続けることを最優先にし、徐々に記録の質を高めていくことが長期的な定着のポイントです。
チポーレではICTを活用した情報発信をサポート
保育ドキュメンテーションが園の強みや保育の質を「見える化」する手段であるならば、それを園外にどう届けるか=“情報発信の導線”も重要なテーマになります。せっかく良い実践があっても、外部に届いていなければ保護者や求職者の心には残りません。
株式会社チポーレでは、そうした保育現場の声に応える形で、ICTを活用した情報発信の支援サービスを提供しています。
たとえば、園の魅力を継続的に発信できる「園児募集らいん君」では、日常のドキュメンテーションの一部を写真付きメッセージとしてLINEで配信可能。ICTで蓄積した保育の記録が、そのまま園のブランディングや保護者への安心感につながる設計です。
また、「採用担当らいん君」では、園の取り組みを写真やメッセージで見せることで、求人票だけでは伝えきれない園の保育観や雰囲気を応募前に伝えることができます。求職者にとっては“働くイメージ”が具体的に持てるため、ミスマッチの防止や応募率アップにもつながる好循環が生まれています。
ドキュメンテーションを「記録」にとどめず、「発信」に活かしたいと考える園にとって、こうしたICT連携は大きな武器になります。園の魅力を“見せる力”へと変えていきましょう。
まとめ
保育ドキュメンテーションは、単なる記録作業ではありません。そこには「保育の質を社会に見せる」「子どもの育ちをチームで支える」「保護者や地域とつながる」ための力が詰まっています。ICTの発展により、これまで以上にその価値を広げやすくなった今こそ、“見える化”から“伝える化”へと、記録のあり方を進化させるタイミングです。
また記録を“発信”へと活かす視点を持つことで、園の魅力を内外に伝える武器になります。情報発信のサポートツールを活用すれば、写真や言葉の積み重ねが、保育への共感や応募・入園の動機に直結します。
これからの保育は、“黙っていても伝わる”時代ではありません。だからこそ、日々の実践をていねいに記録し、ICTの力を借りて社会へと届けていく姿勢が、選ばれる園づくりにつながるのです。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。