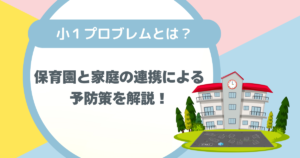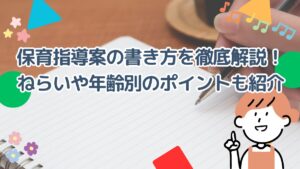【保育施設関係者必見】加配とは?仕事内容や補助金等について詳しく解説!
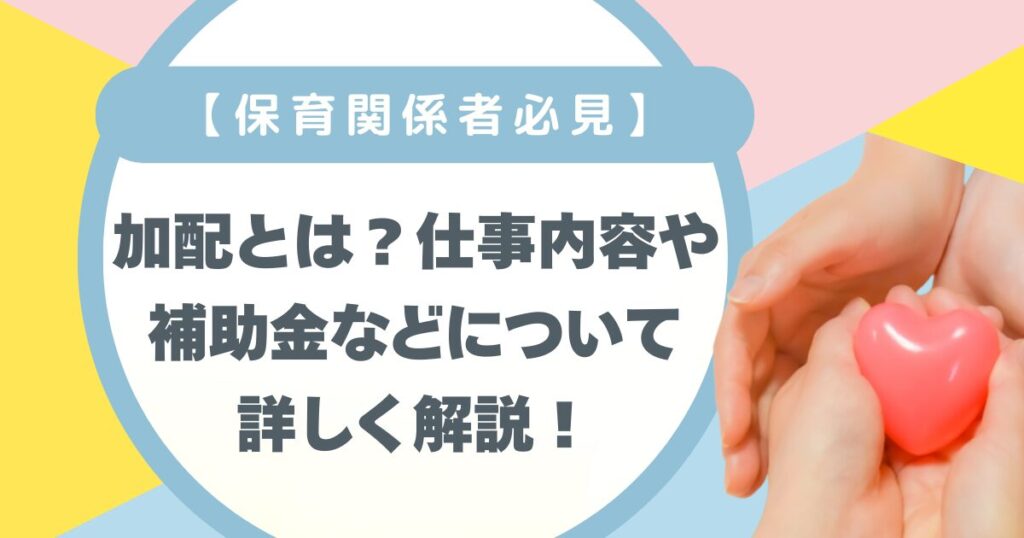
日々の保育の中で、「もっと丁寧な保育をしたい。」そんな思いを抱いたことはありませんか? 子どもたちの特性が多様化するいま、ひとりひとりの「困りごと」に寄り添うための体制づくりが、園にも求められています。
そのひとつの手段が「加配制度」です。保育士を追加で配置し、個別支援を必要とする子どもに寄り添うこの仕組みは、単なる人員補充ではなく、園全体の保育の質を高める大きな支えとなります。この記事では、加配制度の目的や対象、具体的な支援内容、導入のメリットまでをわかりやすく解説します。園運営におけるヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
目次
加配とは?

加配について理解するには、まずその仕組みを正しく知ることが大切です。ここでは「加配の定義」「対象となる子ども」「加配の目的」の3つの観点から解説します。基礎を押さえることで、保育の現場で求められる支援の全体像がより明確になるでしょう。
加配の定義
「加配(かはい)」とは、集団保育の中で特別な支援が必要な子どもに対して、保育士などの職員を通常よりも多く配置する制度です。日常生活や集団活動において困りごとを抱えやすい子どもに対し、より丁寧な保育を行うことで、安心して園生活を送れるように支援します。対象となる子どもは一人ひとり特性が異なるため、必要な支援も個別の配慮が求められます。また加配は園全体の人員に余裕を持たせ、保育の質を高めるための重要な仕組みでもあります。
加配の目的
加配の第一の目的は、特性のある子どもたちが無理なく安心して生活できる環境をつくることです。たとえば感覚が過敏で音に驚きやすい、初めての活動が苦手で混乱しやすい、言葉の理解や表現に時間がかかるといった子どもに対して、加配保育士が近くで支援することで、子どもの気持ちが安定し、園生活に前向きに関わりやすくなります。
対象の子どもだけにとどまらず、まわりの園児にとっても落ち着いた保育環境が保たれるという点で、加配は園全体へ良い影響があります。また、特定の保育士に支援業務が偏りすぎるのを防ぐという意味でも、職員間の負担軽減につながります。
加配の対象となる子ども
加配の対象になるのは、「医師から発達障害などの診断を受けている子ども」だけとは限りません。実際には、園での生活において著しい困難さが見られる場合や、保育士が継続的な支援の必要性を感じている場合などにも、加配が検討されます。
加配の対象となる例
| 区分 | 内容 | 特徴 |
| 障害のある子ども | 医学的な診断が出ているケース | 身体障害・知的障害・精神障害・発達障害など |
| 発達に特性のある子ども | 診断はないが、集団生活での適応が難しい場合。自治体判断で加配対象になることがある | 強いこだわり行動、激しい癇癪など |
| 医療ケアが必要な子ども | 医療行為を伴う支援が必要な場合。安全確保のため専門職が加配されることがある | 喀痰吸引、経管栄養、投薬管理など |
| 外国籍・家庭環境など特別な配慮が必要な子ども | 日本語理解が困難、文化的・言語的ギャップが大きい場合に個別支援が必要 | 外国籍の子ども、家庭環境に配慮が必要な場合 |
加配保育士の支援内容

加配保育士は、特性のある子どもたちが園生活を安心して過ごせるよう、日々さまざまな支援を行っています。ここでは、実際に加配保育士が担っている役割や関わり方について見ていきましょう。
食事や着替えなど身辺自立のサポート
加配保育士は、子ども一人ひとりの発達段階や特性に寄り添いながら、日常生活のサポートを行います。特に食事や着替え、排泄などの「身辺自立」に関する場面では、一般的な声かけや支援だけでは難しい子どもも少なくありません。
たとえば、食事中に集中が続かない子には、一口ごとに「次はこれを食べようね」と優しく促したり、着替えの手順が覚えられない子には、視覚的な手順カードを使って見通しを持たせたりといった工夫が求められます。加配保育士がそばにいることで、「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることができ、自信や自立へとつなげていくことができます。
集団生活への参加や友達との関わりの橋渡し
加配保育士の役割は、個別対応だけにとどまりません。対象の子どもが無理なく集団に加われるよう、クラスの流れの中で橋渡し的なサポートをすることも大切な業務です。
たとえば、全体活動への参加を拒む子どもには、事前に活動内容を伝え、安心できる場所から参加できるよう配慮します。また、友達とのトラブルが起こりやすい場合には、その場で感情を言葉にする手助けをしたり、場面に応じて介入と見守りを切り替えたりする対応が求められます。集団の一員として過ごすことを焦らずサポートし、子ども自身のペースに合わせた関わりを大切にしています。
保護者の不安に寄り添うコミュニケーション
加配保育士は、保護者との信頼関係づくりにも大きな役割を担います。加配対象の子どもを育てる保護者の中には、「他の子と違って申し訳ない」「園に迷惑をかけていないか」といった不安を抱えている方も少なくありません。
そうした気持ちに丁寧に寄り添い、日々の様子や成長を具体的に伝えることで、安心感につながります。加配保育士は、担任保育士と連携しながら保護者対応にも参加し、必要に応じて家庭での様子も共有してもらいながら、支援の方向性をすり合わせていきます。
加配保育士の配置基準について

加配保育士の人数や資格、配置時間などについて、国が全国一律で配置基準を設けているわけではありません。ただし、補助金を申請する場合は、こども家庭庁が示す「標準的な配置」を参考に、障害児2人につき1名の加配を行うなど、一定の条件を満たす必要があります。そのため多くの自治体はこの基準に沿った形で要綱を定めている場合が多く見受けられます。加配保育士を配置する際は、自治体の要項を確認しましょう。
加配配置の流れ
加配保育士の配置は、保護者・園・自治体が連携しながら段階的に進められます。 まず多くの場合、保護者からの申請がきっかけとなります。家庭での育児の困難さや医師・支援機関からの助言を受け、園と協力して診断書や記録を整え、自治体へ申請を行います。自治体の判断を経て加配対象と認定されると、園には正式な受け入れ要請が届き、ここから配置準備が始まります。加配保育士の人材確保はもちろん、子どもの特性に合わせた環境整備も重要です。音や光への過敏さがある場合は落ち着ける空間を用意し、こだわりが強い場合はスケジュール提示など工夫を取り入れます。こうした事前準備を保護者や職員と共有しながら進めることで、スムーズな受け入れと安全な保育体制の実現につながります。
加配設置によるトラブルとその対処法
加配の導入にあたっては、現場でいくつかの課題やトラブルが生じることもあります。たとえば、「加配保育士が急に退職してしまい人員が足りなくなった」「対象児以外の子どもや保護者から“なぜあの子だけ特別扱いなのか”という声が上がった」などです。
こうした事態に備えるには、まずは職員間の情報共有が欠かせません。万一に備えて複数の職員が支援方法を把握しておくことで、突発的な欠員にも柔軟に対応できます。
また、保護者への説明も丁寧に行うことが大切です。加配は“特別扱い”ではなく、“必要な支援を届けるための仕組み”であることを、保護者会などで分かりやすく共有しておくと、園全体での理解と協力が得られやすくなります。
トラブルを未然に防ぐためには、制度をきちんと理解し、保育の方針として全職員が一貫した姿勢で臨むことがなにより重要です。
加配に関する補助金制度について

新しく保育士を雇ったり、環境整備のために備品を購入したり、加配保育士の配置には、人件費や体制整備に一定のお金がかかります。
そのため、国や自治体ではこうした負担を軽減するために「加算」と呼ばれる補助金制度を設けています。これらの加算制度を上手に活用することで、園の負担を最小限に抑えることができますので、必ず押さえておきましょう。
主な補助金の種類(例:障害児加配等加算、配置改善加算)
特に代表的なものが「障害児保育加算」や「療育支援加算」です。
「障害児保育加算(子どものための教育・保育給付費)」は、障害や発達に特性のある子どもを受け入れた場合に、通常の配置基準を超えて保育士を加配することで支給される加算です。原則として「障害児2人につき1人の加配」が想定されており、障害児の人数に応じて加算単価が段階的に設定されています。
(制度の対象)
・障害児を受け入れる特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育を行う事業所を除く。)
(負担率)
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
「療育支援加算(子どものための教育・保育給付費)」は、障害児を受け入れている保育施設で、「主任保育士が療育支援に関わる時間を十分に確保できるようにする」ための補助制度です。障害児への個別対応や療育支援も担う必要がある園では、業務負担が過多になりがちです。そこでこの加算制度では、主任を補佐する保育士(=代替保育士)を配置するための費用を支援してくれます。
(制度の対象)
・障害児を受け入れている保育施設
・主任保育士専任加算の対象であること
(負担率)
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(※)
他にも「保育士等キャリアアップ研修」や「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」と言った、研修や備品購入に充てられる補助金もあります。自治体によって提出する書類のフォーマットも変わるため、必ず自治体の交付要綱を確認しましょう。
参照元:こども家庭庁成育局保育政策課「保育所等における障害のあるこどもの受入れについて」
保育士配置における加算と最低基準の違い
保育士の配置には、「最低限守らなければならない国の配置基準」と、「それを上回る配置に対して支給される加算制度」があります。
たとえば、1歳児に対しては6:1の保育士配置が法律で定められています(これが最低基準)。一方で、障害児や特性のある子どもへのより手厚い支援を行う場合には、国の基準を超えた人員配置が必要です。そうした取り組みに対して支給されるのが「加配の加算」です。
加配保育士は、あくまで「通常配置とは別に配置される支援的な役割」のため、原則として最低基準の職員配置数にはカウントされないことは覚えておきましょう。
補助金を受ける際の注意点とリスク
加算制度は園にとって大きな助けになりますが、申請・維持には注意点もあります。例えば加配保育士が離職してしまったことにより、要件を満たしていない期間があった場合、その期間の加算は対象外となり、場合によっては返還が求められる可能性もあります。
加算の算定対象期間や報告義務も明確に定められており、運営上の負担が増えることも考えられます。そのため、制度内容をよく理解して、書類をそろえたり職員配置を行うことが不可欠です。
補助金を活用して成功している園の事例
都内のある小規模保育園では、障害児加配等加算を活用して個別支援担当の保育士を1名加配。毎日同じ職員が継続して関わることで、子どもの情緒が安定し、生活リズムも整ったとの報告がありました。
また加配保育士が入ることにより、特別な支援が必要な子どもに対しての意見交換や情報共有がより活発に行われるようになり、結果として全体の保育の質向上や、職員間での風通しの良い雰囲気に影響したとの事例もあります。
このように、制度を正しく活用することで、子ども・保護者・職員の三者にとってプラスの成果を得ることができます。
加配導入を成功させるための運営・管理の工夫

職員間の役割分担と情報共有体制
加配の先生をスムーズに配置し、うまく機能させるためには、園の先生同士で「誰が何をするのか」を明確にし、しっかり情報を共有する体制が大切です。せっかく加配がついても、その先生一人に支援を任せきりにしてしまうと、子どもの変化に気づけなかったり、トラブルの対応が遅れてしまったりすることがあります。
たとえば、担任の先生・加配の先生・主任の先生が、週に1回でも「今週の支援の方針」「困っていること」などを一緒に話し合う時間をつくるだけで、チームとしての一体感がぐっと高まります。
また、支援する子ども本人だけでなく、その周りの子どもたちにも影響があるという視点も大事です。加配の先生が入ったことで他の子が不安にならないようにする工夫や、クラス全体のバランスを見ながら保育を進めていく視点も忘れずにいたいですね。
加配対象児の個別支援計画の立て方
加配対象となる子どもには、その子の特性に応じた「個別支援計画」を立てることが推奨されます。形式は自治体により異なりますが、基本的には「何に困っていて、どう支援するか」「支援の目的・ゴール」を整理することが目的です。
現場の先生が日々の中で感じている支援の工夫や関わり方を、言葉として整理し、共有できるようにすることがこの計画の目的です。たとえば、「絵カードで活動の流れを伝える」「1対1で落ち着いた声かけを行う」「刺激の少ない空間にする」など、すぐに実践できる内容を具体的に書くことで、加配の先生だけでなく、クラス全体で一貫した支援がしやすくなります。
保育士への研修・スキルアップ支援
加配を担当する保育士には、発達特性や医療的ケアへの理解、支援技術など、通常保育とは異なる知識やスキルが求められます。そのため、園内外の研修やケース検討会などを通じて、継続的に学び続けることが大切です。
近年では自治体や支援センターによる無料研修も充実してきており、活用しやすくなっています。また、研修後の内容を職員間で共有することで、園全体としての支援スキルが底上げされ、子どもへの関わりに統一感が生まれます。
信頼構築につながる保護者への説明
加配対象の子どもの保護者にとって、園からどのような説明を受けるかは、その後の信頼関係を左右する大きな要素です。「申し訳なさ」「不安」「他の保護者の目が気になる」など、複雑な感情を抱えていることも多いため、丁寧に寄り添う姿勢が求められます。
対応としては、「できていないこと」ではなく、「園で大切にしていること」「できるようになるためにどんな支援を考えているか」を前向きに伝えるのが効果的です。加配制度の仕組みや目的をわかりやすく説明し、同意の上で支援を進めることで、保護者の安心感と協力を得やすくなります。
加配導入による園全体のメリット
加配は一部の子どものためだけの制度ではありません。対象の子どもに手厚い支援が入ることで、クラス全体の落ち着きが増し、担任の動きやすさも高まります。また、保育士同士の連携が強化され、職場内の信頼関係やチーム力も育まれる傾向があります。
さらに、職員が「困っている子に向き合える」という実感を持てることで、仕事のやりがいや専門職としての成長にもつながります。このように、加配は園の保育力を底上げし、働きやすい職場づくりの一環としても重要な役割を果たします。
加配実施園としての魅力を発信し、保護者や求職者にアプローチ

加配を配置しているということは、これから子どもを預ける保育園を探している保護者や、就職先を探している保育士に対しても、発信の仕方次第でアピールになります。せっかく導入するのであれば、園のブランディングに活かしましょう。
未就園児を持つ保護者に向けたアピール内容
加配保育士の配置は、園にとって「誰もが安心して通える保育環境を整えている証」とも言えます。しかし、その取り組みが園外に伝わっていなければ、せっかくの努力が園選びの判断材料として活かされません。
保護者は「どれだけ子どもに目が届く保育か」「困りごとがあったとき、しっかり向き合ってくれるか」といった観点を重視しています。加配制度を通じて、子どもに寄り添った支援を行っていることを丁寧に発信することで、安心感を持ってもらいやすくなります。
加配保育士の採用に向けたアピール内容
加配は「一時的な対応」ではなく、園の大切な方針のひとつとして位置づけることも大切です。パンフレットやホームページに、「子ども一人ひとりに寄り添う保育」や「特性に合わせた支援体制が整っています」といった言葉を載せることで、園がどんな思いで保育に取り組んでいるかが伝わりやすくなります。実際、「一人の子とじっくり向き合いたい」「困っている子の力になりたい」「社会的に意義のある保育がしたい」と考える保育士は一定数おり、そうした方にとって、加配を行っている園はとても魅力的に映ります。発信のしかた次第で、こうした想いを持つ人との出会いにもつながっていきます。
SNS・ホームページでの発信事例
園の取り組みを効果的に伝えるには、SNSや園のホームページなど、保護者や求職者が日常的に触れるメディアを活用することが有効です。具体的には、以下のような発信があげられます。
(投稿の例)
・「今日は●●ちゃんと先生の個別活動を行いました」などの写真付き投稿
加配による支援が、日常の一コマとして自然に行われていることが伝わります。
・「お散歩では歩行が不安な●●くんに加配の先生が付き添い、最後までみんなと一緒に歩けました!」という投稿
一人ひとりの特性に応じた支援が、集団の中でどのように行われているかが伝わります。
・「かけっこでは、歩行が難しいお子さんを先生がそりで引っ張って参加!クラスみんなで応援しました」などのエピソード
特別な支援も“みんなで楽しむ”活動として自然に溶け込んでいる様子が伝わります。
・職員のインタビュー記事やコラム
「加配担当として子どもに寄り添う中で感じた成長」など、実体験を交えた発信は信頼感につながります。
これらの発信を通して、「特別なことではなく、ふだんの保育の一部として加配を行っている」ことが伝わると、保護者や求職者にとっても、園のあたたかさや丁寧な支援の様子がよりわかりやすく、魅力的に感じられるようになります。
園児募集らいん君、採用担当らいん君でもっと効果的にアピール
株式会社チポーレが提供する「園児募集らいん君」「採用担当らいん君」は、LINE公式アカウントを活用して、加配を含めた園の取り組みや魅力を分かりやすく発信できるサービスです。
園児募集らいん君では…
園のLINEから、「発達に特性のあるお子さまも安心して通える環境が整っています」といったメッセージや、加配保育の様子を写真付きで配信できます。保護者にとって、園の支援姿勢が自然と伝わるので、信頼して通わせたいと思ってもらえるきっかけになります。
採用担当らいん君では…
「一人ひとりに寄り添う保育がしたい」と思っている保育士に向けて、加配の取り組みや職員インタビューをLINE公式アカウント上に掲載できます。「理念に共感できた」「理想としている保育が垣間見えた」といった理由から、応募や採用に繋がっています。
さらに、LINEならではのスタンプや返信機能で、興味のある人からすぐにリアクションが届き、そのままチャット上園児獲得や保育士の採用へと繋げることも可能です。
園のアピール内容や配信メッセージの文章は全て株式会社チポーレがサポート。導入や配信もフルサポートなので、忙しい園でも無理なく安心して運用できます。
詳しくは、株式会社チポーレ|サービスサイトをご覧ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。