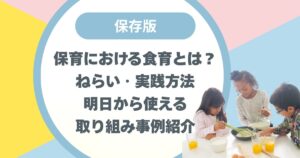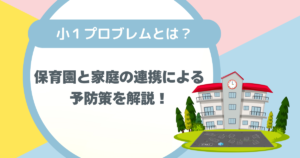保育士の勤務時間のリアル!平均労働時間やシフト制、残業の実態を徹底解説します
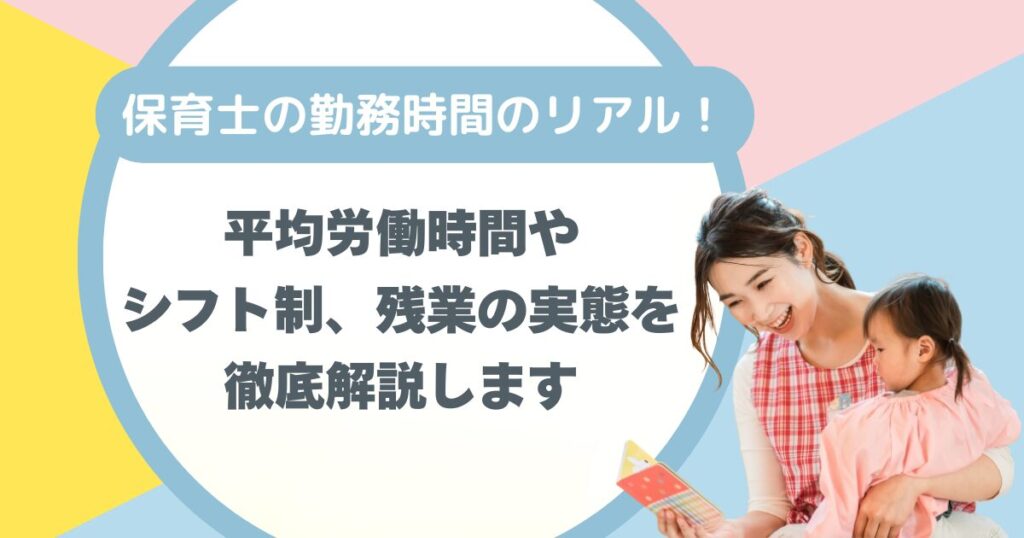
「保育士の仕事は好きだけど、勤務時間が長くて大変そう…」
「これから保育士を目指すけれど、実際はどのくらい働くのだろう?」
保育士という素晴らしい仕事に興味を持つ一方で、勤務時間に関して不安を感じている方は少なくありません。
この記事では、保育士の平均的な勤務時間から、シフト制や残業、休憩のリアルな実態、そして公立・私立、正規・非正規といった働き方の違いまで、あなたの疑問や不安に答える情報を網羅的に解説します。自分に合った働き方を見つけ、保育士として長く輝き続けるためのヒントが満載です。
目次
保育士の勤務時間の基本!法律と平均的なスケジュール
保育士の勤務時間は、法律で定められたルールに基づいていますが、実際の働き方は園によって様々です。まずは、基本となる法律上の決まりと、一般的な保育士の1日の流れを見ていきましょう。
法律で定められている労働時間とは?
日本の労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間、1週40時間」以内と定められています。これは保育士も例外ではなく、多くの保育園ではこの基準に沿って勤務体系が組まれています。しかし、保護者の就労形態の多様化に伴い、早朝保育や延長保育を実施する園が増え、保育士の働き方も柔軟に変化しています。そのため、園によっては1ヶ月または1年単位で労働時間を調整する「変形労働時間制」を導入している場合もあります。
一般的な1日の勤務スケジュール
保育士の1日は、子どもたちの生活リズムに合わせて進みます。開園時間が長い保育園では、主に「早番」「中番」「遅番」のシフト制で対応します。
| 勤務形態 | 勤務時間例 | 主な業務内容 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 開園準備、園内の清掃、早朝保育の受け入れ、保護者からの連絡事項の確認 |
| 中番 | 8:30~17:30 | クラスの主活動、昼食・午睡の補助、保護者対応、保育記録の作成 |
| 遅番 | 10:00~19:00 | 午後の保育、延長保育の対応、お迎えに来る保護者への引き継ぎ、閉園作業 |
上記はあくまで一例であり、園の開園時間や方針によって勤務時間は異なります。
保育士の多様な勤務形態

保育士の働き方は一つではありません。ここでは、代表的な3つの勤務形態「シフト制」「固定時間勤務」「変形労働時間制」について、それぞれの特徴を解説します。
多くの園で採用されるシフト制勤務
シフト制は、多くの保育園で採用されている最も一般的な勤務形態です。 早番・中番・遅番といった異なる時間帯のシフトを、職員が交代で担当します。この制度により、保育園は朝早くから夜遅くまで開園し、保護者の多様なニーズに応えることが可能になるのです。生活リズムが不規則になりやすいという側面はありますが、平日の日中にプライベートな時間を作りやすいというメリットもあります。
規則的な生活が可能な固定時間勤務
固定時間勤務は、毎日決まった時間帯で働くスタイルです。例えば「9時~18時」のように勤務時間が固定されているため、生活リズムを一定に保ちやすく、家庭との両立がしやすいのが大きなメリットです。 ただし、保育園ではシフト制が主流のため、固定時間勤務を導入している園は比較的少ない傾向にあります。パートタイムや派遣保育士の求人では、この働き方が見られることがあります。
繁忙期に対応する変形労働時間制
変形労働時間制は、月単位や年単位で労働時間を調整する制度です。 例えば、運動会や発表会などの行事準備で忙しい月は労働時間を長く設定し、その分、比較的落ち着いている月の労働時間を短くするといった運用が可能です。1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働く日や週があっても、期間内の総労働時間が法定の範囲内に収まっていれば、時間外労働とは見なされません。
保育士の残業はどのくらい?

「保育士はサービス残業や持ち帰り仕事が多い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。ここでは、データと現場の実情から、保育士の残業について掘り下げていきます。
データで見る平均残業時間
厚生労働省の調査によると、保育士の1ヶ月の平均残業時間は約4時間とされています。 この数字だけを見ると、残業は非常に少ないように感じられます。しかし、この統計には、後述する「サービス残業」が含まれていない可能性があり、現場の保育士が感じている負担感とは乖離があるのが実情です。
持ち帰り仕事などサービス残業の現状
保育士の仕事は、子どもたちの保育だけではありません。日誌やおたよりといった書類作成、行事の企画・準備、壁面装飾の制作など、多岐にわたります。これらの業務は、子どもたちが降園した後でないと集中して取り組めないことが多く、結果として勤務時間内に終わらず、サービス残業や自宅への持ち帰り仕事につながりやすいのです。 このような見えない労働時間が、保育士の大きな負担となっているケースは少なくありません。
| 残業になりやすい業務 | 具体的な内容 |
| 書類作成 | 指導計画案、保育日誌、園だより、連絡帳の記入 |
| 行事準備 | 運動会、発表会、季節のイベントの企画、小道具や衣装の作成 |
| 環境整備 | 教室の壁面装飾、おもちゃの修理・清掃 |
| 会議・研修 | 職員会議、クラス会議、外部研修への参加 |
気になる休憩時間の実態
忙しい保育の現場で、休憩はきちんと取れているのでしょうか。法律上の決まりと、現場の実態について解説します。
法律で定められた休憩時間
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと定められています。 したがって、8時間勤務が基本の保育士は、必ず1時間の休憩を取る権利があります。
保育現場で休憩が取りにくい理由
法律で定められているにもかかわらず、保育の現場では十分に休憩が取れていないという声も聞かれます。その主な理由は、子どもたちの午睡(お昼寝)時間中に休憩を取ることが多いものの、その時間も子どもの呼吸チェックや連絡帳の記入、会議などの業務を行わなければならないためです。 人員に余裕がなく、休憩中の職員の代わりに保育に入れる人がいない園では、子どもたちのいる保育室で休憩を取らざるを得ない「ながら休憩」が常態化していることもあります。
【徹底比較】働き方による勤務時間の違い
勤務時間は、園の設立母体や雇用形態によっても大きく異なります。ここでは、様々な角度から勤務時間の違いを比較してみましょう。
公立保育園と私立保育園の勤務体系
公立保育園と私立保育園では、働き方にいくつかの違いがあります。公立保育園で働く保育士は地方公務員となり、勤務時間や休日、福利厚生が条例で明確に定められているため、比較的安定した労働環境が期待できます。一方、私立保育園は園独自の理念や特色を保育に反映させることができ、勤務時間や残業の状況も園の方針によって大きく異なります。
| 項目 | 公立保育園 | 私立保育園 |
| 身分 | 地方公務員 | 会社員・団体職員 |
| 勤務時間 | 7時間45分実働が一般的 | 8時間実働が一般的 |
| 残業 | 比較的少ない傾向 | 園によって差が大きい |
| 休日 | 土日祝休みが多く、カレンダー通り | シフト制で土曜出勤ありの場合が多い |
| 給与 | 年功序列で安定 | 園の給与テーブルによる |
正社員とパート・派遣の働き方
雇用形態によっても、担う責任や勤務時間の柔軟性は変わってきます。正社員は安定した雇用と収入が魅力ですが、クラス担任や行事の主担当など責任ある立場を任されることが多く、残業も発生しやすい傾向にあります。一方、パートや派遣職員は勤務時間や曜日を限定して働けるため、家庭との両立がしやすいのが特徴です。その代わり、給与や賞与、福利厚生の面では正社員と差があることが一般的です。
幼稚園教諭との勤務時間の違い
保育園と同じく未就学児を預かる施設である幼稚園ですが、働き方には違いがあります。幼稚園は文部科学省の管轄で「教育」を行う場とされており、預かり時間は4時間が標準です。そのため、子どもたちが降園した午後の時間を、授業準備や事務作業に充てることができます。また、夏休みなどの長期休暇があるのも大きな特徴です。一方、保育園は厚生労働省の管轄で「福祉」施設とされ、長時間の預かりが基本となるため、保育士はシフト制で一日中子どもの生活を支えます。
保育士の休日について知りたい!

心身ともにリフレッシュし、保育への活力を養うためには、休日の確保が不可欠です。年間休日数や休暇制度について見ていきましょう。
年間休日と一般的な休日パターン
保育士の年間休日は、園によって異なりますが、おおむね105日から125日の範囲です。 日曜日・祝日を定休日とする園が多いため、休日は「日曜+祝日+他1日(平日または土曜)」の週休2日制が基本となります。土曜保育を実施している園では、保育士が交代で出勤し、後日平日に振替休日を取得するケースが一般的です。
有給休暇の取得状況は?
有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、2019年からは年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の取得が義務化されました。 これにより、以前に比べて保育士も有給休暇を取得しやすい環境になりつつあります。しかし、慢性的な人手不足の園では、職員同士で配慮し合い、希望通りに休みが取れない場合もまだあるようです。
産休・育休の取得実績と制度
女性が多い職場であるため、産休・育休制度の充実は非常に重要です。多くの園で制度自体は整っており、取得も可能です。 平成29年の法改正により、保育園に入れないなどの事情がある場合には、育休を最長で子どもが2歳になるまで延長できるようになりました。安心して長く働き続けるためには、制度の有無だけでなく、実際の取得実績や復職後のサポート体制(時短勤務など)が整っているかを確認することが大切です。
無理なく働ける職場を見つけるためのポイント
最後に、心身ともに健康で、やりがいを感じながら長く働き続けられる職場を見つけるための3つのポイントをご紹介します。
残業が少ない保育園の特徴
残業が少ない、あるいは「残業ゼロ」を掲げている保育園には共通する特徴があります。まず、保育士の配置人数に余裕がある点が特徴です。また、事務作業や行事準備の時間を勤務時間内に確保するなどの工夫が見られます。面接や園見学の際に、残業代がきちんと支給されるか、1日の仕事の流れはどのようになっているかなどを具体的に質問してみると良いでしょう。
ICT導入で業務効率化を進める園を選ぶ
近年、保育士の業務負担を軽減するために、ICT(情報通信技術)システムを導入する園が増えています。 例えば、登降園管理システム、保護者への連絡アプリ、指導計画や保育日誌の作成支援ソフトなどです。これらのツールを活用することで、事務作業にかかる時間が大幅に削減され、その分子どもと向き合う時間を増やしたり、残業を減らしたりすることに繋がります。
園の労働環境改善への取り組みを確認する
国も保育士の処遇改善に力を入れています。キャリアアップ研修による手当(処遇改善等加算Ⅱ)や、給与水準を引き上げるための補助金(処遇改善等加算Ⅲ)などの制度が設けられています。 こうした制度を積極的に活用し、職員にきちんと還元している園は、働きやすい環境づくりに熱心であると言えます。求人票や面接で、処遇改善手当の支給実績について確認してみるのも一つの方法です。
| 労働環境改善のチェックポイント | 確認方法 |
| 残業時間と残業代支給 | 面接での質問、口コミサイトの確認 |
| ICTシステムの導入状況 | 園のホームページ、求人票の記載 |
| 処遇改善手当の支給実績 | 面接での質問、求人票の給与内訳 |
| 有給休暇の取得率 | 面接での質問、職員の平均勤続年数 |
まとめ | 保育士として長く働き続けるために
保育士の勤務時間は、法律で1日8時間と定められていますが、シフト制や残業の有無など、実際の働き方は勤務する保育園によって大きく異なります。持ち帰り仕事や休憩が取りにくいといった課題も依然として存在しますが、一方でICT化や国の処遇改善策など、労働環境を良くしようという動きも活発化しています。
この記事で紹介した様々な働き方や、働きやすい職場を見つけるためのポイントを参考に、ご自身のライフスタイルや価値観に合った勤務形態の職場を探してみてください。あなたがいきいきと働ける場所が、きっと見つかるはずです。
また、保育士採用にお悩みの園長先生におすすめしたいのが、「採用担当らいん君」です。LINEを活用した採用支援サービスで、求職者とのやり取りを効率化し、園の魅力をわかりやすく伝えることができます。限られた時間の中でもスムーズに採用活動を進められるため、多くの園で導入が進んでいます。
園にとっても、保育士にとっても安心できる環境づくりの一助として、ぜひ活用をご検討ください。
詳しくは、採用担当らいん君|公式サイトをご覧ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。