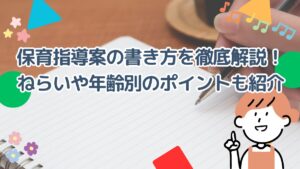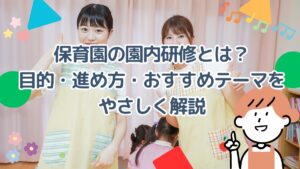保育の目標の立て方を徹底解説!年齢別の文例や保育所保育指針との関連も紹介
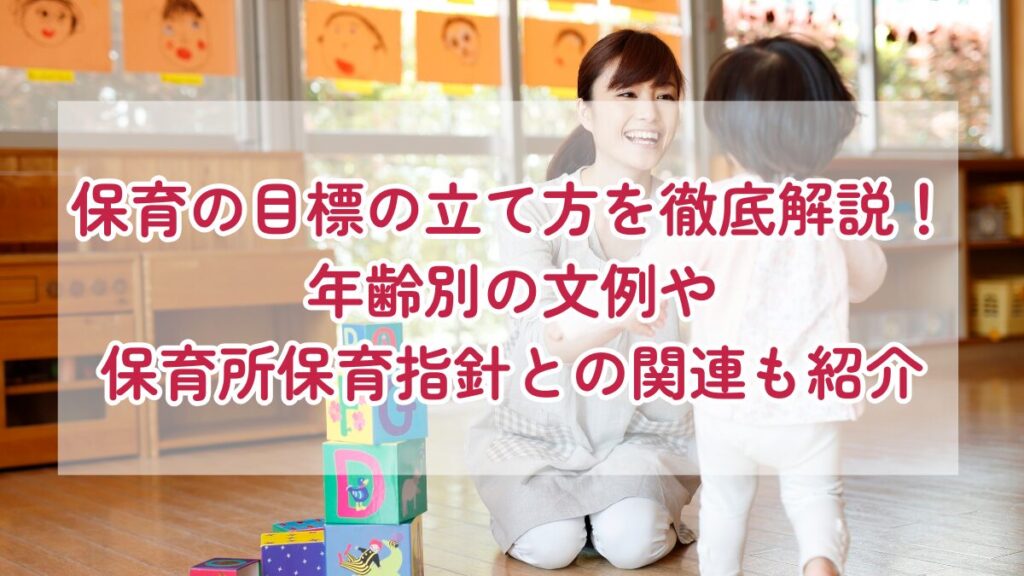
新年度の指導計画を前に、「保育目標って、どうやって立てたらいいんだろう…」と悩んだり、「自分の立てた目標は、本当にこの子たちの成長に合っているのかな?」と不安になったりすることはありませんか。日々の保育に追われる中で、計画書の作成に時間を取られ、頭を悩ませている保育士の方は少なくないはずです。
保育目標は、子どもたちの健やかな成長を支えるための、保育という航海の「羅針盤」のようなものです。明確な目標があることで、日々の保育に一貫性が生まれ、子ども一人ひとりの成長をより深く支えることができます。
この記事では、保育目標の基本的な考え方から、保育の根幹となる「保育所保育指針」との関連、そして明日からすぐに使える年齢別の文例まで、わかりやすく解説していきます。
目次
保育の目標とは?基本的な考え方を解説

保育目標について具体的な計画を立てる前に、まずはその基本的な意味や役割について正しく理解しておくことが大切です。
保育目標は、園の保育理念や方針と深く結びついており、日々の保育の具体的な方向性を示します。
保育における「目標」の定義
保育目標とは、保育園がその保育活動を通して、子どもたちにどのような姿に育ってほしいかを具体的に示したものです。
多くの場合、「〜を養う」「〜を育む」といった言葉で表現され、子どもたちが望ましい未来を築くための力の基礎を培うことを目指します。
例えば、「主体的に行動する子ども」「思いやりのある子ども」といった具体的な子ども像が、目標として掲げられます。この目標は、保育士が日々の保育内容を考えたり、援助の方法を判断したりする際の重要な基盤となるものです。
「保育理念」「保育方針」との違いは?
保育の現場では、「保育理念」「保育方針」「保育目標」という言葉が使われますが、これらの違いを理解することが重要です。この3つは、抽象的なものから具体的なものへと、階層構造になっています。
| 項目 | 概要 | 具体例 |
| 保育理念 | その保育園が最も大切にする、保育における根本的な考え方や哲学。最も上位の概念。 | 「子ども一人ひとりの個性を尊重し、生きる力の基礎を育む」 |
| 保育方針 | 保育理念を実現するために、どのような方向性で保育を進めていくかを示したもの。 | 「見守る保育を実践し、子どもの主体性を大切にする」 |
| 保育目標 | 保育方針に基づき、子どもに育ってほしい具体的な姿を示したもの。日々の保育計画の基礎となる。 | 「自ら考え、行動する子どもを育てる」「友達と協力する楽しさを知る」 |
このように、保育理念という大きな木の幹があり、そこから保育方針という太い枝が伸び、さらに保育目標という具体的な葉が茂るイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
保育の目標と「保育所保育指針」の深い関係
保育目標は、各園が自由に設定できるものではありますが、その根底には国が定めた「保育所保育指針」が存在します。
この指針を理解することは、適切な保育目標を立てる上で不可欠です。
すべての土台となる「保育所保育指針」
「保育所保育指針」は、厚生労働省が定める全国の保育所における保育の質を確保・向上させるためのガイドラインです。
すべての保育園は、この指針に示された内容を踏まえて、保育を実践することが求められています。指針では、保育の目標として「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」ことが掲げられています。
指針で示される「5つの領域」
保育所保育指針では、保育の内容を以下の「5つの領域」として示し、これらを総合的に育むことを目標としています。
| 領域 | ねらい |
| 健康 | 心身の健康に関する領域。元気に過ごし、自分の体を大切にする気持ちを育む。 |
| 人間関係 | 他者との関わりに関する領域。人に対する愛情や信頼感を育て、協調性を養う。 |
| 環境 | 身の回りの環境との関わりに関する領域。様々な環境に好奇心を持って関わり、探求心を育む。 |
| 言葉 | 言葉の育ちに関する領域。言葉への興味や関心を育て、表現する力や聞く力を養う。 |
| 表現 | 感性や表現に関する領域。豊かな感性を持ち、感じたことや考えたことを自分なりに表現する力を育む。 |
【参考】厚生労働省「保育所保育指針解説」を基に作成
これらの5つの領域は互いに密接に関連しており、特定の活動が1つの領域だけに結びつくわけではありません。例えば、友達と一緒にお絵描きをする活動は、「人間関係」「環境」「表現」など複数の領域に関わっています。
指針を具体的な目標に落とし込む方法
保育目標を立てる際は、この5つの領域を意識し、子どもの発達段階に合わせて具体的な言葉に置き換えていく作業が必要です。
例えば、「人間関係」の領域であれば、0歳児には「保育者との安定した関係の中で安心して過ごす」、5歳児には「友達と協力して共通の目的を達成する喜びを味わう」といったように、発達に応じた目標を設定します。
【年齢別】保育の目標の文例集

ここからは、保育所保育指針を踏まえながら、年齢別の保育目標の文例と、目標を立てる際のポイントを解説します。
0歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・特定の保育者と安定した関係を築き、安心して過ごす。
・生理的欲求を適切に満たしてもらい、心地よさを感じる。
・様々な感覚(見る、聞く、触るなど)を通して、身の回りの世界に興味を持つ。
<ポイント>
0歳児は、心身の健康の基礎を培う最も重要な時期です。 特定の保育者との愛着関係を基盤に、安全で安心できる環境で過ごせることが最優先となります。一人ひとりの生活リズムを大切にし、心地よい生活が送れるような目標を設定しましょう。
1歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・保育者との信頼関係のもと、身の回りの環境に興味を持ち、探索活動を楽しむ。
・身振りや片言で、自分の思いを伝えようとする。
・簡単な身の回りのことを自分でしようとする。
<ポイント>
行動範囲が広がり、好奇心が旺盛になる1歳児。 保育者に見守られながら、自分でやってみたいという気持ちを尊重し、探索活動を十分に楽しめるような環境を用意することが大切です。言葉への興味も芽生えるため、応答的な関わりを意識した目標も重要になります。
2歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・保育者や友達との関わりの中で、自分の気持ちを言葉や行動で表現する。
・身の回りの様々なものに興味を持ち、ごっこ遊びなどを楽しむ。
・食事や排泄、着脱など、基本的な生活習慣を自分でやろうとする。
<ポイント>
自我が芽生え、「イヤイヤ期」とも呼ばれる自己主張が見られる時期です。 子どもの「自分でやりたい」という気持ちを大切に受け止め、試行錯誤を温かく見守る姿勢が求められます。言葉でのやり取りが増え、他者への関心も高まるため、簡単なルールのある遊びを取り入れるなど、社会性の芽生えを促す目標を立てましょう。
3歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・保育者や友達と関わる中で、簡単な言葉で自分の気持ちを伝えたり、相手の話を聞いたりする。
・友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わう。
・身の回りの様々な事象に興味や関心を持ち、思考力の芽生えを培う。
<ポイント>
集団生活のルールを理解し始め、友達との関わりが深まる時期です。ごっこ遊びなどを通して、友達とイメージを共有し、一緒に遊ぶ楽しさを経験できるような目標が考えられます。語彙も増え、会話が豊かになるため、言葉で伝え合う楽しさを感じられるような関わりも重要です。
4歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・友達と協力して、共通の目的に向かって遊びを進める楽しさを知る。
・相手の気持ちを考えながら、自分の思いを伝えようとする。
・身近な自然や社会の事象に関心を持ち、探求心を深める。
<ポイント>
仲間意識が芽生え、グループでの活動が増えてきます。友達と話し合ったり、役割を分担したりしながら、一つのことを成し遂げる達成感を味わえるような目標が良いでしょう。葛藤を経験することも増えますが、それも社会性を育む大切な機会と捉え、仲立ちをするような関わりを計画に含めましょう。
5歳児の目標例と立て方のポイント
<文例>
・仲間と協力し、共通の目的を達成するために話し合ったり、工夫したりする。
・相手の気持ちを理解し、思いやりのある行動をとる。
・就学への期待感を持ち、見通しを持って生活する。
<ポイント>
心身ともに大きく成長し、集団の中での自分の役割を理解して行動できるようになります。就学を意識し、生活習慣の自立や、話を聞く姿勢、最後までやり遂げる力などを育むことを目標に含めると良いでしょう。園生活の集大成として、仲間との協同性を深め、自信と期待を持って小学校へ進めるような目標を設定します。
保育目標を立てるための具体的な3つのステップ
では、実際に保育目標はどのような手順で立てればよいのでしょうか。ここでは、具体的な3つのステップに分けて解説します。
ステップ1:子どもの実態と発達過程を把握する
まずは、目の前にいる子どもたちの姿をよく観察することから始めます。
クラス全体としての発達の傾向や特徴、そして一人ひとりの興味や関心、得意なこと、苦手なことなどを丁寧に把握します。前の年度の記録や保護者からの情報も参考にしながら、子どもの「今」の姿を多角的に捉えることが重要です。
ステップ2:長期的な視点で育みたい姿を明確にする
次に、ステップ1で把握した子どもの実態を踏まえ、「この1年間で、子どもたちにどんな姿に育ってほしいか」という長期的な見通しを立てます。
これは「年間目標」にあたります。保育所保育指針の5つの領域を参考にしながら、1年後の育ってほしい姿を具体的にイメージします。この年間目標が、月案や週案といった短期的な目標を立てる際の基盤となります。
ステップ3:具体的な言葉で表現する
最後に、ステップ2で明確にした育みたい姿を、具体的な言葉で目標として記述します。この時、「楽しむ」「頑張る」といった曖昧な言葉ではなく、「〜ができるようになる」「〜しようとする」など、保育士が評価しやすく、誰が読んでも保育のねらいが伝わるような具体的な動詞を用いて表現することがポイントです。
保育目標を立てる際に押さえるべき注意点

効果的な保育目標を立てるためには、いくつか注意すべき点があります。以下のポイントを押さえて、より質の高い計画を作成しましょう。
抽象的な表現は避ける
「思いやりの心を育む」という目標は立派ですが、これだけでは具体的にどのような保育をすればよいのか分かりにくいです。
これを「友達が困っている時に『どうしたの?』と声をかける」「使っているおもちゃを『かして』『いいよ』とやり取りする」のように、子どもの具体的な行動レベルまで落とし込んで考えることが大切です。具体的な行動目標があることで、日々の保育での援助のポイントが明確になります。
子どもの発達とかけ離れていないか確認する
保育士の「こうあってほしい」という願いが先行し、子どもの実際の発達段階とかけ離れた高すぎる目標を設定してしまうことがあります。
目標は、子どもたちが少し頑張れば達成できる「一歩先」の内容であることが理想です。常に子どもの実態に立ち返り、無理のない目標になっているかを確認する視点を持ちましょう。
実現可能な計画であるかを考慮する
立てた目標が、園の環境(園庭の広さ、備品など)や保育士の配置人数などを考慮した上で、実現可能なものであるかどうかも重要です。理想を掲げることは大切ですが、日々の保育の中で実践できなければ意味がありません。園の状況に合わせて、計画を柔軟に調整する姿勢も必要です。
まとめ
保育目標は、子どもたちの成長を支えるための設計図であり、質の高い保育を実践するための道しるべです。保育所保育指針を土台としながら、目の前の子どもたちの姿をしっかりと見つめ、一人ひとりの発達に合った具体的な目標を立てることが重要となります。この記事で紹介したポイントや文例を参考に、自信を持って指導計画の作成に取り組んでください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。