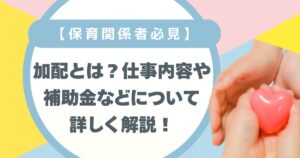保育指導案の書き方を徹底解説!ねらいや年齢別のポイントも紹介
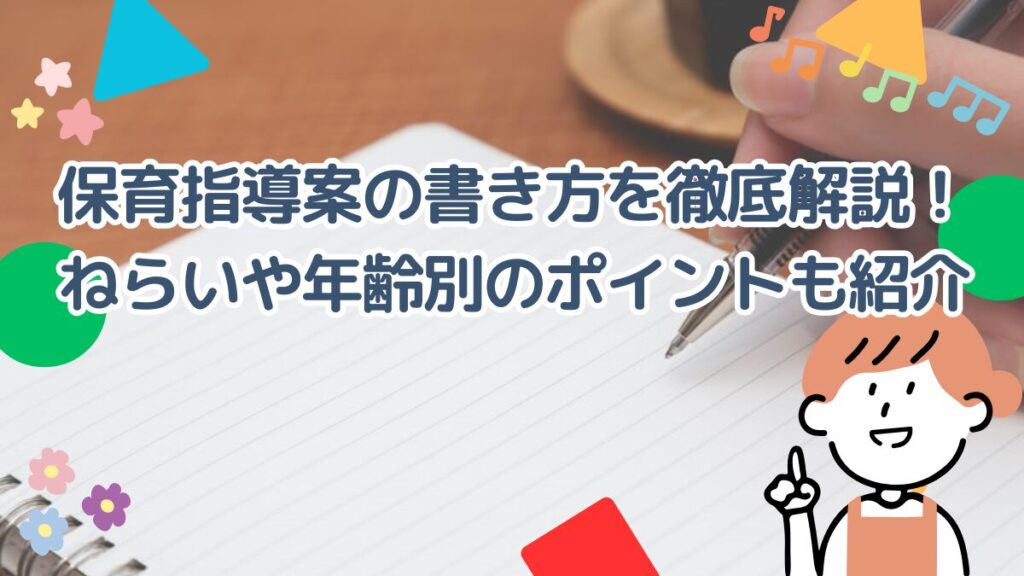
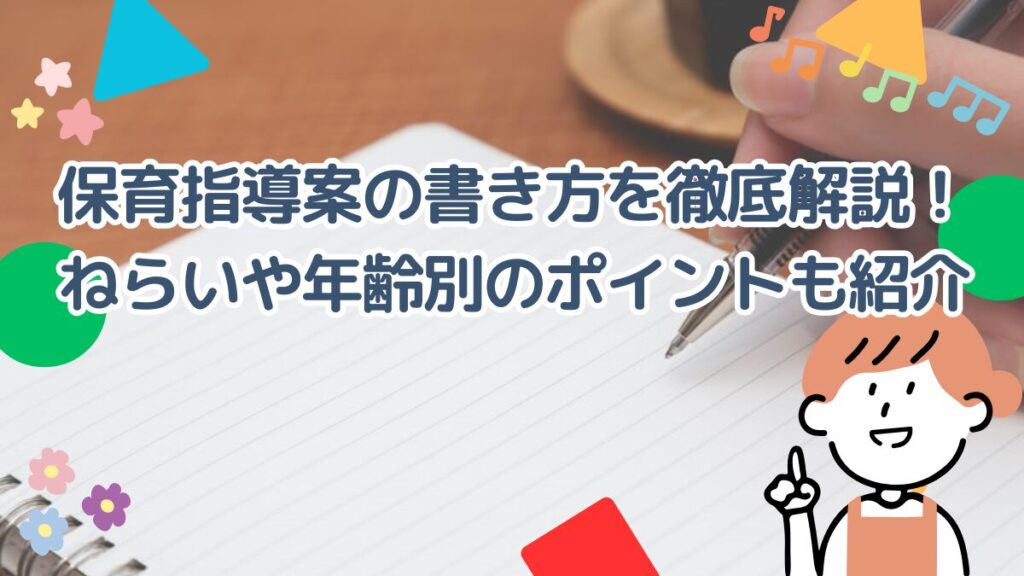
保育士にとって重要な業務の一つである「保育指導案」の作成。しかし、毎日の忙しい業務の中で、どのように書けば良いか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、指導案の基本的な書き方から、子どもの成長に合わせた年齢別のポイント、さらには作成をスムーズに進めるためのコツまで、文例を交えながら詳しく解説します。
保育指導案とは?
保育指導案は、単なる計画書ではありません。
子どもたちの健やかな成長を支えるための、保育の「設計図」とも言える非常に重要な書類です。日々の保育を計画的に進め、保育士間で目標を共有するために作成されます。
子どもの成長を支える保育の設計図
保育指導案は、子どもたちが充実した園生活を送り、健やかに成長するために不可欠です。
指導案を作成することで、保育士は子どもの発達段階に合わせた目標を明確にし、その目標を達成するための具体的な活動を計画することができます。
また、計画に基づいて保育を実践し、その結果を振り返ることで、保育の質を継続的に改善していくことにも繋がります。
なぜ指導案を作成する必要があるのか?
指導案の作成は、厚生労働省が定める「保育所保育指針」においても求められています。
指導案があることで、担当の保育士だけでなく、他の職員とも子どもの育ちに関する共通認識を持つことが可能です。
これにより、クラス全体、さらには園全体として一貫性のある保育を提供できるようになります。
万が一、担任の保育士が不在になった場合でも、他の保育士がスムーズに対応できるという利点もあります。
保育指導案の主な種類と役割
保育指導案には、計画する期間に応じて「年間指導案」「月案」「週案」「日案」の4つの種類があります。 それぞれが連動し合うことで、長期的かつ短期的な視点を持った、質の高い保育が実現します。
| 種類 | 期間 | 主な役割と内容 |
| 年間指導案 | 1年間 | 園の保育目標に基づき、その年度の子どもたちの育ちの最終的な姿を想定し、季節ごとの行事や活動の大枠を計画します。 |
| 月案(月間指導案) | 1ヶ月 | 年間指導案に基づき、その月のねらいや行事、季節感を踏まえた具体的な活動内容を計画します。子どもたちの発達状況に応じて柔軟に調整します。 |
| 週案(週間指導案) | 1週間 | 月案をさらに具体化し、1週間の天候や子どもたちの興味関心を考慮しながら、日々の活動の流れを計画します。 |
| 日案(日間指導案) | 1日 | 1日の保育の具体的な流れを時系列で記したものです。 活動内容だけでなく、個々の子どもへの配慮や声かけなども詳細に計画します。 |
長期的な視点で計画する「年間指導案」
年間指導案は、1年という長いスパンで子どもの成長を見通すための計画です。
4月の時点での子どもの姿と、翌年3月にどのような姿に成長していてほしいかを具体的に描き、その達成に向けた大まかな道筋を示します。主に学年リーダーや主任保育士が中心となって作成することが多いです。
季節や行事を意識した「月案」
月案は、年間計画を基にして、より具体的な1ヶ月の保育計画を立てるものです。
その月の季節や祝日、園の行事などを考慮し、子どもたちが季節の変化を感じられるような活動を取り入れます。子どもたちの興味や発達のペースに合わせて、柔軟に計画を調整することが大切です。
毎日の保育の軸となる「週案」
週案は、月案の内容をさらに細分化し、1週間の活動を計画するものです。
天気予報や子どもたちのその時々のコンディションを考慮に入れながら、日々の活動がスムーズに連動するように組み立てます。この段階で、活動に必要な準備物なども具体的にリストアップしていきます。
1日の流れを具体的に記す「日案」
日案は、その日1日の保育を時系列で詳細に記述する指導案です。
登園から降園まで、どのような活動をどの時間帯に行うのかを具体的に計画します。活動内容だけでなく、子どもの行動を予測し、それに対して保育士がどのように関わるかといった、細やかな配慮まで盛り込むことが特徴です。
指導案の基本的な書き方と5つの構成要素

指導案は園によってフォーマットが異なりますが、「ねらい」「内容」「環境構成」「予想される子どもの姿」「保育者の援助」の5つの項目は、ほとんどの場合で共通しています。
これらは相互に関連しており、一貫性を持たせることが重要です。
保育の目標となる「ねらい」を設定する
「ねらい」は、その活動を通して子どもにどのような経験をさせ、どのように成長してほしいかという具体的な目標を示す、指導案の核となる部分です。「〜できるようになる」「〜を楽しむ」といった形で記述します。
この「ねらい」を明確に設定することで、その後の活動内容や必要な援助が具体的になります。
ねらいを達成するための「内容(活動)」を考える
「内容」には、「ねらい」を達成するために行う具体的な活動を記述します。
例えば、「戸外で思いきり体を動かす」というねらいであれば、「鬼ごっこをする」「固定遊具で遊ぶ」といった具体的な活動が考えられます。子どもたちが主体的に楽しめるような、魅力的な活動を計画することが大切です。
子どもの主体性を引き出す「環境構成」を整える
「環境構成」とは、子どもたちが活動にスムーズに取り組めるように、物的・空間的な環境をどのように整えるかを記述する項目です。使用する遊具やおもちゃの配置、活動スペースの確保、安全への配慮などが含まれます。
子どもが自ら「やってみたい」と思えるような、興味を引く環境を作ることが求められます。
活動中の「子どもの姿」を具体的に予想する
ここでは、計画した活動の中で、子どもたちがどのような言動や反応を見せるかを具体的に予測して記述します。 例えば、「友達と協力して遊ぶ姿」「試行錯誤しながら課題に取り組む姿」などを具体的にイメージしましょう。子どもの姿を予測しておくことで、保育士は落ち着いて対応することができます。
子どもに寄り添う「保育者の援助」を記述する
「保育者の援助」には、子どもの活動をサポートするために保育士がどのような関わり方をするのかを記述します。
具体的には、適切な声かけ、活動への導入、見守り、安全管理などが挙げられます。子どもの自主性を尊重しつつ、必要な場面で的確なサポートができるよう、具体的な援助の方法を考えておきましょう。
【年齢別】指導案作成のポイント
子どもの発達段階は年齢によって大きく異なるため、指導案もそれぞれの年齢に合わせた内容にする必要があります。 ここでは、年齢ごとの発達の特徴と、指導案作成のポイントを解説します。
| 年齢 | 発達の特徴 | 指導案作成のポイント |
| 0歳児 | 特定の大人との愛着関係を基盤に、心身が発達する時期。 | スキンシップを重視し、授乳やおむつ交換などを通して、安心できる環境で基本的な生活習慣の基礎を築くことをねらいとします。 |
| 1-2歳児 | 歩行が安定し、言葉が増え、自我が芽生える時期。 | 子どもの「自分でやりたい」という気持ちを尊重し、探索活動が十分にできるよう、安全な環境構成を工夫します。 |
| 3歳児 | ごっこ遊びが豊かになり、友達との関わりが増える時期。 | 簡単なルールのある集団遊びを取り入れ、友達と関わる楽しさが味わえるような活動を計画します。 |
| 4歳児 | 仲間意識が芽生え、共通の目的を持って遊ぶようになる時期。 | 子どもたち自身でルールを決めたり、役割分担したりする協同的な活動を取り入れ、社会性や探求心を育みます。 |
| 5歳児 | 就学に向けて、見通しを持って行動できるようになる時期。 | 文字や数への興味を引き出す活動や、グループでの話し合いなど、就学後にもつながる主体的な学びの機会を計画します。 |
0歳児:愛着形成と基本的な生活習慣の確立
0歳児の保育では、特定の保育士との間に愛着関係を築き、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが最も重要です。
指導案では、授乳やおむつ交換、着替えといった一つひとつの生活場面を丁寧に行い、子どもとの信頼関係を深めるための具体的な関わり方を記述します。
1〜2歳児:探索活動と自我の芽生えを支える
行動範囲が広がり、「イヤイヤ期」と呼ばれる自我の芽生えが見られる1〜2歳児。子どもの「自分でやりたい」という気持ちを尊重することが大切です。
指導案には、子どもが興味を持ったことに存分に取り組めるような遊びのコーナーを設けたり、子どもの気持ちを受け止める声かけを具体的に記したりします。
3歳児:集団生活の基礎とごっこ遊びの発展
友達への関心が高まり、集団での活動が増えてくる3歳児。ごっこ遊びなどを通して、他者とイメージを共有する楽しさを経験させることが大切です。
簡単なルールのある集団遊びを計画し、順番を守る、貸し借りする、といった社会性の基礎を育むための援助を考えます。
4歳児:協同性と探究心を育む
仲間意識が強まり、友達と協力して共通の目的に向かうことができるようになる4歳児。
指導案には、子どもたちがグループで話し合い、役割を分担しながら進めるようなプロジェクト型の活動を取り入れると良いでしょう。子どもの探究心を刺激するような素材やテーマを用意することがポイントです。
5歳児:就学を見据えた主体的な活動の展開
思考力や社会性が大きく発達し、就学への期待が高まる5歳児。当番活動や行事の係など、責任のある役割を任せることで、自信と自立心を育みます。
文字や数に親しむ遊びを取り入れたり、自分たちで遊びの計画を立てて実行したりするなど、主体性を尊重した活動を計画します。
指導案作成をスムーズに進める3つのコツ

質の高い指導案を効率的に作成するためには、いくつかのコツがあります。日々の業務に追われる中でも実践できる3つのポイントを紹介します。
「保育所保育指針」に立ち返る
指導案の書き方に迷ったときは、「保育所保育指針」やその解説書を読み返すことがおすすめです。
ここには、保育の基本的な考え方や、各年齢で育みたい「ねらい」や「内容」が示されています。指導案の方向性を見失ったときの、信頼できる道しるべとなります。
昨年度の指導案を参考に一貫性を持たせる
前年度までの指導案は、質の高い保育の財産です。 過去の指導案を確認することで、その園が大切にしてきた保育の流れを理解し、一貫性のある計画を立てることができます。
もちろん、そのまま流用するのではなく、今年度の子どもたちの実態に合わせて内容を調整することが重要です。
日々の子どもの姿を丁寧に観察する
最も大切なのは、日々の保育の中で子どもたちの姿をよく観察することです。
子どもが今何に興味を持っているのか、どのような遊びに夢中になっているのか、友達とどう関わっているのか。そうした観察から得られる情報こそが、子どもの発達に即した指導案を作成するための最も重要なヒントになります。
まとめ
保育指導案の作成は、保育士にとって大きな責任が伴う重要な仕事です。
しかし、完璧を目指しすぎて負担に感じる必要はありません。大切なのは、目の前の子どもたちの姿を思い浮かべ、「どうしたらこの子たちがもっと楽しく、健やかに成長できるか」を考えることです。 この記事で紹介したポイントを参考に、自信を持って指導案作成に取り組んでください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。