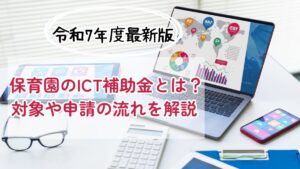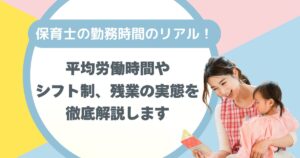保育における食育とは?ねらい・実践方法・明日から使える取り組み事例紹介
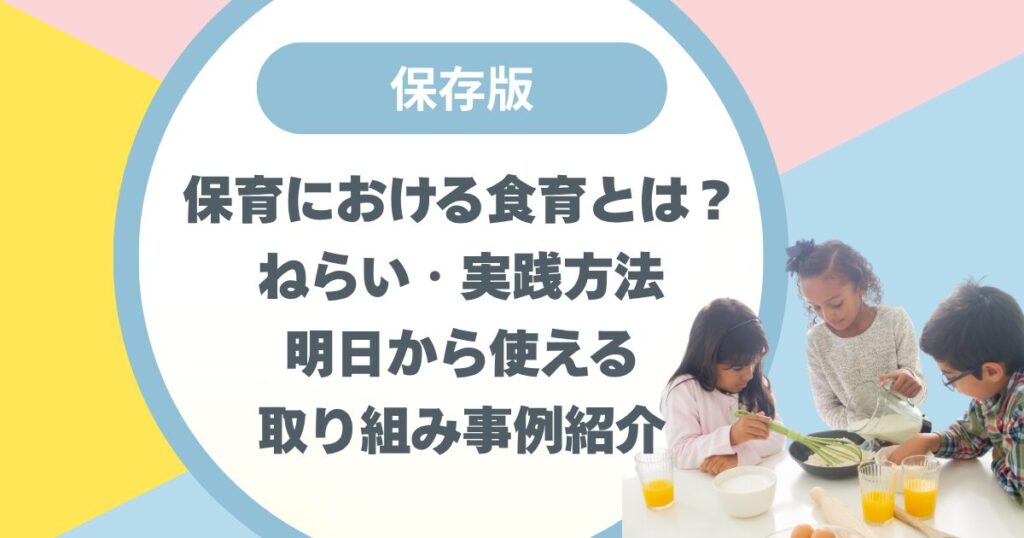
保育園の食育は園児の健やかな成長を支え、保護者から「ここに預けたい」と思われる園づくりにも貢献します。本記事では園長先生や保育士の方向けに、食育を園経営の強みに変える具体策と、すぐ実践できる取り組み事例をご紹介します。
目次
食育とは?
保育園での「食育」は、単なる食事の時間にとどまりません。子どもたちの心と体の成長を支え、人との関わりや命の尊さを学ぶ大切な教育活動です。この章では、食育の基本となる考え方や、保育の中で果たす役割、園児や保護者にとってのメリットについて分かりやすくご紹介します。
食育基本法とは?食育の定義と基本理念について
「食育基本法」は、子どもから大人までが生涯を通じて、健全な食生活を送れるよう支援するための法律です。2005年に制定されました。この法律では、食育を「生きる上での基本」と位置づけています。つまり、食べることを通じて命の大切さや健康の意義を学ぶことが、食育の目的です。
保育園では、乳幼児期の子どもに対して、食事の大切さや楽しさを体験を通して伝えることが、重要な役割となります。食べることに関心をもち、自ら食べようとする気持ちを育むことが、保育現場での食育の第一歩です。
保育現場における食育の役割
乳幼児期は、心も体も大きく育つ大切な時期です。食育はその土台を支えるものです。保育園では、子どもが「食べることって楽しい」と感じられるよう、安心した環境の中で、日々の食事を提供する必要があります。
また、偏食や少食など、子ども一人ひとりの課題に寄り添いながら、楽しい食事の時間を共有することも、保育士の重要な役目です。
日々の保育の中で、子どもたちが自然と「食べることの大切さ」を感じられるような関わりを大切にしましょう。
食育のメリット
食育には、子どもたちの成長を支えるさまざまな効果があります。まず、規則正しい生活習慣が身につきます。決まった時間に食事をとることで、体内リズムが整い、健康的な生活の基礎がつくられます。
また、保育者や友だちと一緒に食べることで、協調性や感謝の気持ちが育まれます。食材や調理に興味をもつことで、自然や文化への関心も広がります。こうした体験は、保護者から見ても魅力的な保育の一環となり、園への信頼感にもつながります。
食育における5領域と園の魅力づくり

食育は、子どもの心と体を育てる多面的な学びです。文部科学省の幼児教育要領では、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域を基本に、食を通じた成長を促すことが求められています。
以下では、各領域ごとに保育園でできる食育の視点と、園の魅力づくりへのつなげ方をご紹介します。
健康|心身の成長と生活習慣の形成
「朝ごはんをしっかり食べる」「よく噛む」「苦手なものも一口は挑戦する」など、食を通じて健康的な生活習慣を身につけます。
このような日常の積み重ねが、子どもたちの体力や集中力を育て、健やかな成長を支えます。また、保護者にも「園での食習慣」を伝えることで、家庭との連携が深まり、信頼関係の構築にもつながります。
人間関係|食を通じた協調性・感謝の心の育成
「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや、配膳・片付けの手伝いを通じて、協調性や思いやりが育ちます。
友だちと一緒に食事をすることで、楽しい会話が生まれ、社会性も自然と身につきます。また、調理員さんや農家の方など、食に関わる人への感謝の気持ちを育む機会にもなります。
環境|食材や自然に対する興味と理解を深める
野菜の栽培や収穫体験、旬の食材に触れる活動を通じて、子どもたちは食材が育つ過程や自然の恵みに興味を持つようになります。
季節の移ろいや地域の風土にも目を向けるきっかけとなり、自然を大切にする心が育ちます。園庭がない園でも、プランターや壁面掲示など工夫次第で取り組むことが可能です。
言葉|食に関する語彙を増やし表現力を育む
「やわらかい」「シャキシャキ」「あまい」「にがい」など、味や食感を言葉で表すことで、語彙力が育ちます。
食事中の会話や絵本の読み聞かせを通じて、自然と表現力や聞く力が身についていきます。保育者が子どもの発言を丁寧に受け止め、言葉を広げてあげることが大切です。
表現|食体験を通じて感性や創造性を広げる
食材の色や形を観察したり、料理をテーマにした絵を描いたりする活動は、子どもたちの感性や想像力を豊かにします。
また、「おいしかった!」「楽しかった!」という気持ちを表現することで、自己肯定感の育成にもつながります。味覚だけでなく、五感を使った体験が、子どもたちの表現力を伸ばします。
食育を続けるための仕組みづくり
食育は一度きりではなく、継続的に取り組むことが大切です。
年間計画や月ごとのテーマを設けることで、職員間での共有がしやすくなり、取り組みに一貫性が生まれます。また、行事や季節に合わせた活動を取り入れることで、子どもたちの関心も高まりやすくなります。
保育士と栄養士の連携で深まる食育の質
食育の充実には、保育士と栄養士の連携が欠かせません。
たとえば、給食のメニューに合わせて食材の紹介をしたり、苦手な食材の克服を一緒に考えたりすることで、保育と給食がつながった学びになります。調理現場との日常的な情報共有が、より実践的で効果的な食育につながります。
保護者に伝える工夫と参加イベントの設計(おたより・交流会など)
保護者に園の食育の様子を伝えることも大切です。
毎月の「食だより」や「給食だより」に写真や子どもの声を載せると、家庭でも話題にしやすくなります。また、保護者参加型のクッキングイベントや、地元野菜を使った試食会なども、園への信頼感を高める機会となります。
食育を通じた園のブランドイメージアップ
「食べることを大切にしている園」は、保護者にとって魅力的な選択肢です。
食育に力を入れることは、単に子どもの成長支援にとどまらず、「この園に預けたい」と思われる大きな理由になります。園内掲示やSNSなどを活用し、日々の取り組みを丁寧に発信することも、園のブランディングに役立ちます。
食育の計画の立て方

食育の効果を最大限に高めるには、計画的な取り組みが欠かせません。ここでは、保育園での食育を継続的に実践するための環境づくりや、食材選びのポイントをご紹介します。
食育に必要な環境の整え方
まず大切なのは、子どもが安心して食事を楽しめる環境を整えることです。
机や椅子の高さを子どもに合わせたり、落ち着いて食べられる空間を意識したりするだけで、食への関心は大きく変わります。また、調理室の見える化や、食材の展示コーナーなどを設けることで、食への興味を自然に引き出せます。
職員間で食育の方針や目的を共有しておくことも、継続的な取り組みに必要不可欠です。年間計画に食育の目標や行事を組み込むことで、無理なく日常に落とし込めるようになります。
食材の選び方と調理方法
食育の効果を高めるには、食材選びにも工夫が必要です。
旬の野菜や果物を取り入れることで、季節を感じられる献立になります。地域の食材を使うと、地元への関心や郷土文化への理解も深まります。
調理方法は、子どもが食べやすく、素材の味を感じられることが大切です。やわらかく煮る、うす味にするなど、子どもの年齢や発達に合わせた工夫をしましょう。また、調理体験を取り入れる際は、切る・ちぎる・混ぜるなど、年齢に応じた工程を選ぶことで、安全に楽しく取り組むことができます。
【年齢別】子どもの成長段階に合わせた食育の目標と実践例
子どもたちは年齢や発達段階によって、食に対する興味や体の準備が異なります。ここでは、月齢ごとのねらいと、保育園でできる具体的な食育の実践例をご紹介します。
6ヶ月未満児:安全な食べ始めのサポートと味覚形成
離乳食の開始は、子どもにとって「食べることの第一歩」です。
この時期は、食べ物の形状や温度、味の違いにゆっくりと慣れていく時期です。無理に食べさせず、「食べる準備を整えること」を第一に考えましょう。保育園では、家庭と連携して離乳の進み具合を把握し、安全に食べられる環境を整えることが大切です。初めての食材には注意し、保護者と情報を共有しながら慎重に進めましょう。
6ヶ月~1歳3ヶ月未満児:食への興味を育てる体験づくり
離乳食が進むと、自分の手で食べ物をつかんだり、口に運んだりする姿が見られるようになります。
この時期の子どもは「自分で食べたい」という意欲が芽生えるため、手づかみ食べやスプーンの練習を積極的に取り入れることが効果的です。
また、食材に触れる・においをかぐ・見た目を楽しむなど、五感を使った体験を通して、食への興味を引き出しましょう。
2歳未満児:自己表現と食習慣の基礎づくり
自我が育つこの時期は、好き嫌いがはっきりしてくる一方で、自分なりの「こだわり」も表れます。
「自分で食べたい」「この順番で食べたい」などの行動を、否定せず見守る姿勢が大切です。保育士は、子どもの気持ちを尊重しながら、楽しく食事に向き合えるよう声かけを工夫しましょう。食事の流れ(あいさつ→配膳→食べる→片付け)を丁寧に繰り返すことで、生活習慣の基礎が身につきます。
2歳児:社会性を育む食事のマナーとコミュニケーション
2歳になると、周囲との関わりの中で食事を楽しむ力が育ってきます。
「みんなと一緒に食べる」「順番を守る」「感謝の気持ちを伝える」といった社会性が少しずつ育まれます。この時期は、給食の配膳や配膳後のあいさつを一緒に行うことで、役割意識や協調性を育てることができます。保育者の模範的な姿勢を見せることが、子どもたちの行動に大きな影響を与えます。
3歳児以上:主体性を促す食育活動と感謝の心の育成
3歳以降の子どもたちは、食事を単なる行為ではなく、「活動」としてとらえる力が育ちます。
食材に関心を持ったり、調理活動に意欲的に取り組んだりする姿が見られるようになります。野菜の皮むきやサンドイッチ作りなど、年齢に応じた簡単な調理体験を取り入れると、主体性が高まります。また、給食を支えてくれる人たちへの「ありがとう」の気持ちを育てることで、命の大切さを感じる感性も養われます。
明日からできる!園での食育実践5つのアイデア

特別な設備がなくても、日常保育の中で手軽に食育を取り入れることは可能です。ここでは、どんな保育園でも実践しやすい5つの食育アイデアをご紹介します。
園庭がなくてもできる◎プランターで栽培体験
園庭がなくても、ベランダや室内の一角で栽培体験はできます。
プランターにミニトマトやラディッシュなど、育てやすい野菜を植えることで、子どもたちは食べ物が育つ過程に興味を持ちます。「大きくなったね」「赤くなってきたよ」といった日々の変化が、観察力や関心を育てます。収穫した野菜を給食で食べると、達成感とともに「食べること」への理解が深まります。
年齢別のかんたん調理体験
調理体験は、年齢に合わせて難易度を変えることで、安全かつ楽しく行えます。
0~1歳児には、保育者が調理する様子を見せる「見せる食育」を。
2歳児には、ちぎる・混ぜるといった簡単な工程を。
3歳以上には、サンドイッチ作りやおにぎりに挑戦してもらうと、自分で作った達成感から苦手な食材も食べやすくなります。調理活動は衛生面にも配慮しながら、少人数制や個別対応で行うのがポイントです。
食にまつわる絵本の読み聞かせ
「たべもの」がテーマの絵本を取り入れることで、子どもたちは楽しみながら食への関心を高められます。
食材の由来や季節感、食べるときの気持ちなどを描いた絵本は、食育の導入に最適です。
たとえば、野菜が土の中から顔を出すしかけが楽しい『やさいさん』(tupera tupera/福音館書店)、本物そっくりの果物に「どうぞ」と声かけたくなる『くだもの』(平山和子/福音館書店)、お米をとぎ、おにぎりをにぎる過程を丁寧に描いた『おにぎり』(小西英子/福音館書店)などは、保育現場でも人気です。
読み聞かせの後に、絵本に出てきた食材を実際に触れたり、給食に出したりすると、より記憶に残る体験になります。図書コーナーに食育絵本を常設すると、保護者の関心も高まり、家庭での話題にもつながります。
季節行事や地域食材を取り入れた食文化体験
節分やひな祭り、お月見など、日本の伝統行事と関連づけて食育を行うと、文化への理解も深まります。
地域の特産物や行事食を取り入れることで、郷土への愛着や食文化の多様性を感じることができます。たとえば、七夕にはそうめんを提供したり、お月見には団子づくり体験をしたりすると、子どもたちは楽しみながら行事の意味を学べます。地域の農家や市場と連携すれば、地産地消の意識づけにもつながります。
給食時間を活用していろんな人と食事をする
日々の給食時間も、食育の大切な場です。
保育士や異年齢の子どもたちと一緒に食べることで、マナーや会話の力が育まれます。また、時には調理員や栄養士が食事に参加することで、「つくってくれる人」の存在を身近に感じられ、感謝の気持ちが育ちます。食器の片付けや食べ残しについて話し合う時間を設けるのも、食に向き合うよい機会となります。
まとめ:食育を通じて育てたい「未来の子どもたち」の姿

保育園での食育は、単に栄養をとるだけの時間ではありません。
子どもたちは食を通して、命の大切さ、感謝の心、健康的な生活習慣を自然と身につけていきます。年齢や発達に応じた取り組みを積み重ねることで、自ら食べる力と、人と関わる力が育ちます。さらに、保護者と連携した食育の発信は、園の魅力を高める大きな要素にもなります。
「食べることが楽しい」「この園に通わせたい」――そんな声が集まる保育園づくりのために、まずはできることから始めてみませんか?
食育に熱意ある保育士の採用を叶えよう!【採用担当らいん君のご紹介】
食育に力を入れる園には、その想いに共感する保育士が必要です。
しかし「応募が少ない」「ミスマッチが起きやすい」といった採用の悩みを抱える園は少なくありません。そこでおすすめなのが、LINEを活用した採用支援ツール「採用担当らいん君」です。
LINE上で応募者と気軽にやり取りでき、園の魅力や食育の取り組みも写真や動画で自然に発信できます。問い合わせ対応や見学予約も自動化できるため、採用担当者の負担を大幅に軽減します。食育への共感を持つ人材とつながるきっかけに、ぜひ活用をご検討ください。
詳しくは、採用担当らいん君|公式サイトをご覧ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。