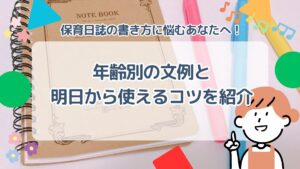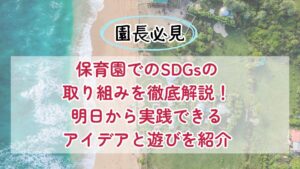保育の五領域とは?園長が押さえるべきねらい・内容・指導計画の活かし方
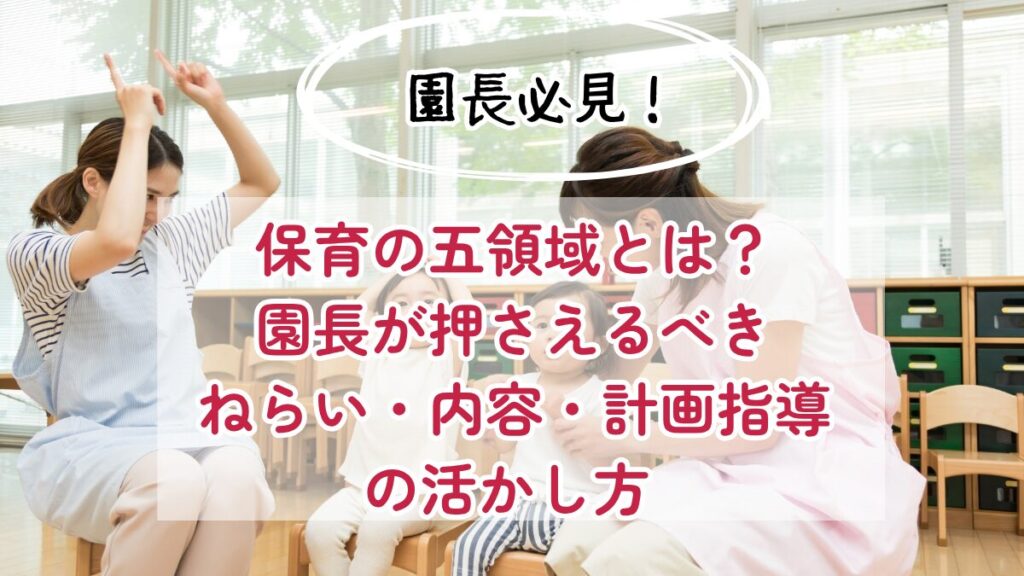
保育の五領域は、保育指針において定められた「子どもの発達を支える5つの観点」です。
日々の保育や指導計画、職員への指導方針にも大きな影響を与える重要な要素です。
この記事では、五領域の定義やねらい、具体的な遊び例、また「10の姿」「3つの柱」との関係までを解説します。
園全体で共通認識を持つための参考に、ぜひお役立てください。
目次
保育の五領域とは?

保育の五領域とは、子どもの発達を支えるための「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの観点を指します。
厚生労働省が定めた「保育所保育指針」に基づき、全国すべての保育施設で共通の視点として活用されています。
それぞれの領域には、年齢や発達段階に応じた「ねらい」と「内容」が定められており、日々の保育活動の土台になります。
たとえば「健康」では、基本的な生活習慣を身につけることや、元気に遊ぶ体づくりが目標となります。
五領域の考え方は、指導案・保育計画の作成や、保育士の研修テーマにも活用されています。
特に園長やリーダー職は、この5つの観点をもとに、職員の保育実践や成長をサポートする役割を担っています。
保育所保育指針に基づく定義と出典
五領域の考え方は、平成30年に改訂された「保育所保育指針(厚生労働省)」に基づいています。
この指針は、子どもの健やかな育ちを支えるための全国共通のルールであり、すべての保育所が従うべき内容となっています。
指針では、五領域について以下のように位置づけられています。
「子どもが環境とのかかわりの中で多様な体験を通じて、心身ともに健やかに育つことを目的として、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域を設定する。」
このように、五領域は単なる分類ではなく、子どもの発達全体を包括的に支える「教育的な視点」を含んでいます。
また、文部科学省が定める幼稚園教育要領や、認定こども園の教育・保育要領とも共通点があり、すべての乳幼児教育で共通の視点といえます。
引用文献:保育所保育指針概要
各五領域のねらいと内容

保育の五領域は、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つに分かれており、それぞれの領域において、子どもの発達を支えるための「ねらい」と「内容」が明確に定められています。
ここでは、各領域について詳しく見ていきます。
健康
「健康」の領域では、子どもが心身ともに健やかに成長し、基本的な生活習慣を身につけることが目的です。
ねらいとしては、十分に体を動かして遊び、休息や栄養をとりながら生活リズムを整えることが挙げられます。
内容には、食事・排泄・着脱といった日常動作の自立に向けた習慣づけが含まれます。
また、けがや病気の予防、安全な行動の理解など、自分の体を大切にする意識を育てることも重要です。
子どもが元気に生活し、自分の健康を守る力を少しずつ身につけていく基盤となる領域です。
引用文献:「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表 (教育・養護のねらい及び内容関係)」
人間関係
「人間関係」の領域は、他者と関わる力を育て、社会性の基礎をつくることがねらいです。
子ども同士のやりとりや、保育者との信頼関係を通じて、共感する心やルールを守る態度が身につきます。
内容としては、友達と一緒に遊ぶ、役割を分担する、自分の気持ちを言葉で伝えるなどの行動が含まれます。
人との関わりを通して「うれしい」「かなしい」などの感情を知り、自分を受け入れ、人を大切にする心が育ちます。
引用文献:「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表 (教育・養護のねらい及び内容関係)」
環境
「環境」の領域では、子どもが身の回りの自然や社会、生活に興味を持ち、関わろうとする力を育てます。
ねらいは、自然や物、人とのかかわりを通じて気づきや疑問を持ち、自ら探ろうとする姿勢を育てることです。
内容には、植物や動物の世話、季節の変化への気づき、道具の使い方や身近な社会との関わりが含まれます。
主体的に環境に関わる経験を重ねることで、考える力や生活の知恵、社会とのつながりが育まれていきます。
引用文献:「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表 (教育・養護のねらい及び内容関係)」
言葉
「言葉」の領域は、自分の思いを伝えたり、相手の話を理解したりする力を育てることがねらいです。
保育者や友達との会話、絵本の読み聞かせ、言葉遊びなどを通じて、語彙を増やし、話す・聞く力を養います。
内容としては、言葉で気持ちを表現する、質問する、相手の話に耳を傾けるといったやりとりが中心です。
言葉は自己表現の手段であり、人と関わる上で欠かせない力です。
言葉を通して自己肯定感や社会性も高まります。
引用文献:「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表 (教育・養護のねらい及び内容関係)」
表現
「表現」の領域では、子どもが感じたことや考えたことを、音・形・動きなどを使って自由に表す力を育てます。
ねらいは、表現することの楽しさや、自分らしさを認められる経験を通じて、自信を持つことです。
内容には、絵を描く、歌う、踊る、ごっこ遊びなど、多様な方法で表現する活動が含まれます。
子どもが安心して自己表現できる環境を整えることで、創造力や感受性、非言語でのコミュニケーション能力が伸びていきます。
引用文献:「幼稚園教育要領・保育所保育指針対照表 (教育・養護のねらい及び内容関係)」
五領域を活かした遊びと日常保育の実例
保育の五領域は、指導計画や評価だけでなく、日常の遊びや活動の中でも自然に取り入れることができます。
遊びを通じて子どもたちが楽しみながら、心身ともに育つ環境をつくるためには、保育者が五領域を意識しながら活動を組み立てることが大切です。
ここでは、各領域に対応する遊びの具体例と、実際の保育活動でどのように五領域を活かせるのかを紹介します。
領域別の遊び事例
五領域は、実際の遊びや日常保育に自然に組み込まれています。ここでは、各領域ごとに対応した遊びを紹介します。
| 五領域 | 内容 |
| 健康 | 戸外での鬼ごっこ、平均台遊び、マット運動など、体を十分に使って遊ぶ活動。 |
| 人間関係 | ごっこ遊び(ままごと、ヒーローごっこなど)、ペアやグループでの簡単なゲーム。 |
| 環境 | 虫探し、季節の自然観察、園内の掃除や植物の水やり。 |
| 言葉 | 絵本の読み聞かせ、しりとり、紙芝居、インタビューごっこ。 |
| 表現 | お絵描き、粘土遊び、リズムダンス、手作り楽器による演奏。 |
このように、五領域は意識すればするほど、日常のあそびに深く関係していることがわかります。
お店屋さんごっこ・フルーツバスケット・公園へのお散歩
ここでは、多くの園で取り組まれている代表的な遊び活動を3つ取り上げ、それぞれがどのように五領域に関わっているかを具体的に見ていきます。
お店屋さんごっこ
お店屋さんごっこは、複数の領域を同時に活かせる遊びです。
たとえば、商品の準備や並べ方には「環境」や「表現」の要素が含まれます。
売り手と買い手のやりとりでは「言葉」や「人間関係」が育まれ、遊びを通じて自然とルールや順番を守る力が身につきます。
また、机の配置や看板づくりなど、自分たちで環境をつくる工夫も「環境」に関わります。
フルーツバスケット
フルーツバスケットは、集団でルールを守って遊ぶゲームです。
言葉を使ってフルーツの名前を覚えたり、タイミングを見て動いたりと、「言葉」「健康」「人間関係」の要素が自然に含まれています。
ルールを理解して遊ぶ中で、聞く力や判断力も育っていきます。
また、「椅子に座る」「立ち上がる」などの動作も含まれるため、運動機能の発達にもつながります。
公園へのお散歩
お散歩は、保育園ならではの大切な日課の一つです。
「健康」の面では、歩いたり坂を登ったりすることで運動になります。
また、道中の草花や虫、季節の変化に気づくことで「環境」への関心が育ちます。
さらに、「人間関係」や「言葉」の面では、保育者や友達との会話、道中の約束事の確認などが含まれます。
「あっちに蝶がいたよ!」「こっちはどんぐりが落ちてた」など、言葉による発見の共有も豊かな育ちにつながります。
このように、五領域は単なる評価項目ではなく、日々の遊びや活動に密接に関係しています。
園長や主任の立場からは、遊びに対して保育者がどのようなねらいを持って取り組んでいるかを確認し、振り返る視点として五領域を活用することが重要です。
合わせて知っておきたい!保育の「10の姿」と「3つの柱」とは

保育の五領域を理解する際には、文部科学省と厚生労働省が共通で示している「幼児期の終わりまでに育ってほしい「10の姿」と、小学校以降の学びにつながる「3つの柱」の考え方もあわせて押さえておくことが大切です。
これらは、保育の質を高め、子どもの発達を長期的に見通すための重要な視点です。
10の姿について
「10の姿」とは、幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿を10項目で示したものです。
これは、幼稚園教育要領・保育所保育指針・こども園教育保育要領のすべてに共通して掲載されており、
子どもの育ちの到達イメージとして、指導計画や保育の振り返りに活用されます。
10の姿は五領域と密接に関係しており、日々の遊びや活動の中で育まれる力の集まりです。
3つの柱について
「3つの柱」は、小学校以降の学びに向けて幼児期に育むべき資質・能力を次の3つに分類したものです。
知識及び技能の基礎
日常生活や遊びを通して得られる「わかる」「できる」という体験が、学びの基礎となります。
たとえば、生活習慣の自立、数や文字への興味、道具の扱いなどがこの領域に含まれます。
思考力、判断力、表現力などの基礎
子どもが感じたり考えたりしながら、遊びの中で試行錯誤をする経験が、この力を育てます。
友達と話し合ったり、思いを絵や言葉で表したりする活動が該当します。
学びに向かう力、人間性など
自分からやってみようとする意欲や、最後までやり遂げようとする粘り強さ、
また、他者と協力したり思いやったりする姿勢がこの領域にあたります。
子どもが安心して過ごせる信頼関係の中で、自然と育っていきます。
五領域と「10の姿」「3つの柱」は、それぞれが保育の質を支える視点であり、決してバラバラのものではありません。
園長先生がこの3つを整理して理解しておくことで、職員研修や指導計画づくりにおいて説得力のある説明が可能になります。
まとめ:保育の五領域を保育活動に活かそう
保育の五領域は、単なる分類ではなく、子どもたちの健やかな発達を支えるための大切な視点です。
「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの柱は、それぞれが独立しているわけではなく、遊びや日常生活を通じて相互に関わりながら、子ども一人ひとりの「育ち」を形づくっています。
園長や主任などリーダーの立場にある方が、五領域の意義をしっかりと理解し、職員にわかりやすく伝えられることが、園全体の保育の質を高める第一歩となります。
また、「10の姿」や「3つの柱」とあわせて捉えることで、より中長期的な視点から子どもの育ちを見通し、指導計画や保育環境の整備、園の保育理念の言語化にもつながります。
五領域を日々の実践に活かし、保育の専門性を園全体で高めていきましょう。
園の取り組みをPRできるサービス「らいん君」
五領域を意識した保育実践は、子どもの育ちを支えるだけでなく、園の魅力として保護者や求職者に伝えることができます。
そうした取り組みを効果的に発信したい園におすすめなのが、「らいん君」シリーズのサービスです。
採用担当らいん君
「採用担当らいん君」は、LINE公式アカウントを活用して、保育士の採用活動を自動化・効率化できるサービスです。
求人情報の発信、見学希望者への対応、イベントの案内などをLINE上でスムーズに行うことができ、応募者とのやりとりがスピーディになります。
「五領域を大切にした保育方針を伝えたい」「園の雰囲気を事前に知ってもらいたい」
そんな想いを、「LINE」という身近なツールで丁寧に届けることができます。
園児募集らいん君
「園児募集らいん君」は、保護者向けの園紹介や問い合わせ対応をLINEで自動化できるサービスです!
園見学の予約受付、質問対応、行事のお知らせなども一括して管理でき、保育内容や五領域を活かした取り組みをしっかりとアピールすることができます。
保育の質を高めるだけでなく、それを外部に伝える工夫もまた、園の信頼や満足度につながります。
らいん君を活用して、園の取り組みをわかりやすく発信していきましょう。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。