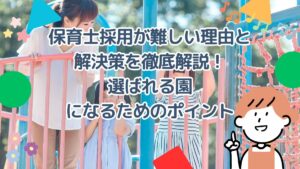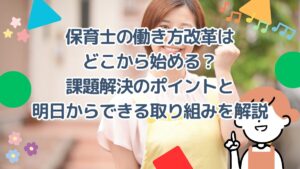保育士の人事評価、どう書く?評価項目や目的、中堅・新人別の例文を交えて紹介
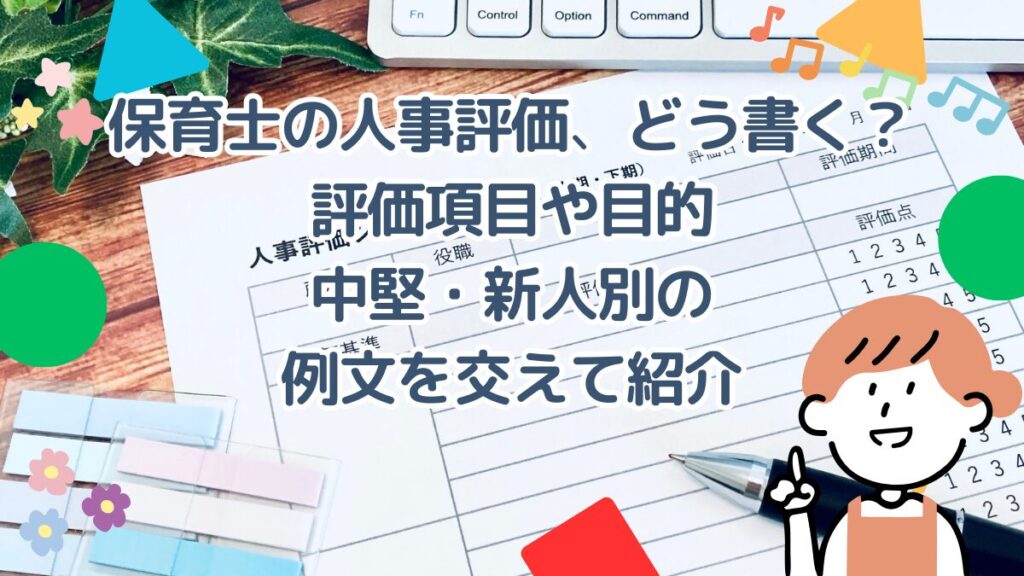
人事評価の季節が近づくと、「自己評価シートに何を書けばいいのだろう…」「自分の頑張りは正当に評価されているのかな?」と頭を悩ませる保育士の方は多いのではないでしょうか。日々の保育業務は、数字で測れる成果が見えにくいため、文章で自己評価をしたり、目標を設定したりすることに難しさを感じるのも無理はありません。また、園の運営側にとっても、職員のモチベーションを高め、成長を促す公正な評価制度の構築は重要な課題です。
この記事では、保育士の人事評価の目的や具体的な評価項目から、経験年数別の目標設定・自己評価の例文、評価者に伝わる書き方のポイントまで、網羅的に解説します。人事評価への苦手意識を克服し、自身の成長とキャリアアップにつなげるためのヒントを見つけていきましょう。
目次
保育士の人事評価とは?その目的と必要性
保育士の人事評価とは、保育士一人ひとりの能力や勤務態度、業績などを一定の基準に基づいて評価し、その後の育成や処遇に反映させる仕組みのことです。近年、保育業界においても、職員の成長を支援し、組織全体の質を向上させるために人事評価制度の重要性が増しています。年功序列ではなく、個々の頑張りを正当に評価する体制は、職員のやりがいにも直結します。
保育士の成長とスキルアップを促す
人事評価の第一の目的は、保育士個々の成長を促すことです。評価を通じて、自身の強みや課題が明確になります。例えば、「子ども一人ひとりの気持ちに寄り添った声かけは得意だが、保護者への説明が少し苦手かもしれない」といった自己分析が可能になります。これにより、次のステップとして何を学ぶべきか、どのようなスキルを伸ばすべきかという具体的な目標設定に繋がり、効果的なスキルアップが期待できます。
職員のモチベーション向上と定着率改善
適切な評価は、保育士の仕事に対するモチベーションを大きく向上させます。自分の頑張りや成果が認められ、昇給や賞与といった処遇に反映されることで、「もっと頑張ろう」という意欲が湧きます。逆に、評価が曖昧で頑張っても報われないと感じると、不満が募り離職の原因にもなりかねません。公正な人事評価は、職員が安心して長く働ける環境作りに不可欠であり、人材の定着率改善にも貢献します。
園の方針や理念の浸透
人事評価の評価項目は、園がどのような人材を求めているか、どのような保育を大切にしているかを示すメッセージでもあります。評価項目に「園の保育理念に基づいた行動」といった内容を盛り込むことで、職員は日々の業務の中で常に園の方針を意識するようになります。評価制度を通じて、園全体の価値観を共有し、一貫性のある質の高い保育サービスを提供することに繋がるのです。
保育士の人事評価における主な評価項目

保育士の人事評価では、どのような点が評価されるのでしょうか。評価項目は園によって様々ですが、一般的には「子どもとの関わり」「保護者対応」「組織への貢献」「自己成長」の4つの観点から設定されることが多いです。
| 評価項目の大分類 | 具体的な評価内容の例 |
| 子どもとの関わり | ・子どもの発達段階や個性に応じた適切な援助ができるか ・安全に配慮し、安心できる環境を構成しているか ・子どもとの信頼関係を築き、主体性を尊重した関わりができるか |
| 保護者対応 | ・保護者の気持ちに寄り添い、丁寧にコミュニケーションが取れるか ・子どもの様子や成長を分かりやすく伝えられるか ・家庭からの相談に対し、適切に対応し、関係機関と連携できるか |
| 組織への貢献 | ・他の職員と協力し、円滑なチームワークを築けるか ・園の行事や係の仕事に主体的に取り組めるか ・報告・連絡・相談を徹底し、情報を共有できるか |
| 自己成長 | ・保育に関する知識や技術向上のため、研修などに積極的に参加しているか ・自身の保育を振り返り、改善しようと努めているか ・社会人としての自覚を持ち、責任ある行動がとれるか |
【子どもとの関わり】保育実践に関する能力
最も中核となる評価項目です。子ども一人ひとりの発達や個性を理解し、それに応じた計画を立て、適切な関わりができるかが問われます。ただ世話をするだけでなく、子どもの主体性を引き出し、遊びや生活の中で学びを促すような環境構成能力も評価の対象となります。また、子どもの安全を確保し、心身ともに健康な生活を送れるように配慮することも重要なポイントです。
【保護者対応】信頼関係の構築と支援
保護者との良好な関係構築も保育士に求められる重要なスキルです。日々の送迎時のコミュニケーションはもちろん、連絡帳の記述や面談などを通じて、子どもの様子を丁寧に伝え、保護者の不安や悩みに寄り添う姿勢が評価されます。子育てに関する的確なアドバイスや、必要に応じて専門機関と連携するなどの支援能力も含まれます。
【組織への貢献】協調性と主体性
保育はチームで行うものです。同僚や他のクラスの職員と円滑に連携し、協力し合える協調性は不可欠です。自分のクラスだけでなく、園全体の方針を理解し、行事や委員会活動などに積極的に貢献する姿勢も評価されます。また、日々の業務における「報告・連絡・相談」を徹底し、チーム全体で情報を共有し、課題解決に取り組む力も問われます。
【自己成長】専門性の向上と自己管理
保育士として常に学び続ける姿勢も大切です。新しい保育の知識や技術を習得するための研修への参加や、資格取得への挑戦などが評価されます。また、日々の保育を客観的に振り返り、課題を見つけて改善していく自己研鑽の姿勢も重要です。遅刻や欠勤がないといった基本的な社会人としての規律や、心身の健康管理も評価の対象となる場合があります。
【経験年数別】人事評価の目標設定と自己評価の例文

ここでは、経験年数別に目標設定と自己評価の具体的な例文を紹介します。ご自身の状況に合わせてアレンジして活用してください。
新人保育士(1~3年目)向けの目標・自己評価例文
新人保育士は、まず園の生活や業務の流れを覚え、基本的な保育スキルを確実に身につけることが目標となります。
目標設定の例:
「園の一日の流れを理解し、先輩保育士の指示がなくても主体的に動ける場面を増やす。また、子ども一人ひとりの名前と個性を覚え、安心して過ごせるような積極的な声かけを心がける。」
自己評価の例文:
「この半年間、まずは笑顔で子どもたちと接し、信頼関係を築くことを第一に考えてきました。特に、登園時に不安そうな表情をしていたAちゃんには、目線を合わせて好きなキャラクターの話をすることで、笑顔で保育室に入れる日が増えました。一方で、活動の準備や片付けでは、まだ先輩方に頼ってしまう場面が多くあります。今後は、一日の流れを予測し、次に何をすべきか考えて行動することで、よりスムーズなクラス運営に貢献したいです。」
中堅保育士(4~7年目)向けの目標・自己評価例文
中堅保育士は、培ってきた経験を活かして保育の質を高めるとともに、後輩の指導やクラス運営の中核を担うことが期待されます。
目標設定の例:
「クラスリーダーとして、保育計画の立案を主体的に行い、後輩職員の意見も積極的に取り入れる。また、保護者からの難しい相談に対しても、初期対応を責任をもって行い、主任や園長と連携して解決に導く。」
自己評価の例文:
「今年度は、2歳児クラスのリーダーとして、子どもたちの発想を活かした活動計画を意識しました。特に、子どもたちが夢中になった『お店屋さんごっこ』では、保護者の方にも廃材集めなどで協力いただき、活動を大きく発展させることができました。これにより、子どもの主体性だけでなく、保護者との連携も深まったと感じています。課題としては、後輩のB先生への指導において、具体的な指示に留まりがちだった点です。来期は、B先生自身が考え、成長できるような関わり方を意識していきます。」
ベテラン保育士(8年目以上)向けの目標・自己評価例文
ベテラン保育士は、自身の専門性をさらに深めるとともに、園全体の保育の質の向上や、組織運営への貢献といった、より高い視点が求められます。
目標設定の例:
「自身の得意分野である障がい児保育に関する知識を活かし、園内研修を企画・実施する。また、若手・中堅職員のキャリア形成について相談に乗り、園全体の保育力向上に貢献する。」
自己評価の例文:
「長年の経験で培った発達支援の知識を、園全体で共有する必要があると感じ、今年度は『気になる子へのポジティブな関わり方』というテーマで園内研修を実施しました。研修後のアンケートでは、多くの職員から『具体的な対応方法が分かり、自信になった』との声をもらい、手応えを感じています。また、保護者対応で悩んでいたC先生の相談に乗り、一緒に対応策を考えた結果、保護者との関係が改善し、先生の自信にも繋がったことは大きな喜びでした。今後は、園の保育理念を次世代に繋いでいくためにも、若手職員の育成にさらに力を注いでいきたいです。」
人事評価シートを作成する際の3つのポイント

自己評価シートを書く際には、いくつかのポイントを押さえることで、評価者により自分の頑張りが伝わりやすくなります。
具体的なエピソードを盛り込む
「頑張りました」「できました」といった抽象的な言葉だけでは、評価者に十分な情報が伝わりません。「〇〇という課題に対し、~という工夫をした結果、△△という成果に繋がった」というように、具体的なエピソードを交えて記述することが重要です。数値で示せる成果があれば(例:欠席日数が減った、残業時間が短縮できたなど)、積極的に盛り込むと客観性が増します。
ポジティブな表現を心がけ、課題は改善策とセットで記述する
自己評価は反省文ではありません。まずは自分の成長した点や達成できたことをポジティブな言葉で記述しましょう。もちろん、課題や反省点を書くことも大切ですが、その際は「~ができなかった」で終わらせるのではなく、「~という課題があるため、今後は〇〇していきたい」と、具体的な改善策や今後の目標とセットで書くことがポイントです。これにより、前向きな姿勢と成長意欲を示すことができます。
園の理念や方針、クラス目標との関連性を意識する
自分の行動や成果が、園の方針やクラスの目標にどのように貢献したのかを意識して記述すると、より高い評価に繋がります。例えば、「園の『主体性を育む』という保育目標に基づき、子どもたちが自ら遊びを選べるような環境構成を工夫しました」のように記述することで、自分の実践が組織の目標達成に貢献していることをアピールできます。
人事評価制度を導入・運用する際の注意点

人事評価制度は、ただ導入するだけでは機能しません。職員の納得感を得て、組織の成長に繋げるためには、いくつかの注意点があります。
評価基準の透明性と公平性を確保する
職員が最も不満を感じるのは、評価基準が曖昧で、誰が評価しても結果が変わるような不公平な評価です。評価項目や基準は全職員に公開し、なぜこの評価になったのかを説明できるように、透明性を確保することが不可欠です。評価者の主観に頼りすぎないよう、自己評価や同僚評価などを組み合わせる(360度評価)ことも有効な手段です。
評価者への研修を十分に行う
園長や主任などの評価者も、評価の専門家ではありません。評価の目的や基準、面談の進め方などについて、事前に十分な研修を行う必要があります。評価者が適切な知識を持たないまま評価を行うと、評価のばらつきや、部下のモチベーションを下げてしまうといった問題が生じかねません。
評価シートを渡して終わり、では人事評価の目的は達成できません。必ず1対1の面談の機会を設け、評価結果を直接伝えることが重要です。その際は、良かった点を具体的に褒め、改善点については一方的に指摘するのではなく、本人と一緒に今後の目標を考える姿勢で対話することが求められます。このフィードバックを通じて、評価への納得感を高め、次への成長意欲を引き出すことができます。
まとめ
保育士の人事評価は、給与や賞与を決めるためだけのものではありません。保育士一人ひとりが自身の保育を振り返り、成長するための重要な機会です。また、園にとっては、職員のモチベーションを高め、組織全体の保育の質を向上させるための大切な仕組みと言えます。本記事で紹介した例文やポイントを、ご自身の成長と園の発展に繋がる人事評価に、ぜひお役立てください。
また、人事評価の結果を採用活動や職員の定着支援にも活かすには、日々のコミュニケーションの質が重要です。職員とのつながりを深め、採用活動の効率化にも貢献するLINE活用ツール「採用担当らいん君くん」もぜひご活用ください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。