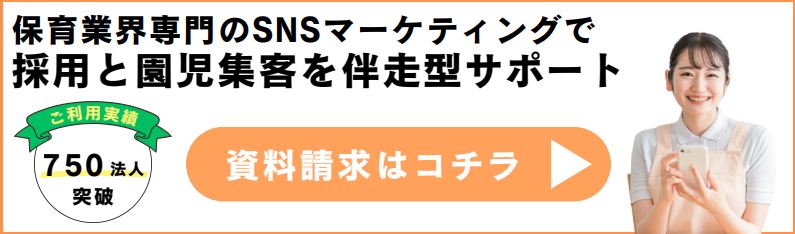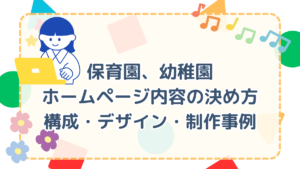園児募集にも採用にも効く!保育園のSNS活用成功事例と運用ポイント
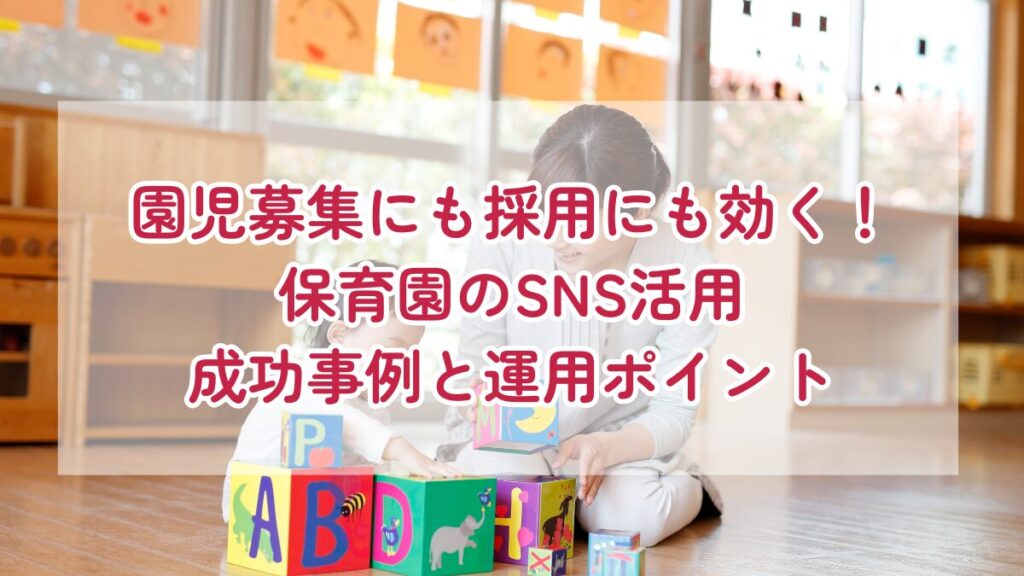
最近では、保育園でも「SNSで園の様子を発信する」取り組みが増えています。InstagramやLINEなどを使って日々の活動を紹介すると、園の雰囲気が伝わりやすく、入園希望の保護者や働きたい保育士からの見学や応募につながりやすくなります。
けれども、「SNSって何から始めたらいいの?」「写真を出しても大丈夫なの?」「トラブルにならないか心配…」そんな不安を持つ園も多いのではないでしょうか。
この記事では、SNSが保育園にもたらす良い効果と、実際にうまくいっている園の例をまじえながら、どんなポイントに気をつければよいかを、わかりやすくご紹介します。
目次
保育園がSNSを活用するメリット

まずは「なぜSNSでの発信が成果につながるのか」という疑問から、一緒に見ていきましょう。
SNSには、園の魅力を知ってもらうだけでなく、親しみが感じられることによって信頼を深める力もあります。
園をアピールできる
近年はスマートフォンで情報を調べるのが当たり前の時代です。2025年時点では、日本人の約9割が各SNSを利用していると言われており、保護者や求職者も「園の公式サイトより先にSNSをチェックする」ことが増えています。
つまり、SNSを活用することで「まだ園を知らない人」にも発見してもらえる機会が大きく広がるのです。
検索では見つけてもらえなかった小規模園や認可外保育園でも、写真1枚・動画1本の投稿がきっかけで「気になる園」として話題に上がるケースも珍しくありません。
タイムリーな情報を発信できる
SNSの大きな強みは、「リアルタイムで情報を届けられること」です。たとえば、保護者向けのLINE公式アカウントを用意しておけば、行事の日程変更や、天候による登降園時間の調整など、これまで電話やメーリングリストで伝えていた内容も、LINEで一斉に発信すれば一瞬で届きます。更にメールに比べて開封率も高いのがポイントです。
さらに求職者や保活中の保護者にとっては、投稿を続けることで「園の名前や写真を何度も目にする」機会が増えます。この繰り返しが、心理学でいう単純接触効果(ザイオンス効果)を生み出します。つまり、人は何度も目にするうちに親しみや好感を持ちやすくなるという働きです。
SNSの発信をこまめに続けるだけで、園の印象が強まり、保護者や求職者から「信頼できそう」「雰囲気が良い園だな」と感じてもらえる確率が高まるのです。
親近感を持ってもらいやすくなる
SNSでは、行事の様子だけでなく、先生たちの普段の姿を発信することも大切です。たとえば、朝の会で子どもたちと笑い合う瞬間や、給食を一緒に楽しむ場面など、人の温かみを感じる投稿は見る人の心に残ります。
こうした投稿が増えると、「先生たちが楽しそう」「子どもとの関係が丁寧そう」など、園に対する好印象が積み重なっていきます。やがてその積み重ねが“ファン化”につながり、「この園を見学してみたい」「ここで働いてみたい」という前向きな気持ちを生み出します。
実際に、職員紹介や日常のちょっとした投稿を続けている園では、「SNSを見て園の雰囲気が伝わった」「先生たちの人柄が分かって安心した」などの声が増え、見学申し込みや応募件数が上がったケースもあります。
SNS運用を成功させるためのコツ

SNSをはじめるときに大切なのは、「勢いで投稿する」のではなく、園としての考え方やルールを決めてから動くことが成功への近道です。また、SNSはだれでも閲覧できるもののため、誤った投稿をすると炎上と言われる評判の悪化につながりかねません。
ここでは、トラブルを防ぎながら、しっかり運用していくためのコツを紹介します。
ニーズのあるコンテンツを把握する
まず意識したいのは、「見る人が知りたい内容を発信すること」です。
例えば求職者であれば「どんな人が働いているのか」「自分が働きたい雰囲気なのか」を知りたくてSNSを見ておりますし、保護者の方であれば「どんなイベントをやっているのか」「子どもは笑顔で過ごせているのか」を気にします。
そのため保育園のSNSでは、誰にどんなことを見せて、どんなイメージを持ってもらいたいのかを明確にしましょう。
また、投稿を続ける中で「どんな投稿に“いいね”や反応が多いか」を見ていくと、保護者が関心を持つテーマが少しずつ見えてきます。それを参考に次の投稿内容を考えれば、「読んでくれる人に寄り添う発信」へと成長していきます。
情報(プロフィール等)を充実させる
SNSを運用するうえで、意外と見落とされがちなのが「プロフィール欄」です。
初めて園のアカウントを見た人が最初に目にする場所なので、ここを整えるだけでも印象が大きく変わります。
たとえばInstagramなら、園名や所在地だけでなく、「どんな保育をしている園なのか」を一文で入れておきましょう。「少人数で家庭的な保育を行う」「英語と遊びを組み合わせたプログラム」など、園の特徴が一目で分かるようにすると、検索から見つけてもらいやすくなります。
また、絶対に忘れないでおきたいのが、プロフィールにホームページやLINE公式アカウントのリンクを貼っておくこと。
そうすると「もっと知りたい」と思った人がすぐ行動に移せます。
SNSの運用はあくまでもブランディングです。次のアクションに繋げていくためには、閲覧しているユーザーが迷わずにアクションできるような設計が欠かせません。
配信の頻度やタイミングを分析する
SNSでは「いつ投稿するか」も大切なポイントです。良い内容を投稿しても、見てもらえる時間帯でなければ反応が得られにくいことがあります。
配信の頻度やタイミングは都度インサイト(分析画面)を見ながら効果検証を続けていきましょう。
まずは、ターゲットとなるユーザーの行動をイメージします。例えば、求職者にみて欲しい場合は夕方〜夜(18時〜21時)に投稿すると、仕事を終えた人がスマートフォンを見る時間と重なりやすく、閲覧数が増える傾向にあります。
一方で、園児募集向けのLINE配信は保護者にあてて配信するため、夜などの家族時間にはスマートフォンをさわれないことが多いです。そういったターゲットにみて欲しい場合は、朝の通勤前や昼休み(8〜12時頃)が閲覧されやすいといわれています。
SNS運用を成功させるための注意点

SNSは大勢の人に見てもらうにはぜひ活用したいツールですが、運用方法や投稿内容を間違えると、批判や大問題に発展しかねません。
あらかじめ注意点を認識し、細心の注意を払って運用していきましょう。
投稿前のチェックは必ず複数人で
SNS運用を長く続けるうえで欠かせないのが、「投稿前の確認体制」です。
1人の判断で投稿してしまうと、誤字や誤解を招く表現、写真の写り込みなどに気づけないことがあります。まずは園全体で、使用してはいけない子どもはいないか、保育園の理念や保育方針にそぐわない投稿になっていないか等チェックリストを作成しましょう。
おすすめは、職員2〜3人でのダブルチェック制です。またとえば「配信内容を作る係」「コンテンツ内容をチェック係」を分けると、ミスや事故を減らせます。。
実際に、この確認ルールを取り入れた園では、「言葉遣いや写真のトーンがそろい、園の発信が安定した」という声もあります。基本的にSNSでは間違った投稿をしても安易に取り消すことは出来ず、信頼回復にも多大な時間がかかります。そうならないためにも“SNS運用におけるチェックリストの作成”と“投稿前にダブルチェック”で未然にトラブルを防ぎましょう。
写真使用の許可とガイドラインの整備
SNSで園の写真を発信するときに、いちばん悩むのが「どこまで出していいのか」という点ではないでしょうか。
個人情報への配慮から「人が映るものはNG」としてしまいたくなる気持ちもわかります。ですが、安全を重視するあまり何も載せないとなると、せっかくの子どもたちの楽しそうな姿や、園の温かい雰囲気がまったく伝わらなくなってしまいます。
保育園のSNSは“情報発信”であると同時に、“園の魅力を見てもらう窓”でもあります。保護者や求職者は、子どもたちの表情や先生たちのやりとりを通して「園の空気感」を感じ取っています。だからこそ、できるだけ自然でリアルな雰囲気が伝わる写真を、前向きに発信していきましょう。
投稿にあたっては、年度初めなどに写真使用の同意書をとっておくと安心です。
また、投稿後に削除の希望があれば、すぐに対応できるようにしておくことも大切です。
もし子どもの顔や姿を載せにくい場合は、「見せない」よりも「どう見せるか」を工夫してみましょう。
たとえば、
- 子どもの顔を少し横向きにしたり、後ろ姿の写真を使う
- グループ全体を写して「雰囲気」で伝える
- ピントを手元や活動に合わせる(例:制作・給食など)
こうした工夫で、プライバシーを守りながらも、園の楽しさや温かさをしっかりと伝えることができます。
ルールを守りながら「見てもらえる園」「伝わる園」になるための発信を続けることが、
結果として保護者や地域からの信頼につながっていきます。
保育園で活用すべきSNSの種類と特徴

SNSと一口に言っても、ツールによって使う目的や得意な発信内容は少しずつ違います。それぞれの特徴を知っておくことで、「どんな投稿をすれば伝わりやすいか」が見えてきます。
ここでは、保育園に特におすすめの5つのSNSをご紹介します。
忙しい人はこれだけ確認!
| SNS名 | 向いている目的 | 特徴・強み | 注意点・弱み | おすすめ度 |
| 園児募集・ブランディング | 写真・動画で園の雰囲気を直感的に伝えられる。多くの人に見てもらいやすい | 継続投稿が必要。フォロワーを増やすには時間がかかる。 | ★★★★☆ | |
| LINE公式アカウント | 採用・園児募集・保護者対応 | 直接メッセージを送れる。プッシュ通知で確実に届く。予約や問い合わせ対応にも便利。 | 導線設計が重要。友だち追加しないと見てもらえない。 | ★★★★☆ |
| X(旧Twitter) | イベント速報・リアルタイム発信 | 短文投稿で気軽に情報を発信できる。拡散性が高い。 | 炎上リスクあり。保育層の利用率はやや低め。 | ★★☆☆☆ |
| YouTube | 園紹介・採用・理念発信 | 動きや声など“園の空気感”を伝えられる。丁寧な発信に最適。 | 撮影・編集に手間がかかる。継続投稿のハードルが高い。 | ★★★☆☆ |
| 地域連携・卒園児とのつながり | 地域行事やOB家庭への発信に強い。コメントで交流も可能。 | 若い世代の利用が減少。主な保護者層には届きにくい。 | ★★☆☆☆ |
Instagram ― 写真で園の雰囲気を伝えるには一番!
Instagramは、園の雰囲気を写真や動画でパッと伝えられる人気のSNSです。
特別な知識がなくても始めやすく、スマートフォン1つで投稿できます。
- フィード投稿とリール動画の2種類の投稿方法があります。
- 写真だけでも投稿できるので、準備が比較的しやすくて安心。
- 写真メインだから、園の雰囲気や保育の様子など伝えられる情報がたくさん!
- 誰でも自由に見られる仕組みなので、園の認知度を上げたいときにぴったりです。
- ただし、フォロワーを増やしたり、認知を広げたりするには、継続的な投稿や見た人からの「いいね」などの反応が大切です。
“日常を少しずつ発信していく”ことで、園のファンが増えていきます。
特別な広告よりも、写真1枚から「温かい雰囲気」が伝わる投稿を目指しましょう。
LINE公式アカウント ― 保護者・求職者とのコミュニケーションに
LINE公式アカウントは、保護者や求職者と直接つながることができる便利なツールです。行事の案内や園見学の予約をLINEで受け付けるだけでも、電話対応の手間がぐっと減ります。またメッセージを送れば相手のスマートフォンにすぐ届くので、「見逃されにくい」のも大きな強みです。
- コンテンツをしっかり作りこめば、他のSNSと同じようにたくさんの情報を発信できます。
- 友だち追加をした人だけが見られる仕組みなので、クローズドな内容も安心して掲載できます。
- プッシュ通知で読んでほしい情報を確実に届けられるのも魅力です。
- やりとりに特化しているので、保護者や求職者とのコミュニケーションの工数を大幅に削減できます。
誰もがみんな利用しているコミュニケーションツールのため、園でもはじめやすいツールですが、ユーザーの反応(見学・応募)につなげるには導線設計が大切です。たとえば、トーク画面のメニューに「園見学予約」や「採用情報」をボタンで設置しておくと、気になった人がその場で行動しやすくなります。
X(旧Twitter) ― リアルタイムな情報発信に
X(旧Twitter)は、短い文章と写真で“今の園の様子”を気軽に発信できるツールです。
日々の小さな出来事をこまめに投稿することで、「園の動きが見える」「親近感がわく」と感じてもらえます。
- 文字数が短いので、スマホからでも簡単に更新できるのが魅力。
- 「今日はお散歩へ行きました」「給食はカレーでした」など、何気ない一言投稿でも十分OK!
- タイムリーな情報発信に向いているので、行事の延期やお知らせにも使えます。
- ただし拡散力が強く、気軽にリアクションができる分おもわぬ投稿から炎上に発展するリスクもあり
リアルタイム発信ができるぶん、誤解を招く表現には注意が必要なのがX(旧twitter)の特徴です。またユーザーの性別もInstagramに比べて男性が多く、保育士や保活中の保護者というターゲットを考えると少し離れます。
YouTube ― 園紹介や行事動画でファンを増やす
YouTubeは、動画で園の魅力をたっぷり伝えられるツールです。動きや声、先生や子どもたちの表情など、写真では伝わらない“空気感”をそのまま届けられるのは、他のSNSにはない大きな魅力と言えるでしょう。
- 園紹介動画や行事ダイジェストなど、テーマを決めて短くまとめるのがポイント。
- 動画は1~2分程度にすると、新しく見に来た人も最後まで見やすくなります。
- 先生のインタビューや園内ツアー動画など、少し長めの動画で丁寧に園の情報を発信することもできます。
- スマホで撮影しても十分OK。ただし、テンポ感や音量、編集の工夫で飽きさせない工夫が大切です。
ほかのSNSに比べてじっくりと内容を作り込めるため、
短い投稿では伝えきれない園の考え方や保育方針をしっかり伝えることができます。
そのぶん、“すでに園に興味を持っている人”の背中を押すツールとしてとても効果的です。
動画の最後に園見学の案内やLINEのリンクを添えれば、行動につながる確率がぐんと上がります。
Facebook ― 地域とのつながりを強化する
Facebookは、もともと地域の人や卒園児の保護者とのつながりを持ちやすいSNSです。
ただし、最近では20〜30代の保護者の利用率が下がっており、投稿をしても見てもらえる層が限られてしまうのが現状です。
園児募集や採用活動を目的に使う場合、InstagramやLINEのほうが反応が出やすいでしょう。
- 投稿は写真1枚と150字前後の短い文章で十分。
- 地域行事や自治体との連携など、“まちと関わる発信”に絞るのがベター。
- 無理に更新頻度を上げるより、「必要な情報だけ載せる」くらいの感覚でOK。
- コメント欄を開放しておけば、卒園児の保護者から温かいメッセージをもらえることもあります。
つまり、Facebookは“メインの発信ツール”というよりも、「地域とのつながりを保つためのサブチャンネル」として考えるのがちょうどいいバランスです。現時点でアカウントを持っている場合は、今はInstagramやLINEを軸にしつつ、Facebookは“更新が止まらない程度”にゆるく運用するくらいで十分で、新規に開設する必要性はないと言えます。
保育園のSNS運営の成功事例

SNSを活用している保育園の中には、実際に園児募集や採用で大きな成果を上げている園もあります。
どんな工夫をしたのか、どのように発信を続けたのかを知ることで、自分たちの園でも取り入れられるヒントが見えてきます。
ここでは、LINEやInstagramなど、ツールを上手に活用して成果を出した園の取り組みを紹介します。
LINE採用で応募前から距離が縮まる!ミスマッチ減&10名採用に成功
東京都内で認可保育園を5施設運営する社会福祉法人では、LINEを採用活動に活用し、10名の保育士採用に成功しました。
導入のきっかけは、保育博でチポーレのブースを見かけたこと。
「LINEで採用?」と驚いたものの、「求職者と近い距離でやり取りができそう」と感じ、導入を決めたそうです。
LINE公式アカウントでは、園の特色や福利厚生、職員インタビュー、1日の流れなど、採用サイトでは伝えきれなかった情報をメニューに整理し、求職者が知りたい内容をすぐ確認できる仕組みを整えました。
また、定期配信では「今週の行事」や「先生たちの日常」を写真付きで紹介。
求人情報だけでなく、園の雰囲気や職員の温かさが伝わる発信を心がけた結果、「LINEで見た行事の様子が印象に残った」「園の雰囲気が伝わってきた」といった声が増え、園見学や応募の動機につながっています。
LINEでのやり取りが中心になってからは返信も早くなり、「メールよりも話しやすい」「気軽に質問できる」といった反応が多く見られました。
担当者は「LINEならやり取りの中で人柄が伝わるので、初めて会うときも緊張が少ない」と話しています。
園の情報発信とコミュニケーションを両立できることが、LINE活用の大きな魅力です。
イベント告知をLINEに切り替え、1か月で親子教室への問合せ12件以上を獲得
横須賀市にある認定こども園では、「園児募集らいん君」を導入し、
イベント告知をLINEに切り替えたことで、導入から1か月で12件以上の問い合わせを獲得しました。
導入前は、園庭開放や説明会の告知をホームページやポスターで行っていましたが、園の立地上、外から園の様子が見えにくく「気軽に立ち寄りにくい」という課題がありました。
LINE導入後は、こちらから保護者へ直接案内ができるようになり、「告知しても見てもらえない」という状況を解消。
イベント参加者にはその場で友だち追加をしてもらい、次回以降の案内を継続的に送ることで、つながりを維持できる仕組みを作りました。
個別チャットでは、「持ち物の案内」に加えて、「暑い日が続いているので帽子をお忘れなく」など、季節に合わせた一言を添えるように工夫。
小さな気配りが信頼につながり、保護者からの返信や反応も増えたそうです。
担当者は「複数の園を比較する保護者にとって、発信の多い園は印象に残りやすい。
LINEはそのきっかけづくりにぴったり」と話しています。
今では、イベント参加から入園につながる動線づくりとして欠かせないツールになっています。
保育園のSNS活用は、プロに任せるのがおすすめ!

SNSを始めるのはとても簡単ですが、いざ運用をしていくと、「どんな内容を投稿したらいいのか」「どのくらいの頻度で更新すればいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
最初は順調でも、他の業務が忙しくなると投稿が止まってしまったり、内容がマンネリ化してしまうこともあります。
そんなときは、SNS運用のプロにサポートを頼むのもひとつの方法です。
専門のチームに任せることで、園の雰囲気や保育方針を的確に発信しながら、応募や園見学といった目標に応じた導線設計までサポートを受けられます。
チポーレでは、保育業界に特化したSNS・採用支援サービスを展開しています。
たとえば「採用担当らいん君」なら、応募前のやり取りを自動化し、求職者と自然なコミュニケーションを取りながら採用までつなげることが可能です。
その他youtubeチャンネルの開設支援や、Instagram運用代行サービスなど、園の課題や規模感に合わせたご提案も可能です。どのSNSが保育園に合っているのか分からない。そうお考えの園長先生は、まずはお気軽にご相談ください。
SNSを上手に活用すれば、「見てもらえる園」「選ばれる園」へと大きく前進できます。
まずは無理のない範囲で始めてみて、続けることが難しいと感じたときは、ぜひチポーレのサポートを活用してみてください!
園に合ったSNS運用を一緒に考え、“あなたの園らしさ”が伝わる発信をお手伝いします。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。