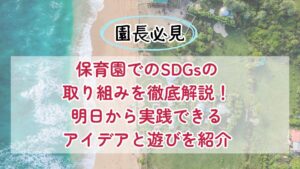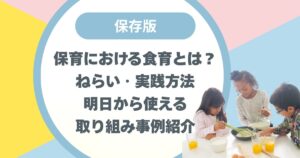【令和7年度│最新版】保育園のICT補助金とは?対象や申請の流れを解説

ICTツールの導入には費用がかかりますが、国や自治体が支援してくれる補助制度を活用すれば、園の負担を大きく減らして始められることをご存知でしょうか。
実はこのICT補助金には複数の制度があり、対象機器や補助金額もさまざまです。たとえば、国が主導する「保育所等におけるICT化推進等事業」や、自治体独自の加算制度、さらには民間企業向けのIT導入補助金まで、保育園でも活用できる制度がいくつか存在します。
自園の課題に合ったICTツールと補助制度を見つけ、金銭負担を極力なくしながら導入を進めていきましょう。
目次
ICT補助金とは?
保育園の業務を効率化するうえで、今注目されているのが「ICT」です。ICTとは、情報通信技術(Information and Communication Technology)の略語であり、登降園管理や保育記録、連絡帳アプリなど、保育現場の業務を主にインターネットを使ってスムーズに行えるようにする仕組みです。
保育ICTシステム導入に使える補助金の種類

こういったシステムの導入には、主に4つの支給元による補助制度があります。
| 支給元 | 制度名・内容 | 主な対象 | 補助内容の特徴 |
| 国(こども家庭庁・厚生労働省) | 保育所等におけるICT化推進等事業(当初予算)+こども誰でも通園制度関連ICT整備支援(令和6年度補正予算) | 認可保育所、認定こども園、小規模保育など | 登降園管理、保育記録、保護者連絡、実費徴収(キャッシュレス)など、4機能が補助対象。補助率:国1/2、自治体1/4、園負担1/4。(※機能数による) 要件次第で最大130万円相当の導入が可能。 |
| 国(こども家庭庁) | 保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金) | 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設 | 午睡センサー、園外見守り用GPS、送迎バス置き去り防止装置や性被害防止策のための設備・備品購入など。 補助率:国2/3、自治体:1/12、園負担:1/4。 要件次第で最大50万円相当の導入が可能。 |
| 自治体(都道府県・市区町村) | 地域独自の上乗せ補助・加算制度 | 地域により異なる(例:東京都、千葉県、札幌市など) | 国の制度に加えて、補助率を引き上げたり、対象機器を拡大したりする取り組みあり。補助率の全額負担や支援上限額の増額などが行われることも。詳細は各自治体の公式HP等で要確認。 |
| 民間・経済産業省 | IT導入補助金(中小企業向け) | 中小企業(保育等も対象(株式会社・社会福祉法人など) ※従業員300人未満 | 勤怠管理ソフト、クラウド型業務支援ツール、LINE連携ツールなど幅広く対応。補助率1/2、最大450万円。一部の保育園で「採用LINE」「保護者コミュニケーション」にも活用実績あり。 |
引用元:こども家庭庁「保育所等におけるICT化推進等事業①」
引用元:こども家庭庁「令和7年度保育関係予算概算要求の概要」
引用元:IT導入補助金2025
次の章から詳しく見ていきましょう。
令和7年度のICT補助金概要

まずはこれら補助金制度の基本的な枠組みをご紹介します。
対象になる施設
各制度では対象は「保育所等」とされており、基本的には以下のような施設が補助の対象です。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育など)
- 一部の認可外保育施設(自治体の判断や対象の制度による)
また、運営法人が中小企業に該当する場合は、経済産業省の「IT導入補助金」の対象になることもあります。社会福祉法人や株式会社など、法人の種類にかかわらず、従業員数が300人以下であることなどの条件を満たせば申請が可能です。
なお、いずれの制度でも、ICT機器やシステムを新たに導入・更新することで、業務の効率化や保育の質の向上に取り組む意欲があることが前提となっています。
補助基準額
制度によって異なりますが、代表的な補助額と補助率は以下のとおりです。
基本的には「上限額」と「補助率」が定められており、実際の補助金額は、導入したシステムの費用に補助率をかけた金額となります。
保育所等におけるICT化推進等事業
補助額:導入した機能の数によって決定
1機能の場合・・・1施設当たり20万円(併せて端末購入等を行う場合: 70万円)
2機能の場合・・・1施設当たり40万円(併せて端末購入等を行う場合: 90万円)
3機能の場合・・・1施設当たり60万円(併せて端末購入等を行う場合:110万円)
4機能の場合・・・1施設当たり80万円(併せて端末購入等を行う場合:130万円)
補助率:国 1/2、自治体 1/4、園 1/4
=機能について=
- 保育に関する計画・記録
- 保護者との連絡
- こどもの登降園管理等の業務
- 実費徴収等のキャッシュレス決済
ICT化推進等事業には、上記以外にも外国籍の子どもを保育するための翻訳機の購入(補助額15万円)や、研修のオンライン化に対する補助金制度(補助額40万円)もあります。
保育環境改善等事業(安全対策)
補助額:制度によって決定
午睡センサー等…50万円
子どもの見守り等に必要な機器の導入/性被害防止対策のための設備・備品…20万円
補助率:国2/3、自治体1/12、園1/4
IT導入補助金(民間)
補助額:導入したプロセス数によって決定
1プロセス以上…5万円以上150万円未満
4プロセス以上…150万円以上450万円以下
補助率:1/2以内、2/3以内※
※3ヶ月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることをしめした場合の補助率は2/3以内
| 種別 | プロセス | |
| 業務プロセス | 共通プロセス | 顧客対応・販売支援 |
| 決済・債権債務・資金回収管理 | ||
| 供給・在庫・物流 | ||
| 会計・財務・経営 | ||
| 総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | ||
| プロセス業種特化型 | その他業種固有のプロセス | |
| 汎用プロセス 単体での使用は不可 | 汎用・自動化・分析ツール (業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフトウェア) | |
実施主体
保育環境改善等事業
保育所等におけるICT化推進等事業
国(こども家庭庁・厚生労働省/経済産業省)によって制度設計がなされていますが、実際の運用・申請受付・交付決定は各自治体(都道府県または市区町村)が実施主体となっています。
つまり、「制度を決めたのは国」ですが、「実際に審査や支給を行うのは自治体」です。
そのため、同じ国の制度であっても、自治体によって実施時期・対象施設・補助要件・提出書類などが異なる場合があります。申請を検討する際は、必ずお住まいの自治体が発行する交付要綱や実施要領を確認しましょう。 (参考1)
IT導入補助金
一方、「IT導入補助金(経済産業省所管)」は、制度設計も実施も国が行いますが、申請は「IT導入支援事業者(登録業者)」が代行する形式となっています。
事業者自身が直接申請することはできないため、補助対象となるツール(ソフトウェア等)を取り扱う支援事業者を通じて申請手続きを進める必要があります。
スケジュール
ICT機器導入に関する補助金は、制度ごとに申請時期や導入期限が異なります。ここでは、主な制度のスケジュールと注意点をご紹介します。
【保育施設向け】ICT化推進等事業・保育環境改善等事業
この2つの制度は、すでに国の予算が確保されており、現在は各自治体が順次内容を公表している段階です。多くの自治体では、令和7年(2025年)4月〜7月ごろに申請受付を開始し、導入の完了期限を11月末〜翌年2月末ごろに設定しています。
たとえば、横浜市の「業務効率化推進事業」では、2025年4月から申請受付が始まり、導入完了期限は同年11月30日までと定められています。
なお、自治体によって申請条件や締切日、必要書類の様式が異なるため、事前確認は必須です。
申請を検討している園は、「ICT補助金 保育園 + 自治体名」で検索し、各自治体の交付要綱を確認しましょう。
【法人向け】IT導入補助金(経済産業省)
保育法人(株式会社・社会福祉法人等)が対象となるこの制度は、年に複数回(4〜12回程度)申請公募が行われます。
最新のスケジュールは、公式ポータルサイトで随時更新されます。
例:2025年は4月・6月・8月に公募あり、交付決定後に契約・納品・実績報告という流れ
申請はIT導入支援事業者(ベンダー)を通じて行うため、事前相談が必須です
保育園で導入可能なICT機器の紹介
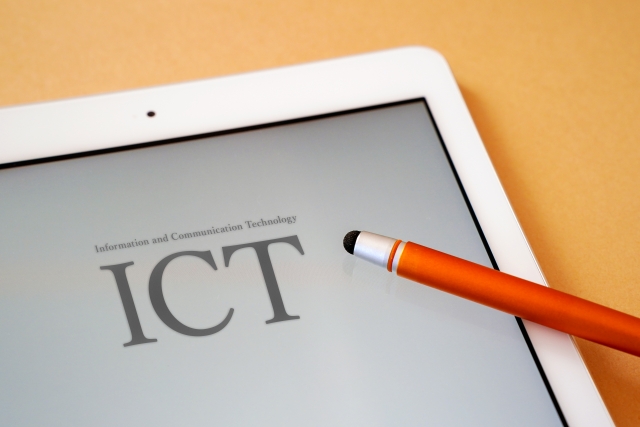
保育現場でのICT化は年々進んでおり、それに伴って補助金の対象となる機器やソフトも多様化しています。ここでは、導入が可能な主なICT機器と、それぞれに対応する補助制度について分かりやすく解説します。対象範囲は自治体により異なるため、事前の確認も忘れずに行いましょう。
タブレット・パソコンなどの基本機器
ICT化に欠かせないのが、タブレットやパソコンといった操作端末です。これらは保育記録、登降園管理、保護者アプリなどの各種システム操作に使用されます。
補助金制度では、システムだけでなくタブレットなどの端末も対象となることが多いため、導入前に確認しておきましょう。
✅ 対応する補助金:
- 保育所等におけるICT化推進等事業(こども家庭庁・自治体)
- IT導入補助金(経済産業省)
保育管理システム(登降園・連絡帳・記録など)
登降園の記録や保護者との連絡、保育日誌などの記録業務を一元管理できるシステムです。ICカードやQRコードを用いた登降園管理や、スマホアプリでの連絡帳送信が可能です。
✅ 対応する補助金:
保育所等におけるICT化推進等事業(保育に関する計画・記録/保護者との連絡/こどもの登降園管理等の業務)
IT導入補助金(ベンダー登録されたサービスであれば可)
セキュリティ・スマートロック関連機器
玄関のスマートロックや、園児の居場所を把握するGPSタグ、午睡中の体動を見守るセンサーなど、安全対策を目的とした機器が該当します。
✅ 対応する補助金:
- 保育環境改善等事業(安全対策)
保育計画・指導案・帳票管理ソフト
年間指導計画や月案・週案、保育日誌などをデジタルで作成・保存・共有できるソフトウェア。複数職員での同時閲覧や過去記録の参照が可能です。
✅ 対応する補助金:
- 保育所等におけるICT化推進等事業(保育に関する計画・記録/
- IT導入補助金
キャッシュレス決済・保護者アプリなど
延長保育料や教材費の集金をキャッシュレスに対応することで、現金管理や会計処理の負担を軽減。保護者側もスマホアプリから決済や確認ができるようになります。
✅ 対応する補助金:
- 保育所等におけるICT化推進等事業(「実費徴収のICT化」枠)
- IT導入補助金
らいん君も助成金対象に!
園児募集を効率化するLINE公式アカウントの構築・運用並走サービス「園児募集らいん君」は、応募受付・日程調整・説明会案内などを自動化でき、業務の負担を軽減できる園児募集支援ツールです。
一部自治体では、未就園児の保護者とのコミュニケーションや園児募集対応も補助対象に含まれる場合があり、「園児募集らいん君」が活用されている事例も出てきています。
✅ 対応する補助金:
・保育所等ICT化推進等事業(厚労省)
∟ 園児募集や保護者連絡を目的としたICTツールが補助対象になるケースあり
・地方自治体の独自制度(例:東京都・横浜市など)
∟ 保護者連絡・業務支援システムの導入支援あり。LINE連携ツールが対象になることも
※補助対象となるかどうかは、自治体の公募要項や担当課への確認が必要です。
ICT技術の活用による保育改善のメリット

ICTの導入は、業務の効率化だけでなく、保育の質を高める大きなチャンスでもあります。
保育士の負担を軽減し、保護者との信頼関係を深め、子どもの安全を守る──そんな日々の保育における重要な課題を、ICTの力で解決できる場面が増えています。ここでは、ICT導入によって得られる代表的な3つのメリットを紹介します。
業務効率化による保育士の負担軽減
ICT機器を導入する最大のメリットは、保育士の業務負担を大きく軽くできることです。たとえば、登降園の打刻をICカードで行えば、手書きの記録が不要になります。
また、月案や保育日誌をシステムで作成すれば、過去データの呼び出しや自動入力機能により、記録の時間が短縮されます。結果として、保育士は子どもと過ごす時間を確保しやすくなり、残業の削減にもつながります。
保護者とのコミュニケーションの向上
保護者向けアプリや連絡帳システムを使えば、日々の連絡がよりスムーズになります。欠席の連絡やお迎え時間の変更、体調の様子などもスマートフォンで簡単に伝えられます。
さらに、写真や動画を共有できる機能もあり、保護者は子どもの様子をリアルタイムで確認できます。こうした情報共有は、保護者の安心感につながり、信頼関係の構築にも効果的です。
子どもの安全管理強化
午睡センサーやGPSタグなどのICT機器を活用することで、安全対策も強化できます。お昼寝中の呼吸状態を自動で確認するセンサーがあれば、職員が頻繁に見回りをしなくても安心です。
また、園外活動時に子どもが持つGPSタグを使えば、現在地の把握ができ、迷子や事故のリスクを減らすことができます。これにより、職員の不安も軽減され、安全で安心な保育が実現します。
補助金の申請から導入後のフォローまで

補助金を活用してICT機器やシステムを導入するには、まず自園が対象となる制度を確認し、公募情報をしっかり把握することが大切です。以下に、主要2制度ごとの一般的な申請・導入の流れをご紹介します。
導入から交付決定までの流れ
【1】保育所等におけるICT化推進等事業(こども家庭庁+自治体)
多くの保育園が利用している公的補助制度では、以下の手順が基本となります。
- 自治体の交付要綱を確認し、対象機器・申請要件を把握
- 見積書や導入計画書を準備
- 自治体へ申請書一式を提出(4〜7月が多い)
- 審査・交付決定通知の受領
- 決定通知後に、システム・機器の発注・導入
- 実績報告を提出し、補助金の交付を受ける
⚠️ 注意点:交付決定前に発注・支払いを行うと、補助金が対象外となる場合があります。自治体のスケジュールとフローに必ず従いましょう。
【2】IT導入補助金(経済産業省)
保育法人が業務支援目的で導入するシステムについては、以下のような手続きが求められます。
- IT導入支援事業者(販売元)と導入内容を相談
- ポータルサイトから電子申請を実施
- 審査・採択結果の通知(通常1〜2か月)
- 採択後に契約・導入
- 実績報告・事後チェック
- 補助金の交付
💡 採用や連絡に活用できるツールを導入したい場合は、まずIT導入支援事業者に相談し、補助対象かどうかを確認しましょう。
申請書類の作成ステップと注意点
補助金の申請には、以下のような書類や準備が共通して必要になります。
制度ごとの違いにも注意しましょう。
| ステップ | 必要書類・注意点 | 対象制度 |
| 1. 導入目的の整理 | 保育の業務軽減、保護者対応の質向上など、具体的な効果を記載 | 両制度共通 |
| 2. 見積書の取得 | 複数業者から取得し、価格妥当性を説明できるように | ICT化推進等事業では特に重要 |
| 3. 機能説明資料 | システムの補助対象機能(登降園・連絡・記録等)に合致していることを明示 | 両制度共通 |
| 4. 支援事業者の有無 | IT導入補助金では、登録された支援事業者経由で申請することが必須 | IT導入補助金のみ |
よくある失敗例とその回避方法
補助金申請でよくあるミスには、以下のようなものがあります。
- 交付決定前に契約・支払いをしてしまった
- 必要書類の不足や不備
- 補助対象外の機器や費用を含めてしまった
特に「保育所等におけるICT化推進等事業」では、交付決定前に発注や支払いを行うと補助対象外となるため、順序の確認が不可欠です。
また「IT導入補助金(経済産業省)」では、事前にIT導入支援事業者と連携し、ポータルサイトで電子申請を行う必要があるため、個人や園単独で進めると不備が出やすいのが注意点です。
これらの失敗を避けるには、早い段階で下記のようなアクションをとることが大切です。
- 自治体の保育課に連絡し、交付要綱・申請様式を入手する
- 書類のひな型や記載例を確認する
- 補助金申請に対応している導入業者と相談する
支援機関や相談窓口の活用もおすすめ
補助金の申請手続きは、初めての方にとって不安が多いものです。そんな時は、以下のようなサポート機関を活用しましょう。
- 自治体の保育課・子育て支援課(ICT化推進等事業の窓口)
- 商工会議所やよろず支援拠点(IT導入補助金の相談窓口)
- ICTベンダーや導入支援企業(申請書類の作成サポート)
- 無料相談を実施する保育ICT関連団体や研修事業者
申請前に専門家へ相談することで、制度の選び間違い・記入ミス・機能の誤認といったトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめと次のステップ

ここまででご紹介してきた内容をふまえ、最後に保育園が取るべきアクションを整理してお伝えします。
補助金活用は今がチャンス!早めの準備を
保育園のICT化は、今や園運営に欠かせない重要な取り組みです。令和7年度も、国や自治体からの支援が整備されており、システムや機器の導入にかかる費用の多くを補助してもらうことが可能です。
業務の効率化はもちろん、保育士の負担軽減や保護者との信頼関係づくり、安全管理の向上など、ICT導入がもたらすメリットは多岐にわたります。
ICT導入を検討している保育園は、このチャンスを逃さずに補助金制度を最大限に活用しましょう。
まずは「らいん君」資料ダウンロードから
弊社でご提供しているサービス「らいん君」も、業務支援ツールとしてICT補助金の対象になり得るサービスです。園児募集や採用活動の手間を大幅に軽減し、効果を最大限伸ばしつつ、業務効率の軽減も目指している方は、ぜひ一度ご検討ください。
導入事例や機能説明は、チポーレの公式ページで詳しくご覧いただけます。
まずは資料をダウンロードして、自園に合った活用方法を探してみてください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。
参考文献1:こども家庭庁「保育業務ワンスオンリーに向けた施設管理プラットフォームの整備」