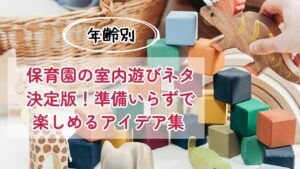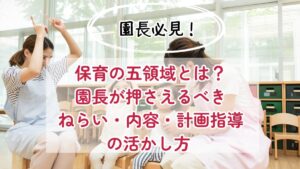保育日誌の書き方に悩むあなたへ!年齢別の文例と明日から使えるコツを紹介
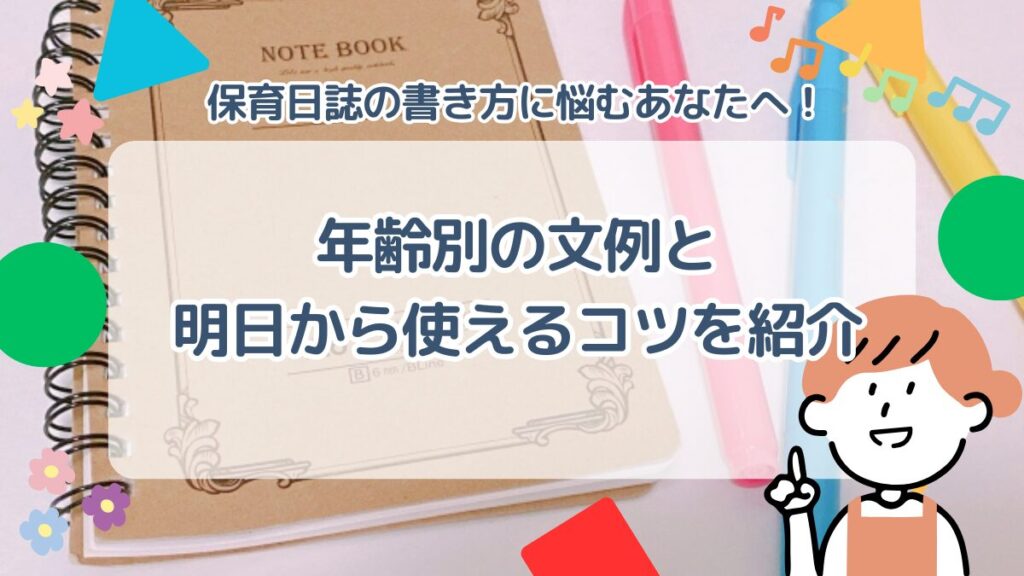
「今日の活動、どう書こう…」「子どもの様子をうまく言葉にできない」。毎日の保育日誌に、そんな悩みを抱えていませんか。保育日誌は、子どもの成長を記録し、保育の質を高めるための大切な業務です。しかし、日々の忙しさの中で、その作成に負担を感じる保育士は少なくありません。この記事では、保育日誌の基本的な書き方から、子どもの成長が伝わる記録のコツ、さらには年齢別の具体的な文例まで、分かりやすく解説します。明日からの日誌作成が少しでも楽になり、子どもの姿を見つめ直す楽しい時間になるよう、一緒に学んでいきましょう。
目次
保育日誌とは?目的と重要性を再確認

保育日誌は、単なる一日の出来事を記録する日記ではありません。子どもたちの成長を支え、より良い保育を実践していくために不可欠なツールです。まずは、その目的と重要性について改めて確認しましょう。
子どもの成長を記録し保育の質を高める
保育日誌の最も重要な目的は、子ども一人ひとりの成長や変化を具体的に記録することです。昨日できなかったことが今日できるようになった瞬間や、友達との関わりの中で見せた表情、夢中になって遊ぶ姿などを言葉にして残すことで、その子の発達の軌跡が見えるようになります。この記録を振り返ることで、保育者は次の活動の計画を立てたり、一人ひとりの発達に応じた適切な援助を考えたりすることができ、結果として保育の質の向上に繋がります。
保育者間の情報共有を円滑にする
保育は、一人の保育者だけで完結するものではなく、チームで行うものです。特に複数担任制のクラスや、早番・遅番などのシフト勤務がある場合、保育日誌は職員間の重要な情報共有ツールとなります。その日にあった出来事や子どもの特筆すべき様子、配慮が必要な事項などを正確に記録・共有することで、どの保育者が対応しても一貫性のある保育を提供できます。これにより、子どもたちは安心して園生活を送ることができるのです。
保護者との信頼関係を築く
保育日誌は、保護者と園をつなぐコミュニケーションツールとしての役割も担います。日誌を通じて園での子どもの様子を伝えることで、保護者は家庭では見られない子どもの一面を知ることができます。言葉での説明に加えて、具体的なエピソードが書かれた日誌は、保育者の専門性や子どもへの温かい眼差しを伝え、保護者の安心感と信頼関係を深めるきっかけとなるでしょう。
保育日誌の基本的な構成と書き方

保育日誌は、園によってフォーマットは異なりますが、一般的に記録すべき項目は共通しています。ここでは、基本的な構成要素と、それぞれの項目で何を書くべきかを解説します。
| 項目 | 記載する内容のポイント |
| ねらい | その日の活動を通して、子どもたちにどんな経験をしてほしいか、何を学んでほしいかを具体的に記述します。 |
| 活動内容 | どのような活動を、どのような流れで行ったかを時系列で記録します。環境構成の工夫なども含めます。 |
| 子どもの姿 | 活動中の子どもの言動や表情、友達との関わりなどを客観的な事実として具体的に描写します。 |
| 保育者の援助・配慮 | 子どもの活動を促したり、安全を確保したりするために、保育者がどのような声かけや働きかけをしたかを記録します。 |
| 考察・反省 | 活動全体を振り返り、「ねらい」が達成できたか、子どもの反応はどうだったかを分析し、今後の保育への課題や改善点を記述します。 |
ねらい:その日の活動で子どもに育みたいこと
「ねらい」は、その日の保育の設計図となる部分です。「~できるようになる」といった到達目標ではなく、「~を楽しむ」「~に親しむ」「~しようとする気持ちが芽生える」のように、子どもの主体的な気持ちや意欲に寄り添った表現で設定することがポイントです。
活動内容:具体的な活動の流れ
ここでは、主活動を中心に一日の流れを記録します。例えば、「戸外遊び」とだけ書くのではなく、「園庭で砂場遊びと固定遊具遊びを行った。砂場では、保育者が用意したカップやシャベルの他に、子どもたちが集めてきた落ち葉や木の実も使い、お店屋さんごっこに発展した」のように、具体的な内容や環境構成の工夫を書き加えることで、状況がより鮮明に伝わります。
子どもの姿:活動中の具体的な言動や様子
子どもの姿を記録する際は、保育者の感想や評価を交えず、見たままの事実を客観的に書くことが大切です。「楽しそうだった」という主観的な表現だけでなく、「『もっとやりたい!』と笑顔で話し、繰り返し滑り台を滑っていた」のように、具体的な子どもの言葉や行動を描写することで、成長の記録としての価値が高まります。
保育者の援助・配慮:子どもの活動を支えるための関わり
子どもの活動に対して、保育者としてどのような意図を持って関わったのかを記録します。例えば、けんかが起きた際に「両者の言い分をそれぞれ聞き、どうすれば一緒に遊べるかを問いかけた」など、具体的な対応を記すことで、保育者自身の振り返りとなり、他の職員が同様の場面に遭遇した際の参考にもなります。
考察・反省:次への保育に繋げる振り返り
一日の保育を振り返り、ねらいに対して子どもの反応はどうだったか、計画通りに進まなかった点はどこか、などを分析します。単なる反省で終わらせず、「〇〇という働きかけは、子どもの意欲を引き出すのに有効だった。次は△△の活動にも取り入れてみたい」のように、次の保育に繋がる前向きな視点で記述することが重要です。
【年齢別】すぐに使える保育日誌の文例集

子どもの発達段階によって、記録で注目すべき視点や表現方法は異なります。ここでは、年齢別の書き方のポイントと文例を紹介します。
0歳児:生理的欲求と情緒の安定を中心に
0歳児は、一人ひとりの生活リズムが異なるため、授乳や睡眠、排泄といった記録が中心になります。また、保育者との愛着関係が形成される重要な時期であるため、スキンシップを通じた情緒の安定に関する記述も大切です。「保育者が『気持ちいいね』と声をかけながら体を撫でると、足をばたつかせて心地よさそうな表情を見せた」のように、子どもの細やかな反応を捉えましょう。
1・2歳児:探索活動と自我の芽生えを捉える
歩行が安定し、言葉も増えてくるこの時期は、身の回りのあらゆるものへの好奇心が高まります。子どもの「やってみたい」という気持ちを尊重し、探索活動に夢中になる姿を記録しましょう。また、「自分でやる!」といった自我の芽生えも見られます。イヤイヤ期の関わりも含め、子どもの気持ちの揺れ動きを丁寧に記すことがポイントです。「おもちゃの取り合いになった際、AちゃんはBくんを叩いてしまった。保育者が間に入り『貸してって言ってみようか』と伝えると、指をさして『かーしーて』と一生懸命に伝えていた」などです。
3歳児:他者との関わりとごっこ遊びの広がり
友達との関わりが増え、ごっこ遊びなどを通じて社会性が育まれる時期です。子ども同士のやり取りや、役割分担の様子、トラブルの解決過程などを記録することで、コミュニケーション能力の育ちが見えてきます。「お店屋さんごっこで、品物がなくなったことに気づいたCちゃんが『葉っぱのお金を集めに行こう』と友達を誘い、遊びが継続するように工夫する姿が見られた」といった記述が考えられます。
4・5歳児:協同性と探求心、就学への意識
グループで共通の目的に向かって活動する協同性が育ちます。ルールのある遊びを楽しんだり、自分たちで目標を立てて取り組んだりする姿を記録しましょう。また、「なぜ?」「どうして?」といった知的な探求心も旺盛になります。図鑑で調べたり、試行錯誤したりする過程を記すことも重要です。「ドッジボールで、どうすれば勝てるかをチームで作戦会議していた。Dくんが『強い人が後ろにいた方が良い』と提案し、みんなで試していた」など、思考力や社会性の育ちを捉えましょう。
保育日誌が「書けない」を解決する4つのコツ

分かってはいても、筆が進まないことは誰にでもあります。そんな時に試してほしい、日誌作成のハードルを下げる4つのコツを紹介します。
5W1Hで子どもの行動を具体的に描写する
何を書けばいいか迷ったら、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の5W1Hを意識して文章を組み立ててみましょう。例えば、「Aちゃんが泣いていた」ではなく、「朝の会(いつ)、保育室のブロックコーナーで(どこで)、Aちゃんが(誰が)、Bくんに赤いブロックを取られてしまったことで(なぜ)、『僕のだったのに』と声をあげて(どのように)、泣いていた(何をした)」と書くことで、状況が格段に具体的になります。
客観的な事実と主観的な解釈を分けて書く
日誌では、実際に起きたこと(事実)と、それを見て保育者が感じたこと(解釈)を区別して書くことが重要です。これらを混同すると、事実が曖昧になったり、思い込みで子どもを評価してしまったりする危険性があります。まずは「〇〇という姿が見られた」という事実を書き、その上で考察の欄に「その行動から△△という気持ちだったのかもしれない」と自分の解釈を加えるようにしましょう。
子どものポジティブな側面に光を当てる
日誌を書いていると、つい「できなかったこと」や「課題点」ばかりに目が行きがちです。しかし、日誌は子どもの成長を記録するものでもあります。昨日より少し成長した点や、その子らしい素敵なところ、友達への優しい関わりなど、ポジティブな側面に意識的に目を向けてみましょう。「〇〇が苦手」という視点だけでなく、「〇〇をしようと挑戦している」という視点で書くことで、日誌が前向きな記録になります。
過去の日誌や他の保育者の記録を参考にする
どうしても言葉が出てこない時は、自分や他の保育者が書いた過去の日誌を読んでみるのがおすすめです。どのような視点で子どもを見ているか、どんな言葉で表現しているかを知ることで、書き方のヒントが得られます。表現を真似ることから始め、徐々に自分らしい記録のスタイルを確立していくと良いでしょう。
保育日誌を書く上での注意点

保育日誌は園の公的な記録文書です。作成にあたっては、内容や言葉遣いに注意を払う必要があります。
個人情報の取り扱いには細心の注意を払う
日誌には子どもの名前や家庭の状況など、多くの個人情報が含まれます。園の外に持ち出さない、施錠できる場所に保管するなど、物理的な管理を徹底することはもちろん、SNSなどに内容を書き込まないなど、情報の取り扱いには最大限の注意が必要です。
専門用語の多用は避け分かりやすい言葉を選ぶ
保育者同士では通じる専門用語も、保護者などが見る可能性を考えると、多用は避けるべきです。例えば「アタッチメントの形成」を「愛着関係を築く」と言い換えるなど、誰が読んでも理解できる平易な言葉で書くことを心がけましょう。
否定的な表現を肯定的な言葉に言い換える
子どもの行動を記録する際は、否定的な表現を使わないように注意が必要です。これは子どもの人格を尊重し、健やかな成長を願う上で非常に重要です。「わがままを言う」は「自分の気持ちを主張できる」、「落ち着きがない」は「好奇心旺盛でいろいろなことに興味がある」のように、ポジティブな言葉に言い換える「リフレーミング」という手法を活用しましょう。
まとめ
保育日誌は、日々の保育を振り返り、子どもの豊かな育ちを支えるための羅針盤です。今回紹介した構成やコツ、文例を参考に、まずは書くことに慣れるところから始めてみてください。日誌を通して子どもの新たな一面を発見する喜びは、保育士という仕事の大きなやりがいの一つとなるはずです。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。