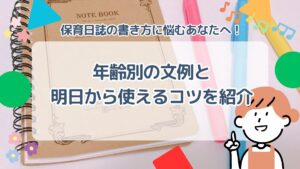【年齢別】保育園の室内遊びネタ決定版!準備いらずで楽しめるアイデア集
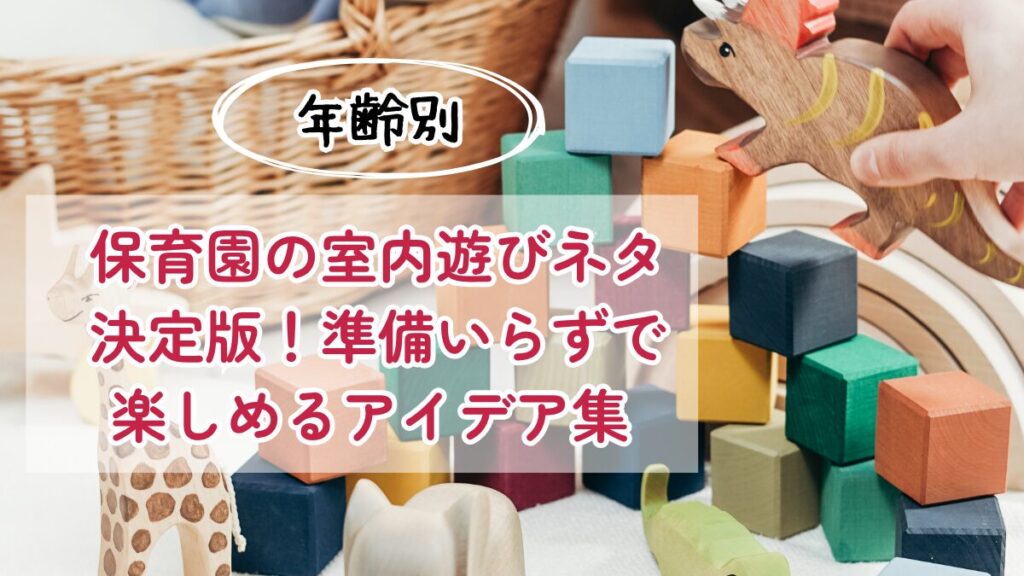
雨の日や気温の高い日が続くと、外で元気に遊ぶことができず、室内での過ごし方に悩む保育士さんも多いのではないでしょうか。子どもたちの有り余る元気を満たしつつ、安全に楽しく過ごせる室内遊びのレパートリーは、いくつあっても困りません。この記事では、0歳児から5歳児まで、年齢別の発達に合わせて楽しめる室内遊びのアイデアを、すぐに実践できる形で豊富にご紹介します。明日からの保育のヒントがきっと見つかるはずです。
目次
室内遊びを行う際の基本的な考え方と注意点

室内遊びを計画し、実行する上で最も大切なのは、子どもたちが安全な環境でのびのびと活動できることです。また、活動内容が子どもたちの発達に合っているか、活動のバランスは取れているかなど、保育士として配慮すべき点がいくつかあります。
子どもの安全を第一に考えた環境設定
室内は戸外に比べてスペースが限られています。子どもたちが安全に遊べるよう、まずは環境設定をしっかりと行いましょう。体を動かす遊びをする際は、机や椅子などを片付けて十分なスペースを確保し、床に危険なものがないか確認します。また、複数の遊びを同時に行う場合は、コーナーを設けて子どもたちが混乱しないように配慮することも大切です。ハサミなどの道具を使う製作活動では、保育士が側につき、正しい使い方を伝えながら安全を見守ります。
| 年齢 | 安全配慮のポイント | 具体例 |
| 0・1歳児 | 誤飲の危険がないか | 小さな部品があるおもちゃは避ける、感触遊びで使う素材は口に入れても安全なものを選ぶ。 |
| 2・3歳児 | 動きが活発になることによる衝突 | 走る、ジャンプするなどの動きがある遊びでは、十分にスペースを確保する。 |
| 4・5歳児 | 道具の正しい使い方 | ハサミやカッターなどを使う際は、事前に使い方を丁寧に説明し、保育士が側で見守る。 |
遊びの「動」と「静」のバランスを意識する
限られた室内空間で過ごしていると、子どもたちはストレスを感じやすくなります。適度に体を動かす「動」の遊びでエネルギーを発散させることは大切ですが、そればかりでは子どもたちが興奮しすぎてしまい、落ち着きがなくなってしまうこともあります。逆に、製作や絵本などの「静」の遊びばかりでは、体を動かしたい欲求が満たされません。保育の時間全体を通して、「動」と「静」の活動をバランス良く組み合わせることで、子どもたちの心と体の安定を図りましょう。
子どもの発達段階に合わせた働きかけ
子どもの発達には個人差がありますが、年齢ごとにある程度の目安があります。0歳児であれば、保育士との愛着関係を築くふれあい遊びが中心になります。言葉を覚え始める2歳児にはごっこ遊び、集団でのルールが理解できるようになる3歳児以上には簡単なゲームが楽しめるようになります。それぞれの年齢の発達段階を理解し、一人ひとりの興味や関心に合わせた遊びを提供することで、子どもの「やってみたい」という気持ちを引き出し、主体的な学びへと繋げることができます。
【年齢別】すぐにできる!保育園の室内遊びアイデア

ここでは、子どもたちの年齢に合わせた室内遊びのアイデアを具体的に紹介します。準備に手間がかからず、すぐに取り入れられるものを中心に集めました。
【0歳児・1歳児】五感を刺激するふれあい遊び
この時期の子どもたちは、特定の保育士との愛着関係を基盤に、身近な人やものに興味を持ち始めます。視覚、聴覚、触覚など五感を優しく刺激する遊びがおすすめです。
- 布遊び
大きな布を波のように揺らしたり、ハンモックのように優しく揺らしたりするだけで、子どもたちは大喜びします。「いないいないばあ」や、歌に合わせて体をくすぐるなど、保育士とのふれあいを楽しみながら、安心感を得ることができます。
- 感触遊び
ビニール袋に入れた色水や、寒天、片栗粉など、安全な素材を使って様々な感触を楽しみます。ひんやりとした感覚や、ドロドロ、フワフワといった不思議な手触りは、子どもの好奇心を大いに刺激します。誤飲には十分注意し、安全な環境で楽しみましょう。
【2歳児】身近な素材で楽しむ感触・模倣遊び
言葉が増え、自我が芽生え始める2歳児は、大人の真似をしたり、何かに見立てて遊んだりすることが大好きになります。指先も器用になってくるため、少し複雑な遊びにも挑戦できるようになります。
- 新聞紙遊び
新聞紙は、破る、丸める、ちぎるといった単純な動作から、剣やドレスを作ったり、雨のように降らせたりと、無限の遊びに発展します。ダイナミックに体を使って遊ぶことで、ストレス発散にも繋がります。
- 粘土遊び
小麦粉粘土やお米の粘土など、安全な素材の粘土を使って、指先をたくさん動かしましょう。丸めたり、伸ばしたりする中で、想像力を働かせ、様々な形を作り出す喜びを味わえます。アレルギーのある子どもには配慮が必要です。
【3歳児】ルールのある遊びに挑戦するゲーム
集団での活動に興味を持ち始め、簡単なルールを理解できるようになる3歳児。友達と関わりながら遊ぶ楽しさを味わえるようなゲームがおすすめです。
- じゃんけん遊び
「じゃんけん列車」や「からだじゃんけん」など、おなじみのじゃんけんも、少しアレンジするだけで立派な集団遊びになります。準備も不要で、室内でも省スペースで楽しめるのが魅力です。
- フルーツバスケット
椅子取りゲームの要素を取り入れた定番の集団遊びです。自分のフルーツを覚え、オニの言うことをよく聞いて素早く移動することで、聞く力や瞬発力が養われます。お題を「フルーツ」から「好きな色」や「朝ごはん」などに変えることで、様々なバリエーションが楽しめます。
【4歳児・5歳児】協調性を育む集団・製作遊び
思考力や社会性がぐんと育つこの時期は、友達と協力して目標を達成したり、少し複雑なルールのあるゲームを楽しんだりできるようになります。手先もさらに器用になり、創造的な製作活動にも意欲的に取り組みます。
- 宝探しゲーム
保育室やホール全体を使って、隠された「宝物」を探し出すゲームです。チームで協力してヒントを解読したり、地図を頼りに探したりすることで、協調性や思考力が育まれます。達成感を味わえるよう、最後にはみんなで宝物を分け合うなどの工夫も良いでしょう。
- カードゲーム・ボードゲーム
カルタやトランプ、簡単なボードゲームなど、ルールに従って友達と競い合う遊びは、思考力や集中力を高めます。勝ち負けを経験する中で、悔しい気持ちを乗り越えたり、相手を思いやったりする心も育ちます。
【種類別】室内遊びのレパートリーを増やそう

遊びのアイデアを「運動」「ごっこ」「製作」「ゲーム」の4つのカテゴリーに分けて紹介します。これらのカテゴリーをバランス良く取り入れることで、保育の幅がさらに広がります。
身体を思いっきり動かす運動遊び
室内でも工夫次第で、子どもたちの運動欲求を満たすことができます。安全に配慮しながら、思いっきり体を動かしましょう。
| 遊びの名称 | 内容 | ねらい |
| サーキット遊び | マットやトンネル、平均台などを組み合わせたコースを周回する。 | 様々な体の動きを経験し、基礎的な運動能力を高める。 |
| 風船遊び | 風船を打ち上げたり、的当てをしたりする。 | 全身を使ってバランス感覚を養う。割れにくく安全。 |
| ハイハイ鬼 | ハイハイで移動しながら鬼ごっこをする。 | 広いスペースがなくても楽しめ、乳児から参加しやすい。 |
想像力を育むごっこ・表現遊び
子どもたちはごっこ遊びを通して、社会のルールを学んだり、他者の気持ちを想像したりします。豊かな表現力を引き出しましょう。
- 忍者ごっこ
抜き足、差し足、忍び足…。忍者の動きを真似るだけで、いつもの保育室が修行の場に変わります。障害物を乗り越えたり、手裏剣を投げたり(新聞紙などで作った安全なもの)と、想像力を働かせながら全身を使って遊びます。
- お店屋さんごっこ
品物やお金を自分たちで作り、売り手と買い手に分かれてやり取りを楽しみます。社会の仕組みを学ぶだけでなく、友達とのコミュニケーション能力も育まれます。
集中力を高める製作・手先を使う遊び
指先を使う細かい作業は、集中力を高め、脳の発達を促します。季節に合わせた製作は、子どもたちの創作意欲を刺激します。
- スライム作り
洗濯のりとホウ砂を混ぜて作る不思議な感触のスライムは、子どもたちに大人気です。材料の分量を変えると固さが変わるなど、実験のような要素も楽しめます。ホウ砂の取り扱いには注意が必要です。
- 廃材を使った製作
牛乳パックやペットボトル、段ボールなど、身近な廃材を使って、乗り物やお家など、ダイナミックな作品作りに挑戦します。友達と協力して作ることで、協調性も育まれます。
みんなで盛り上がるゲーム・集団遊び
ルールのある遊びは、社会性を育む絶好の機会です。クラスの一体感を高め、みんなで楽しむ喜びを分かち合いましょう。
- 椅子取りゲーム
音楽に合わせて椅子の周りを歩き、音楽が止まったら素早く座る定番ゲームです。ドキドキ感を楽しみながら、瞬発力や判断力を養います。負けてしまった子の気持ちにも寄り添う配慮が必要です。
- ハンカチ落とし
座っている人の後ろにそっとハンカチを落とす、これもまた定番のゲームです。気付かれないように歩く緊張感と、追いかけるスリルが楽しめます。
室内遊びのマンネリを防ぐヒント
毎日室内遊びが続くと、どうしても遊びがマンネリ化しがちです。ここでは、子どもも保育士も新鮮な気持ちで遊びに取り組むためのヒントをいくつか紹介します。
いつもの遊びに少しのアレンジを加える
定番の遊びも、少しルールを変えたり、新しい道具を加えたりするだけで、全く新しい遊びに生まれ変わります。例えば、鬼ごっこを「色鬼」に変えてみたり、おままごとに本物の野菜の切れ端を加えてみたり。小さな変化が、子どもたちの新たな興味を引き出すきっかけになります。
子どもたちの「やりたい」を引き出す
保育士が全てを計画するのではなく、「今日は何して遊びたい?」と子どもたちに問いかけてみましょう。子どもたちのアイデアから、予想もしなかった面白い遊びが生まれることがあります。子どもたちが主体的に遊びを創り出す経験は、自信や自己肯定感を育む上で非常に重要です。
季節のイベントと関連付ける
梅雨の時期にはカタツムリや傘の製作をしたり、夏には魚釣りをテーマにしたゲームを楽しんだりと、季節感を取り入れることで、遊びに変化と深みが生まれます。季節の行事や自然現象に関心を持つきっかけにもなり、子どもたちの知的好奇心を刺激します。
まとめ
室内で過ごす時間が増える時期でも、工夫次第で子どもたちの心と体を満たす充実した時間を創り出すことができます。今回ご紹介したアイデアが、日々の保育をより豊かにするための手助けとなれば嬉しいです。安全への配慮を第一に、子どもたちの笑顔があふれる楽しい室内遊びを実践してください。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。