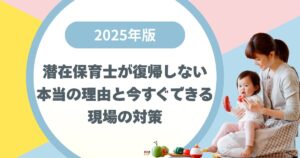お泊まり保育のねらいとは?成功に導くスケジュールと注意点を解説
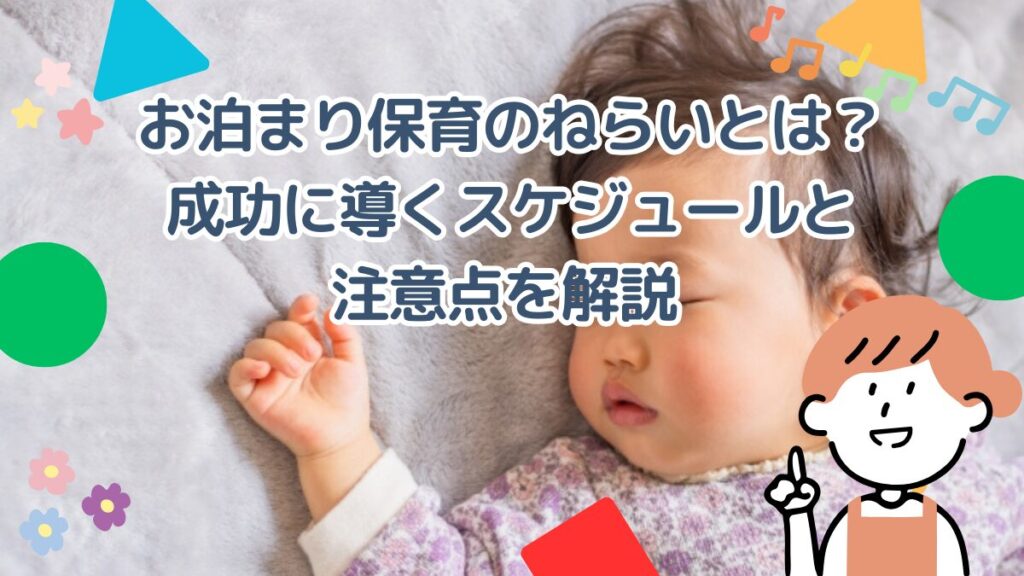
お泊まり保育の季節が近づき、準備に追われている先生方も多いのではないでしょうか。子どもたちの心に残る一大イベントを成功させたいと思う一方で、初めての担当で何から始めるべきか、安全管理は万全か、と不安に感じることもあるでしょう。この記事では、お泊まり保育の基本的な知識から、具体的な計画の立て方、当日盛り上がるレクリエーション、そして保護者の不安に寄り添う方法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、自信を持ってお泊まり保育の準備を進められるようになります。
目次
お泊まり保育とは?子どもたちの成長を促す大切な行事

お泊まり保育は、年長クラスの子どもたちが家族と離れて、保育園や近隣の施設に宿泊する特別な行事です。普段の園生活とは違う環境で一夜を過ごす経験は、子どもたちにとって大きな冒険であり、心身の成長を促す貴重な機会となります。単なる楽しいイベントではなく、教育的な意図を持って計画されています。
お泊まり保育の主なねらい
お泊まり保育には、子どもたちの成長につながる多くのねらいが込められています。主なねらいを理解することで、保育士は一貫した方針を持って子どもたちと関わることができます。
第一に、家族と離れて過ごすことで自立心を養うことがあげられます。自分の荷物を管理したり、寝る準備を自分でしたりといった経験を通じて、「自分ひとりでできた」という達成感が自信につながります。
第二に、集団生活を通して協調性を育むことです。食事の準備や後片付け、ゲームなどの共同作業を友人や保育士と協力して行う中で、他者を思いやる気持ちやルールを守る大切さを学びます。
そして最後に、この特別な体験が心に残る楽しい思い出を作ることです。卒園を控えた子どもたちにとって、仲間と共に過ごした夜は、かけがえのない宝物になるでしょう。
開催時期と対象年齢
お泊まり保育は、主に年長クラス(5歳児) を対象として、6月から8月の夏に行われるのが一般的です。気候が安定しており、キャンプファイヤーや花火、水遊びといった夏ならではの活動を取り入れやすいためです。
場所は、子どもたちが慣れ親しんだ保育園のホールや教室を利用する場合が多いですが、園によっては近隣の宿泊施設や自然の家などを活用することもあります。園内で実施する場合は、いつもの場所が特別な空間に変わる面白さがあり、子どもたちのワクワク感を一層引き立てます。
お泊まり保育の成功は事前準備で決まる

子どもたちが安全に楽しく過ごせるお泊まり保育を実現するためには、周到な事前準備が不可欠です。計画段階から当日までを見通し、職員全体で協力して進めていきましょう。
時期や場所の決定と計画立案
多くの園では、年度初めの職員会議で、前年度の反省点を踏まえながらお泊まり保育の日程や場所、大まかな内容を決定します。園外の施設やバスを利用する場合は、この段階で予約を済ませておく必要があります。
開催日の2〜3ヶ月前には、詳細なタイムスケジュールや活動内容、食事メニュー、アレルギー対応、緊急時マニュアルなどを盛り込んだ実施計画書を作成します。
| 準備項目 | 時期の目安 | 主な内容 |
| 基本計画 | 4月~5月 | 日程、場所、予算の決定。園外施設の場合は予約。 |
| 詳細計画 | 開催2ヶ月前 | タイムスケジュール、活動内容、食事メニューの策定。 |
| 役割分担 | 開催2ヶ月前 | 主担当、救護、食事、夜間巡回などの役割分担を決定。 |
| 保護者説明 | 開催1ヶ月前 | おたより配布、説明会の開催。個別面談の実施。 |
職員間の役割分担と情報共有
お泊まり保育は担任保育士だけでなく、園全体の協力体制で臨むことが重要です。当日の引率、食事の準備、救護、夜間の見守りなど、具体的な役割を事前に明確に分担します。
特に、配慮が必要な子ども(アレルギー、持病、発達上の特性など)に関する情報は、関わる全職員が確実に共有し、誰でも対応できる体制を整えておくことが安全管理の要です。定期的にミーティングを開き、準備の進捗と課題を共有しましょう。
保護者への丁寧な説明とおたより作成
開催の1ヶ月前までには、お泊まり保育の詳細を記載したおたよりを配布し、保護者説明会を実施します。説明会では、スケジュールや持ち物といった事務的な連絡だけでなく、行事のねらいや安全対策について丁寧に伝え、保護者の不安を解消することが大切です。
また、子どもの健康状態やアレルギー、夜間の過ごし方(おねしょの心配など)について、個別に聞き取るためのアンケートや面談の機会を設けると、よりきめ細やかな配慮につながります。
子どもたちの期待感を高める導入
子どもたちにとって、お泊まり保育が楽しみなイベントになるよう、事前の導入も工夫しましょう。過去のお泊まり保育の写真を見せたり、当日行うゲームを少しだけ体験してみたりすることで、期待感は大きく膨らみます。
また、「お泊まり保育で何がしたい?」と子どもたちの意見を聞き、計画に反映させるのも良い方法です。自分たちのアイデアが採用されることで、より主体的に行事に参加する意欲が育まれます。
お泊まり保育当日のタイムスケジュール例

綿密なスケジュールを立てておくことで、当日の運営がスムーズになります。ここでは、園内で実施する場合の一般的なタイムスケジュール例を紹介します。活動内容は園の特色や子どもたちの実態に合わせて調整してください。
【1日目】集合から就寝までの流れ
午後に集合し、非日常的な活動を楽しみながら夜を迎えます。子どもたちの体調や精神的な変化に注意を払いながら進行することが重要です。
| 時間 | 活動内容 | 保育士のポイント |
| 15:00 | 登園、健康チェック、荷物整理 | 保護者から子どもの様子をヒアリングし、体調を最終確認する。 |
| 15:30 | 開会式 | これから始まる楽しい時間への期待感を高める言葉をかける。 |
| 16:00 | 夕食準備(クッキング体験) | 衛生管理を徹底し、安全に調理できるようサポートする。 |
| 18:00 | 夕食、後片付け | みんなで協力して作った食事の楽しさや美味しさを共感し合う。 |
| 19:00 | 夜のお楽しみ会(キャンプファイヤー等) | 安全を最優先し、消火準備などを万全にする。 |
| 20:00 | 入浴、歯磨き、着替え | パニックにならないよう少人数グループで誘導し、落ち着いた雰囲気を作る。 |
| 21:00 | 就寝 | 不安な子には寄り添い、安心できる言葉をかける。絵本の読み聞かせも効果的。 |
【2日目】起床から解散までの流れ
起床後は、朝の清々しい空気の中で活動し、楽しかった二日間を振り返ります。疲れが見える子どももいるため、ゆったりとしたスケジュールを心がけましょう。
| 時間 | 活動内容 | 保育士のポイント |
| 6:30 | 起床、洗顔、着替え | 優しく声をかけて起こし、自分で身支度ができるよう見守る。 |
| 7:00 | 朝の体操、散歩 | 軽い運動で心と体を気持ちよく目覚めさせる。 |
| 7:30 | 朝食、後片付け | 朝食をしっかり食べられるよう声かけをする。 |
| 8:30 | 荷物整理、掃除 | 感謝の気持ちを込めて、使った場所をみんなで綺麗にする。 |
| 9:30 | 閉会式、思い出の共有 | 「お泊まりできた」という達成感を称え、自信につなげる。 |
| 10:00 | 解散 | 保護者に子どもの様子を具体的に伝え、頑張りを共有する。 |
子どもたちが夢中になる!活動・レクリエーションのアイデア

お泊まり保育を特別な思い出にするためには、普段の保育ではできないダイナミックな活動や、夜ならではの雰囲気を活かしたレクリエーションが欠かせません。子どもたちの発達段階や興味に合わせて、安全に楽しめるプログラムを企画しましょう。
園内全体を使ったダイナミックなゲーム
いつもの園庭やホールも、使い方次第で冒険の舞台に変わります。チームで協力して挑戦するゲームは、協調性を育む絶好の機会です。
例えば「宝探しゲーム」では、園内に隠されたヒントカードを頼りに、グループで宝箱を探し出します。また、「スタンプラリー」も人気で、各コーナーにいる先生からクイズや簡単なミッションをクリアしてスタンプを集めます。ゴールした時の達成感は格別です。雨天の場合も想定し、ホールでできる〇✕クイズや、新聞紙を使ったゲームなどを準備しておくと安心です。
夜ならではの特別なお楽しみ会
夜の活動は、お泊まり保育のクライマックスです。園庭で行う「キャンプファイヤー」や「キャンドルサービス」は、幻想的な雰囲気の中で一体感を高めます。火を囲んで歌ったり、ダンスをしたり、先生の出し物を見たりする時間は、忘れられない思い出となるでしょう。
安全に配慮した「手持ち花火」も、夏の夜を彩る素敵なイベントです。火の扱いに関するルールは事前に子どもたちとしっかり確認し、必ず保育士が付き添い、水の入ったバケツを複数用意するなど、安全対策を徹底してください。
協調性を育むクッキング体験
自分たちで夕食を作る経験は、食への興味や感謝の気持ちを育みます。定番のカレーライスやハヤシライスは、野菜の皮むきや型抜き、盛り付けなど、子どもたちが活躍できる工程がたくさんあります。
衛生面には最大限の注意が必要です。調理前の手洗いや消毒はもちろん、食材の管理、加熱時間の確認などを徹底します。栄養士と連携し、アレルギーを持つ子どもへの代替食の準備も万全に行いましょう。自分たちで苦労して作った料理を、みんなで一緒に食べる喜びは、何よりの食育となります。
安全第一!お泊まり保育で特に注意すべき6つのポイント

楽しい思い出は、安全が確保されて初めて作られます。お泊まり保育では、普段と異なる環境や時間帯での活動が多くなるため、事故やトラブルのリスクも高まります。ここでは、特に注意すべき点を6つ挙げ、具体的な対策を解説します。
普段と違う環境での事故やケガの防止
お泊まり保育の特別な雰囲気から、子どもたちは興奮して普段以上に活発になります。廊下を走って転倒したり、友達とふざけて衝突したりといったケガが起こりやすいため、事前の声かけが重要です。「お部屋の中では歩こうね」「暗いから気をつけてね」など、具体的な場面を想定してルールを確認しておきましょう。
また、救護担当の保育士を決め、救急箱の場所と中身を全職員で共有しておくことも必須です。
食物アレルギーへの厳重な対応
食事は、アレルギーを持つ子どもにとって命に関わる重要な場面です。調理・配膳のミスによる誤食は絶対に防がなければなりません。
保護者からの情報提供に基づき、アレルギーを持つ子どもの名前、原因食物、症状、緊急時対応をまとめた一覧表を作成し、全職員で共有します。調理スタッフや栄養士との連携を密にし、調理器具の使い分けや、配膳時のダブルチェックを徹底するなど、厳重な管理体制を構築してください。
安全な入浴のための手順と配慮
浴室は滑りやすく、溺水などの重大事故につながる危険性の高い場所です。一度に多くの園児が入浴すると混乱するため、必ず5〜6人の少人数グループに分け、複数の保育士で対応します。
保育士は着衣のまま介助に専念し、浴槽の中、洗い場、脱衣所それぞれに担当者を配置して、子どもの様子から目を離さないようにします。浴槽のお湯は浅めに張り、湯温の管理にも注意しましょう。
歯磨き中の事故リスクを理解する
楽しい気分のまま歯磨きを始めると、歯ブラシをくわえたまま歩き回ったり、友達とふざけたりして、歯ブラシが喉に刺さるといった重大な事故につながる危険があります。
歯磨きは必ず座って行うことを徹底させ、保育士が側で見守る中で、落ち着いた環境で行えるように配慮してください。「歯磨きが終わるまで、ここでお口をきれいにしようね」と、場所を区切って意識づけをすることも有効です。
持病を持つ子どもへの個別対応
ぜんそくや心疾患などの持病を持つ子どもについては、事前に保護者だけでなく、かかりつけ医とも連携し、緊急時の対応について具体的な指示を受けておくことが望ましいです。
内服薬の管理方法や時間、発作時の対応手順などをまとめた個別計画を作成し、全職員で共有します。環境の変化が症状に影響を与える可能性も考慮し、当日は特に注意深く健康状態を観察してください。
持ち物の管理と記名の徹底
パジャマや下着、タオルなど、普段は使わない多くの私物が集まるため、紛失や取り違えが起こりがちです。事前に配布するおたよりで、すべての持ち物に分かりやすく名前を書くよう、保護者に徹底をお願いしましょう。
子ども自身が自分の荷物を管理できるよう、どこに何を入れるか、家で一緒に準備してもらうことも大切です。
よくある質問と不安への対応策

お泊まり保育は、子どもや保育士だけでなく、保護者にとっても不安がつきものです。寄せられる質問や心配事に丁寧に対応し、信頼関係を築くことが、行事の成功につながります。
保護者の不安にどう寄り添うか
保護者からは、「うちの子は一人で寝られるでしょうか」「おねしょが心配です」「寂しくて泣いてしまったらどうしよう」といった不安が多く寄せられます。まずはその心配な気持ちに共感し、受け止める姿勢が大切です。
その上で、「夜中に何度か見守りをしますのでご安心ください」「おねしょについては、夜間だけ紙パンツを履くなど、お子さんの気持ちに配慮しながら対応します」など、園として具体的な対策を伝えることで、保護者の安心につながります。
| 保護者の主な不安 | 園の対応策の例 |
| おねしょ | 事前に相談を受け、夜間の紙パンツ使用やトイレ誘導など個別に対応する。 |
| 夜泣き・ホームシック | 落ち着くまで保育士が寄り添う体制があることを伝え、安心してもらう。 |
| 食事(偏食など) | 無理強いはせず、楽しい雰囲気の中で一口でも挑戦できるよう促すことを伝える。 |
| 参加の必要性 | 子どもの成長にとっての行事のねらいを丁寧に説明し、参加を無理強いしない。 |
子どもの精神的なストレスへの対応
初めて親元を離れて宿泊する子どもは、大きな不安や寂しさを感じることがあります。なかなか寝付けなかったり、夜中に泣き出したりする子もいるでしょう。
そうした子どもの気持ちに寄り添い、「寂しくなっちゃったんだね」「先生がそばにいるから大丈夫だよ」と優しく声をかけ、抱きしめるなど、情緒的な安定を図ることが重要です。子どもが安心できるまで、根気強く付き合う姿勢が求められます。
保育士自身の勤務に関する疑問
お泊まり保育を担当する保育士からは、「夜は眠れるのですか?」「お風呂はどうするのですか?」といった質問も挙がります。
基本的に、子どもたちが寝ている間も保育士は完全には休めません。夜間の見守りや緊急事態に備え、職員が交代で仮眠を取るのが一般的です。また、保育士の入浴は、子どもの入浴介助が優先されるため、業務開始前や終了後に済ませるか、温かいタオルで体を拭く程度で済ませることがほとんどです。これらの勤務実態については、事前に園として明確な説明が必要です。
まとめ
お泊まり保育は、子どもたちの自立心や協調性を育む、かけがえのない行事です。成功の鍵は、周到な事前準備と、安全への徹底した配慮にあります。この記事で紹介した計画の立て方やスケジュール例、注意点を参考に、子ども、保護者、保育士の全員が笑顔になれるお泊まり保育を実現してください。子どもたちの成長した姿は、保育士にとって何よりの喜びとなるはずです。

【執筆者情報】
上杉 功(うえすぎ いさお)株式会社チポーレ代表取締役。
保育士の採用や園児集客をサポートするサービスを展開中。保育士や園長の負担軽減と保育の質の向上を目指し、現場に即したサービスや情報発信を日々行っております。